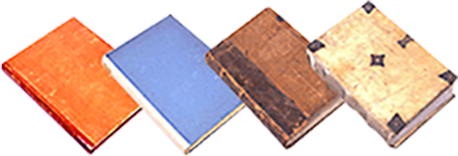第15回 「帚木」より その6
左馬頭が、頼りにする女を語るために、まず信頼ができない女性のことを語る。後半は、恋の歌で綴られている『源氏物語』と、『古事記』における男女の恋の持つ力に言及する。

講師:岡野弘彦
(馬の頭)「さてまた同じ頃、まかりかよひし所は、人もたちまさり、
「さて、また同じころ、まかり通ひし所は、人も立ちまさり心ばせまことにゆゑありと見えぬべく、うち詠み、走り書き、掻い弾く爪音、手つき口つき、みなたどたどしからず、見聞きわたりはべりき。見る目もこともなくはべりしかば、このさがな者を、うちとけたる方にて、時々隠ろへ見はべりしほどは、こよなく心とまりはべりき。この人亡せて後、いかがはせむ、あはれながらも過ぎぬるはかひなくて、しばしばまかり馴るるには、すこしまばゆく艶に好ましきことは、目につかぬ所あるに、うち頼むべくは見えず、かれがれにのみ見せはべるほどに、忍びて心交はせる人ぞありけらし。
かみな月の頃ほひ、月おもしろかりし夜、
神無月のころほひ、月おもしろかりし夜、内裏よりまかではべるに、ある上人来あひて、この車にあひ乗りてはべれば、大納言の家にまかり泊まらむとするに、この人言ふやう、『今宵人待つらむ宿なむ、あやしく心苦しき』とて、この女の家はた、避きぬ道なりければ、荒れたる崩れより池の水かげ見えて、月だに宿る住処を過ぎむもさすがにて、下りはべりぬかし。
もとよりさる心を交はせるにやありけむ、この男いたくすずろきて、門近き廊の簀子だつものに尻かけて、とばかり月を見る。菊いとおもしろく移ろひわたり、風に競へる紅葉の乱れなど、あはれと、げに見えたり。
懐なりける笛取り出でて吹き鳴らし、『蔭もよし』などつづしり謡ふほどに、よく鳴る和琴を、調べととのへたりける、うるはしく掻き合はせたりしほど、けしうはあらずかし。律の調べは、女のものやはらかに掻き鳴らして、簾の内より聞こえたるも、今めきたる物の声なれば、清く澄める月に折つきなからず。
男いたくめでて、簾のもとにあゆみ来て、
男いたくめでて、簾のもとに歩み来て、
『庭の紅葉こそ、踏み分けたる跡もなけれ』などねたます。菊を折りて、
『琴の音も月もえならぬ宿ながら
つれなき人をひきやとめける
悪ろかめり』など言ひて、『今ひと声、聞きはやすべき人のある時、手な残いたまひそ』など、いたくあざれかかれば、女、いたう声つくろひて、
『木枯に吹きあはすめる笛の音を
ひきとどむべき言の葉ぞなき』
となまめき交はすに、憎くなるをも知らで、また、箏の琴を盤渉調に調べて、今めかしく掻い弾きたる爪音、かどなきにはあらねど、まばゆき心地なむしはべりし。ただ時々うち語らふ宮仕へ人などの、あくまでさればみ好きたるは、さても見る限りはをかしくもありぬべし。時々にても、さる所にて忘れぬよすがと思ひたまへむには、頼もしげなくさし過ぐいたりと心おかれて、その夜のことにことつけてこそ、まかり絶えにしか。
伝承の世界をたぐりだす (『古事記』を読む)
「『源氏物語』と紫式部さんとの関係―恐らくこんな五十四帖の形に育て上げてきた一番中心は紫式部に違いないけれども、しかし紫式部一人ではないに違いない。あのころの物語をこんな形にしてきた人々の生みなす力といいましょうか、あるいは語り伝える力を考えておかないと、『源氏物語』を大変読み違えてしまうことになる。殊に、なぜこんなに男女の間の恋の話ばっかり、あるいは恋の歌ばっかり出てくるんだろう。そういう問題になりますと、現代の小説のような、一人の作家の小説のような感じで見たりしていますと、そこのところの評価が、見当が全然狂ってしまうことになる。」
「だから、我々が『古事記』『日本書紀』『風土記』などから、あるいは『万葉集』の古いところなんかもそうですけれども、本当に古代そのままの日本人の心、あるいは生きてきた生き方を手繰り出そうとすれば、これは大変困難な操作ですけれども、一つに堆積してしまった、溶けたオブラートのようにくっついたものを極めて緻密に丹念にはがしていくという、その操作を実はしないと、そこから本当の古代が手繰り出せるというふうにはなっていかないわけです。」
歌は言葉による魂の格闘
「恋というのは、一番端的に言えば、折口は、相手の魂をこちらへ引き寄せようとする。そして相思うというふうな状態だと、相手の異性も自分の魂を自分の方へ引き寄せようとする。そういう猛烈な強い情熱がお互いに働き合って、魂が相手の方へ誘い出され、抜け出ていくような、そういう思いをお互いに感じ合いながら、魂に引かれて肉体も合体する。それが恋の成就なんだ。それを合体させるために、いろんな愛の、恋の行動やゼスチャーがあるわけですけれども、その一番核になっているのが歌ですね。言葉による心の牽引ですね。また、それはそんなに優しいものじゃないんだ。つまり争いなんだ。魂の格闘なんだというわけです。」
須勢理毘売(すせりびめ)の嫉妬 その1
またその神の適后(おほぎさき)須勢理毘売(すせりびめ)の命、いたく嫉妬(うはなりねた)みしたまひき。かれその日子ぢの神侘びて、出雲より倭の国に上りまさむとして、装束(よそひ)し立たす時に、片御手は御馬のくらに繋け、片御足はその御鐙(みあぶみ)に蹈み入れて、歌よみしたまひしく、
ぬばたまの 黒き御衣(みけし)を
まつぶさに 取り装(よそ)ひ
奥(おき)つ鳥 胸(むな)見る時、
羽(は)たたぎも これは宣(ふさ)はず、
辺(へ)つ浪 そに脱ぎ棄(う)て、
そに鳥(どり)の 青き御衣(みけし)を
まつぶさに 取り装(よそ)ひ
奥つ鳥 胸見る時、
羽たたぎも こも宣(ふさ)はず、
辺つ浪 そに脱ぎ棄て、
山県に 蒔(ま)きし あたねつき
染(そめ)木が汁(しる)に 染衣(しめごろも)を
まつぶさに 取り装ひ
奥つ鳥 胸見る時、
羽たたぎも 此(こ)しよろし。
いとこやの 妹の命、
群(むら)鳥の 吾(わ)が群れ往(い)なば、
引け鳥の 吾が引け往なば、
泣かじとは 汝(な)は言ふとも、
山跡(やまと)の 一本(ひともと)すすき
頂傾(うなかぶ)し 汝が泣かさまく
朝雨の さ霧に立たむぞ。
若草の 嬬(つま)の命。
事の 語りごとも こをば。
須勢理毘売(すせりびめ)の嫉妬 その2
ここにそのきさき后 大御さかづき酒坏を取らして、立ち依りささ指挙げて、歌よみしたまひしく、
八千矛の 神の命や、
吾(あ)が大国主。
な汝こそは 男(を)にいませば、
うち廻(み)る 島の埼々(さきざき)
かき廻(み)る 磯の埼おちず、
若草の 嬬(つま)持たせらめ。
吾(あ)はもよ 女(め)にしあれば、
汝(な)を除(き)て 男(を)は無し。
汝(な)を除て 夫(つま)は無し。
文垣(あやがき)の ふはやが下に、
蒸被(むしぶすま) 柔(にこや)が下に、
栲被(たくぶすま) さやぐが下に、
沫雪(あわゆき)の わかやる胸を
栲綱(たくづの)の 白き臂(ただむき)
そ叩(だた)き 叩きまながり
ま玉手 玉手差し纏(ま)き
股長(ももなが)に 寝(い)をしなせ。
豊御酒(とよみき) たてまつらせ。
かく歌ひて、すなはち盞結(うきゆ)ひして、項懸(うなが)けりて、今に至るまで鎮まります。
木の花の佐久夜毘売(さくやひめ)と石長比売(いはながひめ)
ここに大山津見の神、石長(いはなが)比売を返したまへるに因りて、いたく恥ぢて、白し送りて言(まを)さく、「我(あ)が女二人(ふたり)並べたてまつれる由(ゆえ)は、石長比売を使はしては、天つ神の御子の命(みいのち)は、雪零(ふ)り風吹くとも、恒に石(いは)の如く、常磐(ときは)に堅磐(かきは)に動きなくましまさむ。また木(こ)の花(はな)の佐久夜(さくや)毘売を使はしては、木の花の栄ゆるがごと栄えまさむと、誓(うけ)ひて貢進(たてまつ)りき。
ここに石長(いはなが)比売を返さしめて、木(こ)の花(はな)の佐久夜(さくや)毘売をひとり留めたまひつれば、天つ神の御子の御寿(みいのち)は、木の花のあまひのみましまさむとす。
石(いは)の日売(ひめ)のやきもち
その大后石(いは)の日売の命、甚多(いた)く嫉妬(うはなりねた)みしたまひき。かれ天皇の使はせる妾(みめ)たちは、宮の中をもえ臨(のぞ)かず、言(こと)立てば、足も足掻(あが)かに嫉(ねた)みたまひき。
おしてるや 難波の埼よ
出で立ちて わが国見れば、
粟島 淤能碁呂島(おのころじま)、
檳榔(あぢまさ)の 島も見ゆ。
佐気都(さけつ)島見ゆ。
これより後、大后豊(とよ)の楽(あかう)したまはむとして、御綱栢(みつながしは)を採りに、木の国に幸行(い)でましし間に、天皇、八田(やた)の若郎女(わかいらつめ)に婚(まぐはひ)したまひき。ここに大后は、御綱栢を御船に積みみてて還り幸いでます時に、水取(もひとり)の司に駈使(つか)はゆる、吉備の国の児島の郡の仕丁(よほろ)、これおのが国に退(まか)るに、難波の大渡に、後れたる倉人女(くらひとめ)の船に遇ひき。すなはち語りて云はく、「天皇は、このごろ八田の若郎女に婚したまひて昼夜(よるひる)戯遊(たはむ)れますを。もし大后はこの事聞こしめさねかも、しづかに遊び幸行(い)でます」と語りき。
ここにその倉人女、この語る言を聞きて、すなはち御船に追ひ近づきて、 その仕丁(よほろ)が言ひつるごと、状(ありさま)を白しき。ここに大后いたく恨み怒りまして、その御船に載せたる御綱栢は、悉に海に投げ棄(う)てたまひき。かれ其地(そこ)に号(な)づけて御津(みつ)の前(さき)といふ。
つぎねふや 山代河(やましろがは)を
宮上り 吾がのぼれば、
あをによし 那良を過ぎ、
小楯(をだて) 倭(やまと)を過ぎ、
吾(わ)が 見が欲し国は、
葛城(かづらき) 高宮(たかみや)
吾家(わぎへ)のあたり。
奴理能美が家に入ります時に、その奴理能美、おのが養へる三種の虫を、大后に献りき。ここに天皇、その大后のませる殿戸に御立(みたち)したまひて、歌よみしたまひしく、
つぎねふ 山代女の
木钁(こくは)持(も)ち 打ちし大根、
さわさわに 汝(な)が言へせこそ、
うち渡す やがは枝(え)なす
来(き)入り参ゐ来れ。
この天皇と大后と歌よみしたまへる六歌は、志都(しづ)歌の歌ひ返しなり。
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第15回 「帚木」より その6 |
|---|---|
| 収録日 | 2002年4月25日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
講座名:平成14年春期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。