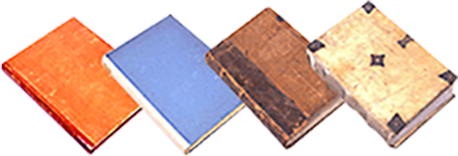第66回 「須磨」より その3
源氏は須磨で在原行平の居た辺りに住む。長雨の頃になり、都にいる人を思い筆をとる。紫の上は落胆し臥せている。内侍(朧月夜)は帝に許され参内するが源氏を思っている。それを帝は怨む。

講師:岡野弘彦
はじめに
・はじめて『源氏物語』を講義した二十代のころ
・折口先生の助言
「折口先生に『どうも自信がなくなって困ります』と言ったら、『君、講義を始めて一年や二年や三年くらいの間、学生の顔を見て講義していてはだめだよ。後ろの壁を見て講義していなさい。まだ研修部は女子学生がいないからいいけれども、女子学生の混じっている部屋なんかでは一層そうだよ』。そんなふうに、あの先生は教室での目の置きどころまで細かく教えてくださる先生でした。『よっぽど慣れるまでは黒板なんかに字なんか書くもんじゃないよ。必ず間違えるから』と。」
おほかたの世の人も、誰かはよろしく思ひきこえむ。
おほかたの世の人も、誰かはよろしく思ひきこえむ。七つになりたまひしこのかた、帝の御前に夜昼さぶらひたまひて、奏したまふことのならぬはなかりしかば、この御いたはりにかからぬ人なく、御徳をよろこばぬやはありし。やむごとなき上達部、弁官などのなかにも多かり。それより下は数知らぬを、思ひ知らぬにはあらねど、さしあたりて、いちはやき世を思ひ憚りて、参り寄るもなし。世ゆすりて惜しみきこえ、下に朝廷をそしり、恨みたてまつれど、「身を捨ててとぶらひ参らむにも、何のかひかは」と思ふにや、かかる折は人悪ろく、恨めしき人多く、「世の中はあぢきなきものかな」とのみ、よろづにつけて思す。
その日は、女君に御物語のどかに聞こえ暮らしたまひて、
その日は、女君に御物語のどかに聞こえ暮らしたまひて、例の、夜深く出でたまふ。狩の御衣など、旅の御よそひ、いたくやつしたまひて、
「月出でにけりな。なほすこし出でて、見だに送りたまへかし。いかに聞こゆべきこと多くつもりにけりとおぼえむとすらむ。一日、二日たまさかに隔たる折だに、あやしういぶせき心地するものを」
とて、御簾巻き上げて、端にいざなひきこえたまへば、女君、泣き沈みたまへるを、ためらひて、ゐざり出でたまへる、月影に、いみじうをかしげにてゐたまへり。「わが身かくてはかなき世を別れなば、いかなるさまにさすらへたまはむ」と、うしろめたく悲しけれど、思し入りたるに、いとどしかるべければ、
「生ける世の別れを知らで契りつつ
命を人に限りけるかな
はかなし」
など、あさはかに聞こえなしたまへば、
「惜しからぬ命に代へて目の前の
別れをしばしとどめてしがな」
「げに、さぞ思さるらむ」と、いと見捨てがたけれど、明け果てなば、はしたなかるべきにより、急ぎ出でたまひぬ。
道すがら、面影につと添ひて、胸もふたがりながら、御舟に乗りたまひぬ。
道すがら、面影につと添ひて、胸もふたがりながら、御舟に乗りたまひぬ。日長きころなれば、追風さへ添ひて、まだ申の時ばかりに、かの浦に着きたまひぬ。かりそめの道にても、かかる旅をならひたまはぬ心地に、心細さもをかしさもめづらかなり。大江殿と言ひける所は、いたう荒れて、松ばかりぞしるしなる。
「唐国に名を残しける人よりも
行方知られぬ家居をやせむ」
渚に寄る波のかつ返るを見たまひて、「うらやましくも」と、うち誦じたまへるさま、さる世の古言なれど、珍しう聞きなされ、悲しとのみ御供の人々思へり。うち顧みたまへるに、来し方の山は霞はるかにて、まことに「三千里の外」の心地するに、櫂の雫も堪へがたし。
「故郷を峰の霞は隔つれど
眺むる空は同じ雲居か」
つらからぬものなくなむ。
おはすべき所は、行平の中納言の、
おはすべき所は、行平の中納言の、「藻塩垂れつつ」侘びける家居近きわたりなりけり。海づらはやや入りて、あはれにすごげなる山中なり。
垣のさまよりはじめて、めづらかに見たまふ。茅屋ども、葦葺ける廊めく屋など、をかしうしつらひなしたり。所につけたる御住まひ、やう変はりて、「かからぬ折ならば、をかしうもありなまし」と、昔の御心のすさび思し出づ。
近き所々の御荘の司召して、さるべきことどもなど、良清朝臣、親しき家司にて、仰せ行なふもあはれなり。時の間に、いと見所ありてしなさせたまふ。水深う遣りなし、植木どもなどして、今はと静まりたまふ心地、うつつならず。国の守も親しき殿人なれば、忍びて心寄せ仕うまつる。かかる旅所ともなう、人騒がしけれども、はかばかしう物をものたまひあはすべき人しなければ、知らぬ国の心地して、いと埋れいたく、「いかで年月を過ぐさまし」と思しやらる。
やうやう事静まりゆくに、長雨のころになりて、
やうやう事静まりゆくに、長雨のころになりて、京のことも思しやらるるに、恋しき人多く、女君の思したりしさま、春宮の御事、若君の何心もなく紛れたまひしなどをはじめ、ここかしこ思ひやりきこえたまふ。
京へ人出だし立てたまふ。二条院へたてまつりたまふと、入道の宮のとは、書きもやりたまはず、昏されたまへり。宮には、
「松島の海人の苫屋もいかならむ
須磨の浦人しほたるるころ
いつとはべらぬなかにも、来し方行く先かきくらし、『汀まさりて』なむ」
尚侍の御もとに、例の、中納言の君の私事のやうにて、中なるに、
「つれづれと過ぎにし方の思うたまへ出でらるるにつけても、
こりずまの浦のみるめのゆかしきを
塩焼く海人やいかが思はむ」
さまざま書き尽くしたまふ言の葉、思ひやるべし。
大殿にも、宰相の乳母にも、仕うまつるべきことなど書きつかはす。
京には、この御文、所々に見たまひつつ、
京には、この御文、所々に見たまひつつ、御心乱れたまふ人びとのみ多かり。二条院の君は、そのままに起きも上がりたまはず、尽きせぬさまに思しこがるれば、さぶらふ人びともこしらへわびつつ、心細う思ひあへり。
もてならしたまひし御調度ども、弾きならしたまひし御琴、脱ぎ捨てたまへる御衣の匂ひなどにつけても、今はと世になからむ人のやうにのみ思したれば、かつはゆゆしうて、少納言は、僧都に御祈りのことなど聞こゆ。二方に御修法などせさせたまふ。かつは、「思し嘆く御心静めたまひて、思ひなき世にあらせたてまつりたまへ」と、心苦しきままに祈り申したまふ。
旅の御宿直物など、調じてたてまつりたまふ。かとりの御直衣、指貫、さま変はりたる心地するもいみじきに、「去らぬ鏡」とのたまひし面影の、げに身に添ひたまへるもかひなし。
出で入りたまひし方、寄りゐたまひし真木柱などを見たまふにも、胸のみふたがりて、ものをとかう思ひめぐらし、世にしほじみぬる齢の人だにあり、まして、馴れむつびきこえ、父母にもなりて生ほし立てならはしたまへれば、恋しう思ひきこえたまへる、ことわりなり。ひたすら世になくなりなむは、言はむ方なくて、やうやう忘れ草も生ひやすらむ、聞くほどは近けれど、いつまでと限りある御別れにもあらで、思すに尽きせずなむ。
入道宮にも、春宮の御事により思し嘆くさま、いとさらなり。
入道宮にも、春宮の御事により思し嘆くさま、いとさらなり。御宿世のほどを思すには、いかが浅く思されむ。年ごろはただものの聞こえなどのつつましさに、「すこし情けあるけしき見せば、それにつけて人のとがめ出づることもこそ」とのみ、ひとへに思し忍びつつ、あはれをも多う御覧じ過ぐし、すくすくしうもてなしたまひしを、「かばかり憂き世の人言なれど、かけてもこの方には言ひ出づることなくて止みぬるばかりの、人の御おもむけも、あながちなりし心の引く方にまかせず、かつはめやすくもて隠しつるぞかし」。あはれに恋しうも、いかが思し出でざらむ。御返りも、すこしこまやかにて、
「このころは、いとど、
塩垂るることをやくにて松島に
年ふる海人も嘆きをぞつむ」
尚侍君の御返りには、
「浦にたく海人だにつつむ恋なれば
くゆる煙よ行く方ぞなき
さらなることどもは、えなむ」
とばかり、いささか書きて、中納言の君の中にあり。思し嘆くさまなど、いみじう言ひたり。あはれと思ひきこえたまふ節々もあれば、うち泣かれたまひぬ。
姫君の御文は、心ことにこまかなりし御返りなれば、あはれなること多くて、
「浦人の潮くむ袖に比べ見よ
波路へだつる夜の衣を」
ものの色、したまへるさまなど、いときよらなり。何ごともらうらうじうものしたまふを、思ふさまにて、「今は他事に心あわたたしう、行きかかづらふ方もなく、しめやかにてあるべきものを」と思すに、いみじう口惜しう、夜昼面影におぼえて、堪へがたう思ひ出でられたまへば、「なほ忍びてや迎へまし」と思す。またうち返し、「なぞや、かく憂き世に、罪をだに失はむ」と思せば、やがて御精進にて、明け暮れ行なひておはす。
大殿の若君の御事などあるにも、いと悲しけれど、「おのづから逢ひ見てむ。頼もしき人々ものしたまへば、うしろめたうはあらず」と、思しなさるるは、なかなか、子の道の惑はれぬにやあらむ。
(つづき)
(8.のつづき)
まことや、騒がしかりしほどの紛れに漏らしてけり。
まことや、騒がしかりしほどの紛れに漏らしてけり。かの伊勢の宮へも御使ありけり。かれよりも、ふりはへ尋ね参れり。浅からぬことども書きたまへり。言の葉、筆づかひなどは、人よりことになまめかしく、いたり深う見えたり。
「なほうつつとは思ひたまへられぬ御住ひをうけたまはるも、明けぬ夜の心惑ひかとなむ。さりとも、年月隔てたまはじと、思ひやりきこえさするにも、罪深き身のみこそ、また聞こえさせむこともはるかなるべけれ。
うきめかる伊勢をの海人を思ひやれ
藻塩垂るてふ須磨の浦にて
よろづに思ひたまへ乱るる世のありさまも、なほいかになり果つべきにか」
と多かり。
「伊勢島や潮干の潟に漁りても
いふかひなきは我が身なりけり」
ものをあはれと思しけるままに、うち置きうち置き書きたまへる、白き唐の紙、四、五枚ばかりを巻き続けて、墨つきなど見所あり。
「あはれに思ひきこえし人を、ひとふし憂しと思ひきこえし心あやまりに、かの御息所も思ひ倦じて別れたまひにし」と思せば、今にいとほしうかたじけなきものに思ひきこえたまふ。折からの御文、いとあはれなれば、御使さへむつましうて、二、三日据ゑさせたまひて、かしこの物語などせさせて聞こしめす。
若やかにけしきある侍の人なりけり。かくあはれなる御住まひなれば、かやうの人もおのづからもの遠からで、ほの見たてまつる御さま、容貌を、いみじうめでたし、と涙落しをりけり。
御返り書きたまふ、言の葉、思ひやるべし。
御返り書きたまふ、言の葉、思ひやるべし。
「かく世を離るべき身と、思ひたまへましかば、同じくは慕ひきこえましものを、などなむ。つれづれと、心細きままに、
伊勢人の波の上漕ぐ小舟にも
うきめは刈らで乗らましものを
海人がつむなげきのなかに塩垂れて
いつまで須磨の浦に眺めむ
聞こえさせむことの、いつともはべらぬこそ、尽きせぬ心地しはべれ」
などぞありける。かやうに、いづこにもおぼつかなからず聞こえかはしたまふ。
花散里も、悲しと思しけるままに書き集めたまへる御心、御心見たまふ、をかしきも目なれぬ心地して、いづれもうち見つつ慰めたまへど、もの思ひのもよほしぐさなめり。
「荒れまさる軒のしのぶを眺めつつ
しげくも露のかかる袖かな」
とあるを、「げに、葎よりほかの後見もなきさまにておはすらむ」と思しやりて、「長雨に築地所々崩れてなむ」と聞きたまへば、京の家司のもとに仰せつかはして、近き国々の御荘の者などもよほさせて、仕うまつるべき由のたまはす。
尚侍の君は、人笑へにいみじう思しくづほるるを、
尚侍の君は、人笑へにいみじう思しくづほるるを、大臣いとかなしうしたまふ君にて、せちに、宮にも内裏にも奏したまひければ、「限りある女御、御息所にもおはせず、公ざまの宮仕へ」と思し直り、また、「かの憎かりしゆゑこそ、いかめしきことも出で来しか」。許されたまひて、参りたまふべきにつけても、なほ心に染みにし方ぞ、あはれにおぼえたまける。
七月になりて参りたまふ。いみじかりし御思ひの名残なれば、
七月になりて参りたまふ。いみじかりし御思ひの名残なれば、人のそしりもしろしめされず、例の、主上につとさぶらはせたまひて、よろづに怨み、かつはあはれに契らせたまふ。
御さま容貌もいとなまめかしうきよらなれど、思ひ出づることのみ多かる心のうちぞ、かたじけなき。御遊びのついでに、
「その人のなきこそ、いとさうざうしけれ。いかにましてさ思ふ人多からむ。何ごとも光なき心地するかな」とのたまはせて、「院の思しのたまはせし御心を違へつるかな。罪得らむかし」
とて、涙ぐませたまふに、え念じたまはず。
「世の中こそ、あるにつけてもあぢきなきものなりけれ、と思ひ知るままに、久しく世にあらむものとなむ、さらに思はぬ。さもなりなむに、いかが思さるべき。近きほどの別れに思ひ落とされむこそ、ねたけれ。生ける世にとは、げに、よからぬ人の言ひ置きけむ」
と、いとなつかしき御さまにて、ものをまことにあはれと思し入りてのたまはするにつけて、ほろほろとこぼれ出づれば、
「さりや。いづれに落つるにか」
とのたまはす。
「今まで御子たちのなきこそ、さうざうしけれ。春宮を院ののたまはせしさまに思へど、よからぬことども出で来めれば、心苦しう」
など、世を御心のほかにまつりごちなしたまふ人びとのあるに、若き御心の、強きところなきほどにて、いとほしと思したることも多かり。
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第66回 「須磨」より その3 |
|---|---|
| 収録日 | 2005年6月18日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
平成17年春期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。