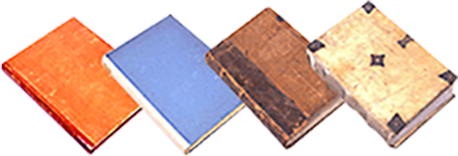第70回 「明石」より その1
御歌の流れと折口信夫曰くの感染教育について。都も須磨も激しい天候が治まらず、紫の上から身を賤しくやつした遣いが来る。桐壺の帝が夢枕に顕ち、即刻舟出をして住吉の神の導きに従うようにと告げる。

講師:岡野弘彦
- 目次
-
- 折口信夫の『死者の書』について
- なほ雨風やまず、雷鳴り静まらで、日ごろになりぬ。
- 二条院よりぞ、あながちにあやしき姿にて、そほち参れる。
- 京にも、この雨風、いとあやしき物のさとしなりとて、
- 「かくしつつ世は尽きぬべきにや」と思さるるに、
- やうやう風なほり、雨の脚しめり、星の光も見ゆるに、
- ひねもすにいりもみつる雷(かみ)の騷ぎに、
- 飽かず悲しくて、「御供に参りなむ」と泣き入りたまひて、
- 渚に小さやかなる舟寄せて、人二、三人ばかり、
- 去(い)ぬる朔日(ついたち)の日の夢に、
- 良清、忍びやかに伝へ申す。
- 知らぬ世界に、めづらしき愁への限り見つれど、
- 浜のさま、げにいと心ことなり。
- 舟より御車にたてまつり移るほど、
- すこし御心静まりては、京の御文ども聞こえたまふ。
折口信夫の『死者の書』について
・川本喜八郎監督人形アニメーション映画『死者の書』について
「折口信夫は日本の古代を舞台にして『死者の書』を書いたわけですけれども、それは決して日本民族だけの問題ではない。大津皇子の背後には、無数の天若彦のような鎮まらない魂の系譜があるわけです。さらに大津皇子の魂と新しく入ってきた仏様に対する深い帰依の思いとが、言ってみれば『死者の書』の彼の人の背景、二上山の雄岳・雌岳の上に彼岸中日の日に姿をあらわす金色の男の姿の中には三重のイメージがダブっているわけです。そういうものが小説を繰り返し読んでいると、だんだんわかってくるわけですけれども、言葉の世界で理解するのはなかなか難しいところがあります。それを幾つも幾つも人形をつくって、人形の微妙な違いによってアニメ映画で示されるというと、また言葉から、文字から伝わってくるものとは違った伝わり方がしてくるわけで、折口信夫が、これを何とかして演劇に、あるいは映画によって表現したかった、その思いが一つの形で実現せられているわけであります。」
・和歌による感染教育
「平安時代、天皇や皇后になるはずの若い貴人には、宮中や藤原氏に伝わっている、力ある和歌や物語をお聞かせすることが大切であった」。まさに『源氏物語』などはその代表であるわけですが、もう一つその奥にある『古今和歌集』『万葉集』というふうな歌、それから物語。それは神話と言ってもいいんですが、「歌や物語そのものに魂が内在していて、歌ったり語ったりすると、その魂の力が働いて貴人の心に感染するのである。だから当時は、博士による漢才(からざえ)の知識教育よりも、女房による和歌や物語(神話)を通した感染教育が重んじられた。この魅力的な説は、日本文学史を深く見通して得た、折口信夫の卓見でした。私は若い宮様や妃殿下、内親王の御進講には、そのことを常に心がけて、古代歌謡や『万葉集』から始めて、世々の勅撰和歌集の秀歌を講義しました。」
なほ雨風やまず、雷鳴り静まらで、日ごろになりぬ。
明石
なほ雨風やまず、雷鳴り静まらで、日ごろになりぬ。いとどものわびしきこと、数知らず、来し方行く先、悲しき御ありさまに、心強うしもえ思(おぼ)しなさず、「いかにせまし。かかりとて、都に帰らむことも、まだ世に許されもなくては、人笑はれなることこそまさらめ。なほ、これより深き山を求めてや、あと絶えなまし」と思すにも、「波風に騒がれてなど、人の言ひ伝へむこと、後の世まで、いと軽々しき名をや流し果てむ」と思し乱る。
御夢にも、ただ同じさまなる物のみ来つつ、まつはしきこゆと見たまふ。雲間もなくて、明け暮るる日数に添へて、京の方もいとどおぼつかなく、「かくながら身をはふらかしつるにや」と、心細う思せど、頭(かしら)さし出づべくもあらぬ空の乱れに、出で立ち参る人もなし。
二条院よりぞ、あながちにあやしき姿にて、そほち参れる。
二条院よりぞ、あながちにあやしき姿にて、そほち参れる。道かひにてだに、人か何ぞとだに御覧じわくべくもあらず、まづ追い払ひつべき賤(しづ)の男(を)の、むつましうあはれに思さるるも、我ながらかたじけなく、屈(く)しにける心のほど思ひ知らる。御文に、
「あさましくを止みなきころのけしきに、いとど空さへ閉づる心地して、眺めやる方なくなむ。
浦風やいかに吹くらむ思ひやる
袖うち濡らし波間なきころ」
あはれに悲しきことども書き集めたまへり。ひきあくるよりいとど汀まさりぬべく、かきくらす心地したまふ。
京にも、この雨風、いとあやしき物のさとしなりとて、
「京にも、この雨風、いとあやしき物のさとしなりとて、仁王会など行はるべしとなむ聞こえはべりし。内裏(うち)に参りたまふ上達部なども、すべて道閉ぢて、政事(まつりごと)も絶えてなむはべる」
など、はかばかしうもあらず、かたくなしう語りなせど、京の方のことと思せばいぶかしうて、御前(おまへ)に召し出でて、問はせたまふ。
「ただ、例の雨のを止みなく降りて、風は時々吹き出でつつ、日ごろになりはべるを、例ならぬことに驚きはべるなり。いとかく、地の底徹(とお)るばかりの氷(ひ)降り、雷の静まらぬことははべらざりき」
など、いみじきさまに驚き懼(お)ぢてをる顔のいとからきにも、心細さぞまさりける。
「かくしつつ世は尽きぬべきにや」と思さるるに、
「かくしつつ世は尽きぬべきにや」と思さるるに、そのまたの日の暁(あかとき)より、風いみじう吹き、潮(しほ)高う満ちて、波の音荒きこと、巌(いはほ)も山も残るまじきけしきなり。雷(かみ)の鳴りひらめくさま、さらに言はむ方なくて、「落ちかかりぬ」とおぼゆるに、ある限りさかしき人なし。
「我はいかなる罪を犯して、かく悲しき目を見るらむ。父母にもあひ見ず、かなしき妻子(めこ)の顔をも見で、死ぬべきこと」
と嘆く。君は御心を静めて、「何ばかりのあやまちにてか、この渚(なぎさ)に命をば極めむ」と、強う思しなせど、いともの騒がしければ、色々の幣帛(みてぐら)ささげさせたまひて、
「住吉の神、近き境(さかひ)を鎮め守りたまふ。まことに迹(あと)を垂れたまふ神ならば、助けたまへ」
と、多くの大願を立てたまふ。おのおのみづからの命をば、さるものにて、かかる御身のまたなき例に沈みたまひぬべことのいみじう悲しき、心を起こして、すこしものおぼゆる限りは、「身に代へてこの御身一つを救ひたてまつらむ」と、とよみて、諸声(もろごゑ)に仏神を念じたてまつる。
「帝王の深き宮に養はれたまひて、いろいろの楽しみにおごりたまひしかど、深き御慈しみ、大八洲(おほやしま)にあまねく、沈める輩(ともがら)をこそ多く浮かべたまひしか。今、何の報いにか、ここら横様なる波風には溺ほれたまはむ。天地、ことわりたまへ。罪なくて罪に当たり、官(つかさ)、位を取られ、家を離れ、境を去りて、明け暮れ安き空なく、嘆きたまふに、かく悲しき目をさへ見、命尽きなむとするは、前(さき)の世の報いか、この世の犯しか、神仏、明らかにましまさば、この愁へやすめたまへ」
と、御社(みやしろ)の方に向きて、さまざまの願を立てたまふ。
また、海の中の龍王、よろづの神たちに願を立てさせたまふに、いよいよ鳴りとどろきて、おはしますに続きたる廊に落ちかかりぬ。炎燃え上がりて、廊は焼けぬ。心魂なくて、ある限り惑ふ。後(うしろ)の方なる大炊殿(おほいどの)とおぼしき屋に移したてまつりて、上下(かみしも)となく立ち込みて、いとらうがはしく泣きとよむ声、雷(いかづち)にも劣らず。空は墨をすりたるやうにて、日も暮れにけり。
◆〔評釈〕「住吉の神」/神仏への祈願の心の伝統(9分~19分)
やうやう風なほり、雨の脚しめり、星の光も見ゆるに、
やうやう風なほり、雨の脚しめり、星の光も見ゆるに、この御座所(おましどころ)のいとめづらかなるも、いとかたじけなくて、寝殿に返し移したてまつらむとするに、
「焼け残りたる方も疎ましげに、そこらの人の踏みとどろかし惑へるに、御簾などもみな吹き散らしてけり」
「夜を明してこそは」
とたどりあへるに、君は御念誦したまひて、思しめぐらすに、いと心あわたたし。
月さし出でて、潮の近く満ち来ける跡もあらはに、名残なほ寄せ返る波荒きを、柴(しば)の戸押し開けて、眺めおはします。近き世界に、ものの心を知り、来し方行く先のことうちおぼえ、とやかくやとはかばかしう悟る人もなし。あやしき海人(あま)どもなどの、貴(たか)き人おはする所とて、集り参りて、聞きも知りたまはぬことどもをさへづりあへるも、いとめづらかなれど、え追ひも払はず。
「この風、今しばし止まざらましかば、潮上(のぼ)りて残る所なからまし。神の助けおろかならざりけり」
と言ふを聞きたまふも、いと心細しといへばおろかなり。
「海にます神の助けにかからずは
潮の八百会(やほあひ)にさすらへなまし」
ひねもすにいりもみつる雷(かみ)の騷ぎに、
ひねもすにいりもみつる雷(かみ)の騷ぎに、さこそいへ、いたう困(こう)じたまひにければ、心にもあらずうちまどろみたまふ。かたじけなき御座所(おましどころ)なれば、ただ寄りゐたまへるに、故院、ただおはしまししさまながら立ちたまひて、
「など、かくあやしき所にはものするぞ」
とて、御手を取りて引き立てたまふ。
「住吉の神の導きたまふままに、はや舟出(ふなで)して、この浦を去りね」
とのたまはす。いとうれしくて、
「かしこき御影に別れたてまつりにしこなた、さまざま悲しきことのみ多くはべれば、今はこの渚に身をや捨てはべりなまし」
と聞こえたまへば、
「いとあるまじきこと。これは、ただいささかなる物の報いなり。我は、位に在りし時、あやまつことなかりしかど、おのづから犯しありければ、その罪を終(お)ふるほど暇なくて、この世を顧(かへり)みざりつれど、いみじき愁へに沈むを見るに、堪へがたくて、海に入り、渚に上(のぼ)り、いたく困(こう)じにたれど、かかるついでに内裏(だいり)に奏すべきことのあるによりなむ、急ぎ上りぬる」
とて、立ち去りたまひぬ。
飽かず悲しくて、「御供に参りなむ」と泣き入りたまひて、
飽かず悲しくて、「御供に参りなむ」と泣き入りたまひて、見上げたまへれば、人もなく、月の顔のみきらきらとして、夢の心地もせず、御けはひ止まれる心地して、空の雲あはれにたなびけり。
年ごろ、夢にうちにも見たてまつらで、恋しうおぼつかなき御さまを、ほのかなれど、さだかに見たてまつりつるのみ、面影におぼえたまひて、「我がかく悲しびを極め、命尽きなむとしつるを、助けに翔(かけ)りたまへる」と、あはれに思すに、「よくぞかかる騷ぎもありける」と、名残頼もしう、うれしうおぼえたまふこと、限りなし。
胸つとふたがりて、なかなかなる御心惑ひに、うつつの悲しきこともうち忘れ、「夢にも御応(いら)へを今すこし聞こえずなりぬること」といぶせさに、「またや見えたまふ」と、ことさらに寝入りたまへど、さらに御目も合はで、暁方になりにけり。
◆〔評釈〕父帝の夢の歴史的背景と物語の内的な響き合い(7分45秒~)
渚に小さやかなる舟寄せて、人二、三人ばかり、
渚に小さやかなる舟寄せて、人二、三人ばかり、この旅の御宿りをさして来(く)。何人ならむと問へば、
「明石の浦より、前(さき)の守新発意(しぼち)の、御舟装ひて参れるなり。源少納言、さぶらひたまはば、対面(たいめ)してことの心とり申さむ」
と言ふ。良清、おどろきて、
「入道は、かの国の得意にて、年ごろあひ語らひはべりつれど、私に、いささかあひ恨むることはべりて、ことなる消息をだに通(かよ)はさで、久しうなりはべりぬるを、波の紛れに、いかなることかあらむ」
と、おぼめく。君の、御夢なども思し合はすることもありて、「はや会へ」とのたまへば、舟に行きて会ひたり。「さばかり激しかりつる波風に、いつの間にか舟出しつらむ」と、心得がたく思へり。
去(い)ぬる朔日(ついたち)の日の夢に、
「去(い)ぬる朔日(ついたち)の日の夢に、さま異なるものの告げ知らすることはべりしかば、信じがたきことと思うたまへしかど、『十三日にあらたなるしるし見せむ。舟装(よそ)ひまうけて、かならず、雨風止まば、この浦にを寄せよ』と、かねて示すことのはべりしかば、試みに舟の装ひをまうけて待ちはべりしに、いかめしき雨、風、雷(いかづち)のおどろかしはべりつれば、人の朝廷(みかど)にも、夢を信じて国を助くるたぐひ多うはべりけるを、用ゐさせたまはぬまでも、このいましめの日を過ぐさず、このよしを告げ申しはべらむとて、舟出だしはべりつるに、あやしき風細う吹きて、この浦に着きはべりつること、まことに神のしるべ違(たが)はずなむ。ここにも、もししろしめすことやはべりつらむ、とてなむ。いと憚り多くはべれど、このよし、申したまへ」
と言ふ。
良清、忍びやかに伝へ申す。
良清、忍びやかに伝へ申す。
君、思しまはすに、夢うつつさまざま静かならず、さとしのやうなることどもを、来し方行く末思し合はせて、
「世の人の聞き伝へむ後のそしりもやすからざるべきを憚りて、まことの神の助けにもあらむを、背くものならば、またこれよりまさりて、人笑はれなる目をや見む。うつつの人の心だになほ苦し。はかなきことをもつつみて、我より齢(よはひ)まさり、もしは位高く、時世(ときよ)の寄せ今一際(ひときは)まさる人には、なびき従ひて、その心むけをたどるべきものなりけり。退きて咎なしとこそ、昔のさかしき人も言ひ置きけれ。げに、かく命を極め、世にまたなき目の限りを見尽くしつ。さらに後(のち)のあとの名をはぶくとても、たけきこともあらじ。夢の中(うち)にも父帝の御教へありつれば、また何ごとをか疑はむ」
と思して、御返りのたまふ。
知らぬ世界に、めづらしき愁への限り見つれど、
「知らぬ世界に、めづらしき愁への限り見つれど、都の方よりとて、言(こと)問ひおこする人もなし。ただ行方なき空の月日の光ばかりを、故郷(ふるさと)の友と眺めはべるに、うれしき釣舟をなむ。かの浦に、静やかに隠ろふべき隈(くま)はべりなむや」
とのたまふ。限りなくよろこび、かしこまり申す。
「ともあれ、かくもあれ、夜の明け果てぬ先に御舟にたてまつれ」
とて、例の親しき限り、四、五人ばかりして、たてまつりぬ。
例の風出で来て、飛ぶやうに明石に着きたまひぬ。ただはひ渡るほどは片時の間といへど、なほあやしきまで見ゆる風の心なり。
浜のさま、げにいと心ことなり。
浜のさま、げにいと心ことなり。人しげう見ゆるのみなむ、御願ひに背きける。入道の領(ろう)占めたる所々、海のつらにも山隠れにも、時々につけて、興をさかすべき渚の苫屋(とまや)、行なひをして後の世のことを思ひ澄ましつべき山水のつらに、いかめしき堂を建てて三昧を行なひ、この世のまうけに、秋の田の実を刈り収め、残りの齢(よはひ)積むべき稲の倉町どもなど、折々、所につけたる見どころありてし集めたり。
高潮に怖(お)ぢて、このころ、娘などは岡辺(べ)の宿に移して住ませければ、この浜の館(たち)に心やすくおはします。
舟より御車にたてまつり移るほど、
舟より御車にたてまつり移るほど、日やうやうさし上がりて、ほのかに見たてまつるより、老(おい)忘れ、齢延(の)ぶる心地して、笑みさかえて、まづ住吉の神を、かつがつ拝みたてまつる。月日の光を手に得たてまつりたる心地して、いとなみ仕うまつること、ことわりなり。
所のさまをばさらにも言はず、作りなしたる心ばへ、木立(こだち)、立石(たていし)、前栽(せんざい)などのありさま、えも言はぬ入江の水など、絵に描(か)かば、心のいたり少なからむ絵師は描き及ぶまじと見ゆ。月ごろの御住まひよりは、こよなくあきらかに、なつかしき。御しつらひなど、えならずして、住まひけるさまなど、げに都のやむごとなき所々に異ならず、艶(えん)にまばゆきさまは、まさりざまにぞ見ゆる。
すこし御心静まりては、京の御文ども聞こえたまふ。
すこし御心静まりては、京の御文ども聞こえたまふ。参れりし使は、今は、
「いみじき道に出で立ちて悲しき目を見る」
と泣き沈みて、あの須磨に留まりたるを召して、身にあまれる物ども多くたまひて遣(つか)はす。むつましき御祈りの師ども、さるべき所々には、このほどの御ありさま、詳しく言ひつかはすべし。
入道の宮ばかりには、めづらかにてよみがへるさまなど聞こえたまふ。二条院のあはれなりしほどの御返りは、書きもやりたまはず、うち置きうち置き、おしのごひつつ聞こえたまふ御けしき、なほことなり。
「返す返すいみじき目の限りを見尽くし果てつるありさまなれば、今はと世を思ひ離るる心のみまさりはべれど、『鏡を見ても』とのたまひし面影の離るる世なきを、かくおぼつかなながらやと、ここら悲しきさまざまのうれはしさは、さしおかれて、
遥かにも思ひやるかな知らざりし
浦よりをちに浦伝ひして
夢のうちなる心地のみして、覚め果てぬほど、いかにひがこと多からむ」
と、げに、そこはかとなく書き乱りたまへるしもぞ、いと見まほしき側(そば)目(め)なるを、「いとこよなき御心ざしのほど」と、人びと見たてまつる。
おのおの、故郷(ふるさと)に心細げなる言(こと)伝(づ)てすべかめり。
を止みなかりし空のけしき、名残なく澄みわたりて、漁(あさり)する海人(あま)ども誇らしげなり。須磨はいと心細く、海人の岩屋もまれなりしを、人しげき厭ひはしたまひしかど、ここはまた、さまことにあはれなること多くて、よろづに思し慰まる。
◆〔評釈〕「貴種流離譚」の典型としての須磨流謫(るたく)〈神話から物語へ〉(19分23秒~)
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第70回 「明石」より その1 |
|---|---|
| 収録日 | 2005年11月19日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
平成17年秋期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。