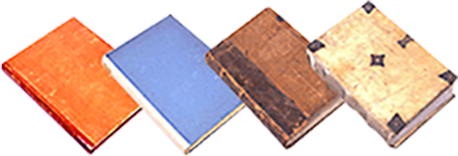第80回 「関屋」~「絵合」その1
近著紹介の後、内弟子として折口信夫を看病した往時を偲ばれる。関屋の巻。空蝉が常陸介と上洛、逢坂の関で石山寺参詣の源氏と再会しやりとりをする。絵合。前斎宮は入内し梅壺女御に。「遥けき仲と神やいさめし」と朱雀院は嘆く。

講師:岡野弘彦
- 目次
-
- はじめに
- 伊予介といひしは、故院崩れさせたまひて、またの年、常陸になりて下りしかば、
- 関入る日しも、この殿、石山に御願果しに詣でたまひけり。
- 九月晦日なれば、紅葉の色々こきまぜ、霜枯れの草むらむらをかしう見えわたるに、
- 石山より出でたまふ御迎へに右衛門佐参りてぞ、まかり過ぎしかしこまりなど申す。
- 佐召し寄せて、御消息あり。
- 「年ごろのとだえも、うひうひしくなりにけれど、心にはいつとなく、
- かかるほどに、この常陸守、老いの積もりにや、悩ましくのみして、
- (休憩)絵合の巻について
- 前斎宮の御参りのこと、中宮の御心に入れてもよほしきこえたまふ。
- 院はいと口惜しく思し召せど、人悪ろければ、御消息など絶えにたるを、
- 殿も渡りたまへるほどにて、「かくなむ」と、女別当御覧ぜさす。
- 「この御返りは、いかやうにか聞こえさせたまふらむ。また、御消息もいかが」
- 「院の御ありさまは、女にて見たてまつらまほしきを、この御けはひも似げなからず、
はじめに
・15年ぶりに歌集を出版
・『バグダッド燃ゆ』(砂子屋書房・2006)
・折口先生の原稿を口述筆記していたころの思い出
・折口信夫『日本古代抒情詩集』
・斎藤茂吉『作歌四十年』
「しかし、そういう先生(折口信夫)が、どんなに偉い先生だと言われている人に診てもらってもわからないんだ。僕はどうせ親きょうだいはみんな癌で亡くなっているんだから、癌で死ぬんだけれども、もう診てもらわなくたっていいよ。病院に入るのは嫌だ、箱根で動かないと言うんです。だんだん弱ってこられると、一緒にいるのが本当に苦しくて、耐えがたくなってくるわけですが、そういう心を支えるためにも、僕は、そのころどういうわけか急に短歌をつくる気持ちがわいてきたので、手帳に歌ばっかり書いて、先生の枕元に座って、何か言われればすぐにしてあげられるようにしていたわけです。そうしたら、また『おっさんは鬼みたいな人や。あれほど一生短歌に情熱をかけ続けてきた僕が、もうその歌すらつくる意欲がなくなっている枕元で、歌ばっかり書いている』。そんなことを言われたら、僕、立つ瀬がないんですけれども、悪いことしたと思っていたら顔は怒っていないんです。優しい顔をして言っているわけで、それはわかりました。ああ、そうか、お前さんもやっと八年目くらいに短歌を本当に自分でつくる気になったかというふうな気持ちで言ってくだすったのだろうと思いますけれども、そのころから私の歌の目が開けたわけですね。」
伊予介といひしは、故院崩れさせたまひて、またの年、常陸になりて下りしかば、
関屋
伊予介といひしは、故院崩れさせたまひて、またの年、常陸になりて下りしかば、かの帚木もいざなはれにけり。須磨の御旅居も遥かに聞きて、人知れず思ひやりきこえぬにしもあらざりしかど、伝へ聞こゆべきよすがだになくて、筑波嶺の山を吹き越す風も、浮きたる心地して、いささかの伝へだになくて、年月かさなりにけり。限れることもなかりし御旅居なれど、京に帰り住みたまひて、またの年の秋ぞ、常陸は上りける。
関入る日しも、この殿、石山に御願果しに詣でたまひけり。
関入る日しも、この殿、石山に御願果しに詣でたまひけり。京より、かの紀伊守などいひし子ども、迎へに来たる人びと、「この殿かく詣でたまふべし」と告げければ、「道のほど騒がしかりなむものぞ」とて、まだ暁より急ぎけるを、女車多く、所狭うゆるぎ来るに、日たけぬ。
打出の浜来るほどに、「殿は、粟田山越えたまひぬ」とて、御前の人びと、道もさりあへず来込みぬれば、関山に皆下りゐて、ここかしこの杉の下に車どもかき下ろし、木隠れに居かしこまりて過ぐしたてまつる。車など、かたへは後らかし、先に立てなどしたれど、なほ、類広く見ゆ。
車十ばかりぞ、袖口、物の色あひなども、漏り出でて見えたる、田舎びず、よしありて、斎宮の御下りなにぞやうの折の物見車思し出でらる。殿も、かく世に栄え出でたまふめづらしさに、数もなき御前ども、皆目とどめたり。
九月晦日なれば、紅葉の色々こきまぜ、霜枯れの草むらむらをかしう見えわたるに、
九月晦日なれば、紅葉の色々こきまぜ、霜枯れの草むらむらをかしう見えわたるに、関屋より、さとくづれ出でたる旅姿どもの、色々の襖のつきづきしき縫物、括り染めのさまも、さるかたにをかしう見ゆ。御車は簾下ろしたまひて、かの昔の小君、今、右衛門佐なるを召し寄せて、
「今日の御関迎へは、え思ひ捨てたまはじ」
などのたまふ御心のうち、いとあはれに思し出づること多かれど、おほぞうにてかひなし。女も、人知れず昔のこと忘れねば、とりかへして、ものあはれなり。
「行くと来とせき止めがたき涙をや
絶えぬ清水と人は見るらむ
え知りたまはじかし」と思ふに、いとかひなし。
石山より出でたまふ御迎へに右衛門佐参りてぞ、まかり過ぎしかしこまりなど申す。
石山より出でたまふ御迎へに右衛門佐参りてぞ、まかり過ぎしかしこまりなど申す。昔、童にて、いとむつましうらうたきものにしたまひしかば、かうぶりなど得しまで、この御徳に隠れたりしを、おぼえぬ世の騷ぎありしころ、ものの聞こえに憚りて、常陸に下りしをぞ、すこし心置きて年ごろは思しけれど、色にも出だしたまはず、昔のやうにこそあらねど、なほ親しき家人のうちには数へたまひけり。
紀伊守といひしも、今は河内守にぞなりにける。その弟の右近将監解けて御供に下りしをぞ、とりわきてなし出でたまひければ、それにぞ誰も思ひ知りて、「などてすこしも、世に従ふ心をつかひけむ」など、思ひ出でける。
佐召し寄せて、御消息あり。
佐召し寄せて、御消息あり。「今は思し忘れぬべきことを、心長くもおはするかな」と思ひゐたり。
「一日は、契り知られしを、さは思し知りけむや。
わくらばに行き逢ふ道を頼みしも
なほかひなしや潮ならぬ海
関守の、さもうらやましく、めざましかりしかな」
とあり。
「年ごろのとだえも、うひうひしくなりにけれど、心にはいつとなく、
「年ごろのとだえも、うひうひしくなりにけれど、心にはいつとなく、ただ今の心地するならひになむ。好き好きしう、いとど憎まれむや」
とて、賜へれば、かたじけなくて持て行きて、
「なほ、聞こえたまへ。昔にはすこし思しのくことあらむと思ひたまふるに、同じやうなる御心のなつかしさなむ、いとどありがたき。すさびごとぞ用なきことと思へど、えこそすくよかに聞こえ返さね。女にては、負けきこえたまへらむに、罪ゆるされぬべし」
など言ふ。今は、ましていと恥づかしう、よろづのこと、うひうひしき心地すれど、めづらしきにや、え忍ばれざりけむ、
「逢坂の関やいかなる関なれば
しげき嘆きの仲を分くらむ
夢のやうになむ」
と聞こえたり。あはれもつらさも、忘れぬふしと思し置かれたる人なれば、折々は、なほ、のたまひ動かしけり。
かかるほどに、この常陸守、老いの積もりにや、悩ましくのみして、
かかるほどに、この常陸守、老いの積もりにや、悩ましくのみして、もの心細かりければ、子どもに、ただこの君の御ことをのみ言ひ置きて、
「よろづのこと、ただこの御心にのみ任せて、ありつる世に変はらで仕うまつれ」
とのみ、明け暮れ言ひけり。
女君、「心憂き宿世ありて、この人にさへ後れて、いかなるさまにはふれ惑ふべきにかあらむ」と思ひ嘆きたまふを見るに、
「命の限りあるものなれば、惜しみ止むべき方もなし。いかでか、この人の御ために残し置く魂もがな。わが子どもの心も知らぬを」
と、うしろめたう悲しきことに、言ひ思へど、心にえ止めぬものにて、亡せぬ。
しばしこそ、「さのたまひしものを」など、情けつくれど、うはべこそあれ、つらきこと多かり。とあるもかかるも世の道理なれば、身一つの憂きことにて、嘆き明かし暮らす。ただ、この河内守のみぞ、昔より好き心ありて、すこし情けがりける。
「あはれにのたまひ置きし、数ならずとも、思し疎までのたまはせよ」
など追従し寄りて、いとあさましき心の見えければ、
「憂き宿世ある身にて、かく生きとまりて、果て果ては、めづらしきことどもを聞き添ふるかな」と、人知れず思ひ知りて、人にさなむとも知らせで、尼になりにけり。
ある人びと、いふかひなしと、思ひ嘆く。守も、いとつらう、
「おのれを厭ひたまふほどに。残りの御齢は多くものしたまふらむ。いかでか過ぐしたまふべき」
などぞ、あいなのさかしらやなどぞ、はべるめる。
(休憩)絵合の巻について
・絵合の巻について
・王氏と藤原氏との勢力争いの渦
・三十代に入り、人間的深まりを感じさせる光源氏
「 それから、皆さんもお感じになっていらっしゃるように、何といっても、二十代の終わりになって、ここでは三十代に入る源氏。十代から二十代前半の光源氏の姿とは非常に違った人間としての成長を遂げている。そして別の意味での人間としての重厚さというものが出てきている。そういう光源氏、思慮深くて、人間に対する判断は実に鋭く持っているけれども、それをあらわすときには決して短絡させた形ではあらわさない。そのかわり、一遍心の底に深く思い秘めた心というものは、単に異性に対する問題だけではなくて、政治的な問題に対しても非常に深い形であらわしてくる。」
前斎宮の御参りのこと、中宮の御心に入れてもよほしきこえたまふ。
絵合
前斎宮の御参りのこと、中宮の御心に入れてもよほしきこえたまふ。こまかなる御とぶらひまで、とり立てたる御後見もなしと思しやれど、大殿は、院に聞こし召さむことを憚りたまひて、二条院に渡したてまつらむことをも、このたびは思し止まりて、ただ知らず顔にもてなしたまへれど、おほかたのことどもは、とりもちて親めききこえたまふ。
院はいと口惜しく思し召せど、人悪ろければ、御消息など絶えにたるを、
院はいと口惜しく思し召せど、人悪ろければ、御消息など絶えにたるを、その日になりて、えならぬ御よそひども、御櫛の筥、打乱の筥、香壷の筥ども、世の常ならず、くさぐさの御薫物ども、薫衣香、またなきさまに、百歩の外を多く過ぎ匂ふまで、心ことに調へさせたまへり。大臣見たまひもせむにと、かねてよりや思しまうけけむ、いとわざとがましかむめり。
殿も渡りたまへるほどにて、「かくなむ」と、女別当御覧ぜさす。
殿も渡りたまへるほどにて、「かくなむ」と、女別当御覧ぜさす。ただ、御櫛の筥の片つ方を見たまふに、尽きせずこまかになまめきて、めづらしきさまなり。挿櫛の筥の心葉に、
「別れ路に添へし小櫛をかことにて
遥けき仲と神やいさめし」
大臣、これを御覧じつけて、思しめぐらすに、いとかたじけなくいとほしくて、わが御心のならひ、あやにくなる身を抓みて、
「かの下りたまひしほど、御心に思ほしけむこと、かう年経て帰りたまひて、その御心ざしをも遂げたまふべきほどに、かかる違ひ目のあるを、いかに思すらむ。御位を去り、もの静かにて、世を恨めしとや思すらむ」など、「我になりて心動くべきふしかな」と、思し続けたまふに、いとほしく、「何にかくあながちなることを思ひはじめて、心苦しく思ほし悩ますらむ。つらしとも、思ひきこえしかど、また、なつかしうあはれなる御心ばへを」など、思ひ乱れたまひて、とばかりうち眺めたまへり。
「この御返りは、いかやうにか聞こえさせたまふらむ。また、御消息もいかが」
「この御返りは、いかやうにか聞こえさせたまふらむ。また、御消息もいかが」
など、聞こえたまへど、いとかたはらいたければ、御文はえ引き出でず。宮は悩ましげに思ほして、御返りいともの憂くしたまへど、
「聞こえたまはざらむも、いと情けなく、かたじけなかるべし」
と、人びとそそのかしわづらひきこゆるけはひを聞きたまひて、
「いとあるまじき御ことなり。しるしばかり聞こえさせたまへ」
と聞こえたまふも、いと恥づかしけれど、いにしへ思し出づるに、いとなまめき、きよらにて、いみじう泣きたまひし御さまを、そこはかとなくあはれと見たてまつりたまひし御幼心も、ただ今のこととおぼゆるに、故御息所の御ことなど、かきつらねあはれに思されて、ただかく、
「別るとて遥かに言ひし一言も
かへりてものは今ぞ悲しき」
とばかりやありけむ。御使の禄、品々に賜はす。大臣は、御返りをいとゆかしう思せど、え聞こえたまはず。
「院の御ありさまは、女にて見たてまつらまほしきを、この御けはひも似げなからず、
「院の御ありさまは、女にて見たてまつらまほしきを、この御けはひも似げなからず、いとよき御あはひなめるを、内裏は、まだいといはけなくおはしますめるに、かく引き違へきこゆるを、人知れず、ものしとや思すらむ」など、憎きことをさへ思しやりて、胸つぶれたまへど、今日になりて思し止むべきことにしあらねば、事どもあるべきさまにのたまひおきて、むつましう思す修理宰相を詳しく仕うまつるべくのたまひて、内裏に参りたまひぬ。
「うけばりたる親ざまには、聞こし召されじ」と、院をつつみきこえたまひて、御訪らひばかりと、見せたまへり。よき女房などは、もとより多かる宮なれば、里がちなりしも参り集ひて、いと二なく、けはひあらまほし。
「あはれ、おはせましかば、いかにかひありて、思しいたづかまし」と、昔の御心ざま思し出づるに、「おほかたの世につけては、惜しうあたらしかりし人の御ありさまぞや。さこそえあらぬものなりけれ。よしありし方は、なほすぐれて」、物の折ごとに思ひ出できこえたまふ。
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第80回 「関屋」~「絵合」その1 |
|---|---|
| 収録日 | 2006年7月8日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
平成18年春期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。