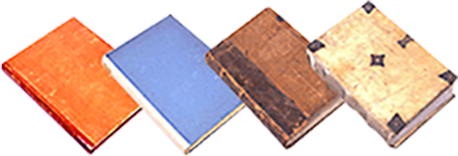第82回 「絵合」より その3
源氏が催す絵合で朱雀院は斎宮下向の儀式の絵を、源氏は須磨の絵日記を出す。琴(きん)の琴など、文才より本才に力を入れて修養した源氏に、出家への兆しが現われ始める。斎藤茂吉、近藤芳美や中村憲吉などの短歌について。

講師:岡野弘彦
はじめに
・折口信夫先生の五十三年祭
「もっとも苦しき たたかいに 最もくるしみ 死にたる むかしの陸軍中尉 折口春洋 ならびにその 父信夫の墓」
・山室山の本居宣長の奥墓
・本居宣長の没後の門人 国学者・平田篤胤と歴史学者・伴信友(『長等(ながら)の山風』の著者)
・本居宣長の墓の歌碑
「那伎迦良ハ何處能土爾成里努斗毛魂波翁乃母登爾住可那牟(なきがらはいづくの土となりぬとも魂は翁のもとにゆかなむ)」
・和歌連作「怒りの墓」
「あらみたま二つあいよる御墓山わかかなしみもここに埋めん」
・出雲系の信仰と気多神社
「大和系の信仰というのは、早く、いわゆる中国化してしまって、漢文風の記述の中に、『日本書紀』的な記述の中にその本当の姿を隠してしまって、出雲系の『出雲風土記』や『古事記』の伝えの方が古風な日本人の心のありようを細やかに察することができるわけですが、その出雲系の神様が日本海側に輾転と流布している代表的な一つが気多神社。海に向かってずっと伸びている能登半島が「けた」ですね。神を迎えるけた、聖なる祭壇であるわけですが、そういう聖なる祭壇の上にいて、一年中神聖な機を織って、海の彼方、空の彼方から祝福に来てくれる霊的なものを迎えようとしている聖なる乙女、棚機(たなばた)つ女(め)、その信仰の面影を地理的に非常によく残している。後のお祭りの中にも、そういう名残がいろいろ残っているところです。そして海岸のタブの森は、また漂着神を迎えるうっそうとした神の依代(よりしろ)であるわけです。自然な依代です。海の彼方から、タブの木、タブの実が漂着してきて、海岸で長い年月の間にうっそうとした森をつくる。そういう森が自然に村の神の森になっていく、そういう場所なんです。そこが信仰をそっちのけにした変な利害関係の争い、そして最高裁まで争いを続けていくというふうな形になっているのは、日本人全体の心の荒廃の象徴のような感じがするわけです。」
その日と定めて、にはかなるやうなれど、
その日と定めて、にはかなるやうなれど、をかしきさまにはかなうしなして、左右の御絵ども参らせたまふ。女房のさぶらひに御座よそはせて、北南方々別れてさぶらふ。殿上人は、後涼殿の簀子に、おのおの心寄せつつさぶらふ。
左は、紫檀の箱に蘇芳の花足、敷物には紫地の唐の錦、打敷は葡萄染の唐の綺なり。童六人、赤色に桜襲の汗衫、衵は紅に藤襲の織物なり。姿、用意など、なべてならず見ゆ。
右は、沈の箱に浅香の下机、打敷は青地の高麗の錦、あしゆひの組、花足の心ばへなど、今めかし。童、青色に柳の汗衫、山吹襲の衵着たり。
皆、御前に舁き立つ。主上の女房、前後と、装束き分けたり。
召しありて、内大臣、権中納言、参りたまふ。
召しありて、内大臣、権中納言、参りたまふ。その日、帥宮も参りたまへり。いとよしありておはするうちに、絵を好みたまへば、大臣の、下にすすめたまへるやうやあらむ、ことことしき召しにはあらで、殿上におはするを、仰せ言ありて御前に参りたまふ。
この判仕うまつりたまふ。いみじう、げに描き尽くしたる絵どもあり。さらにえ定めやりたまはず。
例の四季の絵も、いにしへの上手どものおもしろきことどもを選びつつ、筆とどこほらず描きながしたるさま、たとへむかたなしと見るに、紙絵は限りありて、山水のゆたかなる心ばへをえ見せ尽くさぬものなれば、ただ筆の飾り、人の心に作り立てられて、今のあさはかなるも、昔のあと恥なく、にぎははしく、あなおもしろと見ゆる筋はまさりて、多くの争ひども、今日は方々に興あることも多かり。
朝餉の御障子を開けて、中宮もおはしませば、深うしろしめしたらむと思ふに、
朝餉の御障子を開けて、中宮もおはしませば、深うしろしめしたらむと思ふに、大臣もいと優におぼえたまひて、所々の判ども心もとなき折々に、時々さし応へたまひけるほど、あらまほし。
定めかねて夜に入りぬ。
左はなほ数一つある果てに、「須磨」の巻出で来たるに、
左はなほ数一つある果てに、「須磨」の巻出で来たるに、中納言の御心、騒ぎにけり。あなたにも心して、果ての巻は心ことにすぐれたるを選り置きたまへるに、かかるいみじきものの上手の、心の限り思ひすまして静かに描きたまへるは、たとふべきかたなし。
親王よりはじめたてまつりて、涙とどめたまはず。その世に、「心苦し悲し」と思ほししほどよりも、おはしけむありさま、御心に思ししことども、ただ今のやうに見え、所のさま、おぼつかなき浦々、磯の隠れなく描きあらはしたまへり。
草の手に仮名の所々に書きまぜて、まほの詳しき日記にはあらず、あはれなる歌などもまじれる、たぐひゆかし。誰もこと事思ほさず、さまざまの御絵の興、これに皆移り果てて、あはれにおもしろし。よろづ皆おしゆづりて、左、勝つになりぬ。
夜明け方近くなるほどに、ものいとあはれに思されて、
夜明け方近くなるほどに、ものいとあはれに思されて、御土器(かはらけ)など参るついでに、昔の御物語ども出で来て、
「いはけなきほどより、学問に心を入れてはべりしに、すこしも才(さえ)などつきぬべくや御覧じけむ、院ののたまはせしやう、『才学といふもの、世にいと重くするものなればにやあらむ、いたう進みぬる人の、命、幸ひと並びぬるは、いとかたきものになむ。品高く生まれ、さらでも人に劣るまじきほどにて、あながちにこの道な深く習ひそ』と、諌(いさ)めさせたまひて、本才の方々のもの教へさせたまひしに、つたなきこともなく、またとり立ててこのことと心得ることもはべらざりき。絵描くことのみなむ、あやしくはかなきものから、いかにしてかは心ゆくばかり描きて見るべきと、思ふ折々はべりしを、おぼえぬ山賤(やまがつ)になりて、四方(よも)の海の深き心を見しに、さらに思ひ寄らぬ隈なく至られにしかど、筆のゆく限りありて、心よりはことゆかずなむ思うたまへられしを、ついでなくて、御覧ぜさすべきならねば、かう好き好きしきやうなる、後の聞こえやあらむ」
と、親王(みこ)に申したまへば、
「何の才(ざえ)も、心より放ちて習ふべきわざならねど、道々に物の師あり、学(まね)び所あらむは、事の深さ浅さは知らねど、おのづから移さむに跡ありぬべし。筆取る道と碁打つこととぞ、あやしう魂(たましひ)のほど見ゆるを、深き労なく見ゆるおれ者も、さるべきにて、書き打つたぐひも出で来れど、家の子の中には、なほ人に抜けぬる人の、何ごとをも好み得けるとぞ見えたる。院の御前にて、親王(みこ)たち、内親王、いづれかは、さまざまとりどりの才(ざえ)習はさせたまはざりけむ。その中にも、とり立てたる御心に入れて、伝へ受けとらせたまへるかひありて、『文才(もんざい)をばさるものにて言はず、さらぬことの中には、琴(きん)弾かせたまふことなむ一(いち)の才(ざえ)にて、次には横笛(よこぶえ)、琵琶(びは)、箏(さう)の琴(こと)をなむ、次々に習ひたまへる』と、主上(うへ)も思しのたまはせき。世の人、しか思ひきこえさせたるを、絵はなほ筆のついでにすさびさせたまふあだこととこそ思ひたまへしか、いとかう、まさなきまで、いにしへの墨がきの上手ども、跡をくらうなしつべかめるは、かへりて、けしからぬわざなり」
と、うち乱れて聞こえたまひて、酔(ゑ)ひ泣きにや、院の御こと聞こえ出でて、皆うちしほたれたまひぬ。左はなほ数一つある果てに、「須磨」の巻出で来たるに、中納言の御心、騒ぎにけり。あなたにも心して、果ての巻は心ことにすぐれたるを選り置きたまへるに、かかるいみじきものの上手の、心の限り思ひすまして静かに描きたまへるは、たとふべきかたなし。
親王よりはじめたてまつりて、涙とどめたまはず。その世に、「心苦し悲し」と思ほししほどよりも、おはしけむありさま、御心に思ししことども、ただ今のやうに見え、所のさま、おぼつかなき浦々、磯の隠れなく描きあらはしたまへり。
草の手に仮名の所々に書きまぜて、まほの詳しき日記にはあらず、あはれなる歌などもまじれる、たぐひゆかし。誰もこと事思ほさず、さまざまの御絵の興、これに皆移り果てて、あはれにおもしろし。よろづ皆おしゆづりて、左、勝つになりぬ。
源氏物語のなかの芸能論
・「ほぼ才学なし、和歌をよくす」(『三代実録』)――在原業平評
・漢才(からざえ)と大和魂(やまとごころ)
・平安貴族たちの「よきアマチュアリズム」――その懐の深さ
「現在の我々の遊びという感覚とはかなり違う、もっともっと深くて広い遊び。結局、『遊び』というのは、魂を深く養う魂の遊び、あるいは優れた魂と響き合う心を持つ。そういう『遊び』、それから才の方は『学(まね)び』。つまり真似する。真似するところから才を身につけていくわけです。
そんなふうに考えると、ここのところ、桐壺の帝の光源氏に対する訓戒の一番深い心のありようがくみ取れるだろうと思うんです。言ってあることの具体的なこと、それだけにとどまっていると、少しわからないというか、桐壺の帝の本心というものがなかなかくみ取れないところがあるんですけれども、日本の古来からの伝統的な魂の遊びというものが一番大事なのだ。漢才を学ぶことも貴族の教養としては大事だけれども、そういうことに専門家のように深く打ち込むということは、むしろ要らざることなんだというふうなことを諭していられる。それが当時の大貴族の理想なんだというふうに説いていられると思えば、ここの話はよくわかると思うんです。 」
折口信夫の芸能研究と「まれびと」
・山田孝雄著 『源氏物語の音楽』(宝文館出版)
・「音楽も、日本人の深い魂の遊びの一つなのだ」(折口信夫)
・日本人にとっての「芸能」とは何か ―折口信夫の芸能史講義―
・互いに影響を与え合った柳田国男と折口信夫
・「まれびと」論のヒントとなった台湾の『蛮族調査書』
「漢才を専門にしている文章(もんじょう)博士とか漢学の博士とかいうものは、中古から中世の逸話集なんかにしょっちゅう出てきますでしょう。博士の、歌を詠んだりするときの下手くそな、あるいは全然見当外れの愚かさと、女房のそういう面での滑らか過ぎるほど滑らかな巧みさ。いつも博士の方が負けてしまって醜態をさらす。女房がしたり顔で「勝った」という顔をしている。あれは何か対照的な形ですね。あれはカリカチュアライズせられ、誇張化せられているわけですけれども、中世の逸話集でそういう形になっていく一つのもとは、大和魂は女性の方がより伝承していったわけです。漢才の方は男の方が専門に学(まね)びとっていったわけです。そういうものの対立ですね。 」
二十日あまりの月さし出でて、こなたは、まださやかならねど、
二十日あまりの月さし出でて、こなたは、まださやかならねど、おほかたの空をかしきほどなるに、書司の御琴召し出でて、和琴、権中納言賜はりたまふ。さはいへど、人にまさりてかき立てたまへり。親王、箏の御琴、大臣、琴、琵琶は少将の命婦仕うまつる。上人の中にすぐれたるを召して、拍子賜はす。いみじうおもしろし。
明け果つるままに、花の色も人の御容貌ども、ほのかに見えて、鳥のさへづるほど、心地ゆき、めでたき朝ぼらけなり。禄どもは、中宮の御方より賜はす。親王は、御衣また重ねて賜はりたまふ。
そのころのことには、この絵の定めをしたまふ。
そのころのことには、この絵の定めをしたまふ。
「かの浦々の巻は、中宮にさぶらはせたまへ」
と聞こえさせたまひければ、これが初め、残りの巻々ゆかしがらせたまへど、
「今、次々に」
と聞こえさせたまふ。主上にも御心ゆかせたまひて思し召したるを、うれしく見たてまつりたまふ。
はかなきことにつけても、かうもてなしきこえたまへば、権中納言は、「なほ、おぼえ圧さるべきにや」と、心やましう思さるべかめり。主上の御心ざしは、もとより思ししみにければ、なほ、こまやかに思し召したるさまを、人知れず見たてまつり知りたまひてぞ、頼もしく、「さりとも」と思されける。
さるべき節会どもにも、「この御時よりと、末の人の言ひ伝ふべき例を添へむ」と思し、私ざまのかかるはかなき御遊びも、めづらしき筋にせさせたまひて、いみじき盛りの御世なり。
大臣ぞ、なほ常なきものに世を思して、
大臣ぞ、なほ常なきものに世を思して、今すこしおとなびおはしますと見たてまつりて、なほ世を背きなむと深く思ほすべかめる。
「昔のためしを見聞くにも、齢足らで、官位高く昇り、世に抜けぬる人の、長くえ保たぬわざなりけり。この御世には、身のほどおぼえ過ぎにたり。中ごろなきになりて沈みたりし愁へに代はりて、今までもながらふるなり。今より後の栄えは、なほ命うしろめたし。静かに籠もりゐて、後の世のことをつとめ、かつは齢をも延べむ」と思ほして、山里ののどかなるを占めて、御堂を造らせたまひ、仏経のいとなみ添へてせさせたまふめるに、末の君達、思ふさまにかしづき出だして見むと思し召すにぞ、とく捨てたまはむことは、かたげなる。いかに思しおきつるにかと、いと知りがたし。
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第82回 「絵合」より その3 |
|---|---|
| 収録日 | 2006年9月9日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
平成18年春期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。