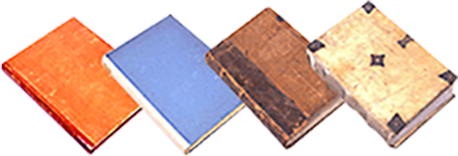第86回 「薄雲」より その2
明石の上は重い心を決め、雪かきくらす中、姫君との別れを惜しむ。源氏は「生ひそめし根も深ければ武隈の松に小松の千代をならべむ」と詠む。女君(紫の上)の手による姫君の御袴(はかま)着(ぎ)は「襷引き結ひたまへる胸つきぞ、うつくしげさ添ひて見えたまへる」。

講師:岡野弘彦
- 目次
-
- 前回の復習
- 「げに、いにしへは、いかばかりのことに定まりたまふべきにかと、
- 尼君、思ひやり深き人にて、「あぢきなし。見たてまつらざらむことは、
- さかしき人の心の占どもにも、もの問はせなどするにも、
- 「乳母をもひき別れなむこと。明け暮れのもの思はしさ、
- 雪、霰がちに、心細さまさりて、「あやしくさまざまに、もの思ふべかりける身かな」と、
- この雪すこし解けて渡りたまへり。例は待ちきこゆるに、
- 暗うおはし着きて、御車寄するより、はなやかにけはひことなるを、
- 若君は、道にて寝たまひにけり。抱き下ろされて、泣きなどはしたまはず。
- 御袴着は、何ばかりわざと思しいそぐことはなけれど、けしきことなり。
- 大堰には、尽きせず恋しきにも、身のおこたりを嘆き添へたり。
- 年も返りぬ。うららかなる空に、思ふことなき御ありさまは、いとどめでたく、
- 山里のつれづれをも絶えず思しやれば、公私もの騒がしきほど過ぐして、
前回の復習
・前回の復習
冬になりゆくままに、川づらの住まひ、いとど心細さまさりて、うはの空なる心地のみしつつ明かし暮らすを、君も、
「なほ、かくては、え過ぐさじ。かの、近き所に思ひ立ちね」
と、すすめたまへど、「つらき所多く心見果てむも、残りなき心地すべきを、いかに言ひてか」などいふやうに思ひ乱れたり。
「さらば、この若君を。かくてのみは、便なきことなり。思ふ心あれば、かたじけなし。対に聞き置きて、常にゆかしがるを、しばし見ならはさせて、袴着の事なども、人知れぬさまならずしなさむとなむ思ふ」
と、まめやかに語らひたまふ。「さ思すらむ」と思ひわたることなれば、いとど胸つぶれぬ。
「改めてやむごとなき方にもてなされたまふとも、人の漏り聞かむことは、なかなかにや、つくろひがたく思されむ」
とて、放ちがたく思ひたる、ことわりにはあれど、
「うしろやすからぬ方にやなどは、な疑ひたまひそ。かしこには、年経ぬれど、かかる人もなきが、さうざうしくおぼゆるままに、前斎宮のおとなびものしたまふをだにこそ、あながちに扱ひきこゆめれば、まして、かく憎みがたげなめるほどを、おろかには見放つまじき心ばへに」
など、女君の御ありさまの思ふやうなることも語りたまふ。
「げに、いにしへは、いかばかりのことに定まりたまふべきにかと、
「げに、いにしへは、いかばかりのことに定まりたまふべきにかと、つてにもほの聞こえし御心の、名残なく静まりたまへるは、おぼろけの御宿世にもあらず、人の御ありさまも、ここらの御なかにすぐれたまへるにこそは」と思ひやられて、「数ならぬ人の並びきこゆべきおぼえにもあらぬを、さすがに、立ち出でて、人もめざましと思すことやあらむ。わが身は、とてもかくても同じこと。生ひ先遠き人の御うへも、つひには、かの御心にかかるべきにこそあめれ。さりとならば、げにかう何心なきほどにや譲りきこえまし」と思ふ。
また、「手を放ちて、うしろめたからむこと。つれづれも慰む方なくては、いかが明かし暮らすべからむ。何につけてか、たまさかの御立ち寄りもあらむ」など、さまざまに思ひ乱るるに、身の憂きこと、限りなし。
尼君、思ひやり深き人にて、「あぢきなし。見たてまつらざらむことは、
尼君、思ひやり深き人にて、
「あぢきなし。見たてまつらざらむことは、いと胸いたかりぬべけれど、つひにこの御ためによかるべからむことをこそ思はめ。浅く思してのたまふことにはあらじ。ただうち頼みきこえて、渡したてまつりたまひてよ。母方からこそ、帝の御子も際々におはすめれ。この大臣の君の、世に二つなき御ありさまながら、世に仕へたまふは、故大納言の、今ひときざみなり劣りたまひて、更衣腹と言はれたまひし、けぢめにこそはおはすめれ。まして、ただ人はなずらふべきことにもあらず。また、親王たち、大臣の御腹といへど、なほさし向かひたる劣りの所には、人も思ひ落とし、親の御もてなしも、え等しからぬものなり。まして、これは、やむごとなき御方々にかかる人、出でものしたまはば、こよなく消たれたまひなむ。ほどほどにつけて、親にもひとふしもてかしづかれぬる人こそ、やがて落としめられぬはじめとはなれ。御袴着のほども、いみじき心を尽くすとも、かかる深山隠れにては、何の栄かあらむ。ただ任せきこえたまひて、もてなしきこえたまはむありさまをも、聞きたまへ」
と教ふ。
さかしき人の心の占どもにも、もの問はせなどするにも、
さかしき人の心の占どもにも、もの問はせなどするにも、なほ「渡りたまひてはまさるべし」とのみ言へば、思ひ弱りにたり。
殿も、しか思しながら、思はむところのいとほしさに、しひてもえのたまはで、
「御袴着のことは、いかやうにか」
とのたまへる御返りに、
「よろづのこと、かひなき身にたぐへきこえては、げに生ひ先もいとほしかるべくおぼえはべるを、たち交じりても、いかに人笑へにや」
と聞こえたるを、いとどあはれに思す。
日など取らせたまひて、忍びやかに、さるべきことなどのたまひおきてさせたまふ。放ちきこえむことは、なほいとあはれにおぼゆれど、「君の御ためによかるべきことをこそは」と念ず。
「乳母をもひき別れなむこと。明け暮れのもの思はしさ、
「乳母をもひき別れなむこと。明け暮れのもの思はしさ、つれづれをもうち語らひて、慰めならひつるに、いとどたつきなきことをさへ取り添へ、いみじくおぼゆべきこと」と、君も泣く。
乳母も、
「さるべきにや、おぼえぬさまにて、見たてまつりそめて、年ごろの御心ばへの、忘れがたう恋しうおぼえたまふべきを、うち絶えきこゆることはよもはべらじ。つひにはと頼みながら、しばしにても、よそよそに、思ひのほかの交じらひしはべらむが、安からずもはべるべきかな」
など、うち泣きつつ過ぐすほどに、師走にもなりぬ。
雪、霰がちに、心細さまさりて、「あやしくさまざまに、もの思ふべかりける身かな」と、
雪、霰がちに、心細さまさりて、「あやしくさまざまに、もの思ふべかりける身かな」と、うち嘆きて、常よりもこの君を撫でつくろひつつ見ゐたり。
雪かきくらし降りつもる朝、来し方行く末のこと、残らず思ひつづけて、例はことに端近なる出で居などもせぬを、汀の氷など見やりて、白き衣どものなよよかなるあまた着て、眺めゐたる様体、頭つき、うしろでなど、「限りなき人と聞こゆとも、かうこそはおはすらめ」と人びとも見る。落つる涙をかき払ひて、
「かやうならむ日、ましていかにおぼつかなからむ」と、らうたげにうち泣きて、
「雪深み深山の道は晴れずとも
なほ文かよへ跡絶えずして」
とのたまへば、乳母、うち泣きて、
「雪間なき吉野の山を訪ねても
心のかよふ跡絶えめやは」
と言ひ慰む。
この雪すこし解けて渡りたまへり。例は待ちきこゆるに、
この雪すこし解けて渡りたまへり。例は待ちきこゆるに、さならむとおぼゆることにより、胸うちつぶれて、人やりならず、おぼゆ。
「わが心にこそあらめ。いなびきこえむをしひてやは、あぢきな」とおぼゆれど、「軽々しきやうなり」と、せめて思ひ返す。
いとうつくしげにて、前にゐたまへるを見たまふに、
「おろかには思ひがたかりける人の宿世かな」
と思ほす。この春より生ふす御髪、尼削ぎのほどにて、ゆらゆらとめでたく、つらつき、まみの薫れるほどなど、言へばさらなり。よそのものに思ひやらむほどの心の闇、推し量りたまふに、いと心苦しければ、うち返しのたまひ明かす。
「何か。かく口惜しき身のほどならずだにもてなしたまはば」
と聞こゆるものから、念じあへずうち泣くけはひ、あはれなり。
姫君は、何心もなく、御車に乗らむことを急ぎたまふ。寄せたる所に、母君みづから抱きて出でたまへり。片言の、声はいとうつくしうて、袖をとらへて、「乗りたまへ」と引くも、いみじうおぼえて、
「末遠き二葉の松に引き別れ
いつか木高きかげを見るべき」
えも言ひやらず、いみじう泣けば、 「さりや、あな苦し」と思して、
「生ひそめし根も深ければ武隈の
松に小松の千代をならべむのどかにを」
と、慰めたまふ。さることとは思ひ静むれど、えなむ堪へざりける。乳母の少将とて、あてやかなる人ばかり、御佩刀、天児やうの物取りて乗る。人だまひによろしき若人、童女など乗せて、御送りに参らす。
道すがら、とまりつる人の心苦しさを、「いかに。罪や得らむ」と思す。
暗うおはし着きて、御車寄するより、はなやかにけはひことなるを、
暗うおはし着きて、御車寄するより、はなやかにけはひことなるを、田舎びたる心地どもは、「はしたなくてや交じらはむ」と思ひつれど、西表をことにしつらはせたまひて、小さき御調度ども、うつくしげに調へさせたまへり。乳母の局には、西の渡殿の、北に当れるをせさせたまへり。
若君は、道にて寝たまひにけり。抱き下ろされて、泣きなどはしたまはず。
若君は、道にて寝たまひにけり。抱き下ろされて、泣きなどはしたまはず。こなたにて御くだもの参りなどしたまへど、やうやう見めぐらして、母君の見えぬをもとめて、らうたげにうちひそみたまへば、乳母召し出でて、慰め紛らはしきこえたまふ。
「山里のつれづれ、ましていかに」と思しやるはいとほしけれど、明け暮れ思すさまにかしづきつつ、見たまふは、ものあひたる心地したまふらむ。
「いかにぞや、人の思ふべき瑕なきことは、このわたりに出でおはせで」
と、口惜しく思さる。
しばしは、人びともとめて泣きなどしたまひしかど、おほかた心やすくをかしき心ざまなれば、上にいとよくつき睦びきこえたまへれば、「いみじううつくしきもの得たり」と思しけり。こと事なく抱き扱ひ、もてあそびきこえたまひて、乳母も、おのづから近う仕うまつり馴れにけり。また、やむごとなき人の乳ある、添へて参りたまふ。
御袴着は、何ばかりわざと思しいそぐことはなけれど、けしきことなり。
御袴着は、何ばかりわざと思しいそぐことはなけれど、けしきことなり。御しつらひ、雛遊びの心地してをかしう見ゆ。参りたまへる客人ども、ただ明け暮れのけぢめしなければ、あながちに目も立たざりき。ただ、姫君の襷引き結ひたまへる胸つきぞ、うつくしげさ添ひて見えたまへる。
大堰には、尽きせず恋しきにも、身のおこたりを嘆き添へたり。
大堰には、尽きせず恋しきにも、身のおこたりを嘆き添へたり。さこそ言ひしか、尼君もいとど涙もろなれど、かくもてかしづかれたまふを聞くはうれしかりけり。何ごとをか、なかなか訪らひきこえたまはむ、ただ御方の人びとに、乳母よりはじめて、世になき色あひを思ひいそぎてぞ、贈りきこえたまひける。
「待ち遠ならむも、いとどさればよ」と思はむに、いとほしければ、年の内に忍びて渡りたまへり。
いとどさびしき住まひに、明け暮れのかしづきぐさをさへ離れきこえて、思ふらむことの心苦しければ、御文なども絶え間なく遣はす。
女君も、今はことに怨じきこえたまはず、うつくしき人に罪ゆるしきこえたまへり。
年も返りぬ。うららかなる空に、思ふことなき御ありさまは、いとどめでたく、
年も返りぬ。うららかなる空に、思ふことなき御ありさまは、いとどめでたく、磨き改めたる御よそひに、参り集ひたまふめる人の、おとなしきほどのは、七日、御よろこびなどしたまふ、ひき連れたまへり。
若やかなるは、何ともなく心地よげに見えたまふ。次々の人も、心のうちには思ふこともやあらむ、うはべは誇りかに見ゆる、ころほひなりかし。
東の院の対の御方も、ありさまは好ましう、あらまほしきさまに、さぶらふ人びと、童女の姿など、うちとけず、心づかひしつつ過ぐしたまふに、近きしるしはこよなくて、のどかなる御暇の隙などには、ふとはひ渡りなどしたまへど、夜たち泊りなどやうに、わざとは見えたまはず。
ただ、御心ざまのおいらかにこめきて、「かばかりの宿世なりける身にこそあらめ」と思ひなしつつ、ありがたきまでうしろやすくのどかにものしたまへば、をりふしの御心おきてなども、こなたの御ありさまに劣るけぢめこよなからずもてなしたまひて、あなづりきこゆべうはあらねば、同じごと、人参り仕うまつりて、別当どもも事おこたらず、なかなか乱れたるところなく、目やすき御ありさまなり。
山里のつれづれをも絶えず思しやれば、公私もの騒がしきほど過ぐして、
山里のつれづれをも絶えず思しやれば、公私もの騒がしきほど過ぐして、渡りたまふとて、常よりことにうち化粧じたまひて、桜の御直衣に、えならぬ御衣ひき重ねて、たきしめ、装束きたまひて、まかり申したまふさま、隈なき夕日に、いとどしくきよらに見えたまふを、女君、ただならず見たてまつり送りたまふ。
姫君は、いはけなく御指貫の裾にかかりて、慕ひきこえたまふほどに、外にも出でたまひぬべければ、立ちとまりて、いとあはれと思したり。こしらへおきて、「明日帰り来む」と、口ずさびて出でたまふに、渡殿の戸口に待ちかけて、中将の君して聞こえたまへり。
「舟とむる遠方人のなくはこそ
明日帰り来む夫と待ち見め」
いたう馴れて聞こゆれば、いとにほひやかにほほ笑みて、
「行きて見て明日もさね来むなかなかに
遠方人は心置くとも」
何事とも聞き分かでされありきたまふ人を、上はうつくしと見たまへば、遠方人のめざましきも、こよなく思しゆるされにたり。
「いかに思ひおこすらむ。われにて、いみじう恋しかりぬべきさまを」
と、うちまもりつつ、ふところに入れて、うつくしげなる御乳をくくめたまひつつ、戯れゐたまへる御さま、見どころ多かり。御前なる人々は、
「などか、同じくは」
「いでや」
など、語らひあへり。
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第86回 「薄雲」より その2 |
|---|---|
| 収録日 | 2006年11月25日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
平成18年秋期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。