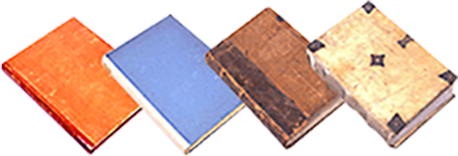第95回 「乙女」より その3
(内)大臣は冠者の君(夕霧)をもてなし、夕霧に笛を与える。内大臣はひそひそ話を聞き、夕霧と雲居雁の間を知る。内大臣は大宮を訪ね、不満を言う。内大臣は乳母と語り、乳母や女房たちは嘆く。何も知らない夕霧が大宮の許に来る。夕霧と雲居雁は煩悶する。

講師:岡野弘彦
- 目次
-
- 「こなたに」とて、御几帳隔てて入れたてまつりたまへり。
- 大臣出でたまひぬるやうにて、忍びて人にもののたまふとて立ちたまへりけるを、
- 殿は、道すがら思すに、
- 二日ばかりありて、参りたまへり。
- 「いかやうなることにてか、今さらの齢の末に、心置きては思さるらむ」
- さるにても、かかることなむと、知らせたまひて、ことさらにもてなし、
- 姫君は、何心もなくておはするに、さしのぞきたまへれば、
- 「よし、しばし、かかること漏らさじ。
- 宮は、いといとほしと思すなかにも、男君の御かなしさはすぐれたまふにやあらむ、
- かく騒がるらむとも知らで、冠者の君参りたまへり。
- 「いとど文なども通はむことのかたきなめり」と思ふに、
- 独り言を聞きたまひけるも恥づかしうて、
- あいなくもの恥づかしうて、わが御方にとく出でて、御文書きたまへれど、
「こなたに」とて、御几帳隔てて入れたてまつりたまへり。
「こなたに」とて、御几帳隔てて入れたてまつりたまへり。
「をさをさ対面もえ賜はらぬかな。などかく、この御学問のあながちならむ。才のほどよりあまり過ぎぬるもあぢきなきわざと、大臣も思し知れることなるを、かくおきてきこえたまふ、やうあらむとは思ひたまへながら、かう籠もりおはすることなむ、心苦しうはべる」
と聞こえたまひて、
「時々は、ことわざしたまへ。笛の音にも古事は、伝はるものなり」
とて、御笛たてまつりたまふ。
いと若うをかしげなる音に吹きたてて、いみじうおもしろければ、御琴どもをばしばし止めて、大臣、拍子おどろおどろしからずうち鳴らしたまひて、
「萩が花摺り」
など歌ひたまふ。
「大殿も、かやうの御遊びに心止めたまひて、いそがしき御政事どもをば逃れたまふなりけり。げに、あぢきなき世に、心のゆくわざをしてこそ、過ぐしはべりなまほしけれ」
などのたまひて、御土器参りたまふに、暗うなれば、御殿油参り、御湯漬、くだものなど、誰も誰もきこしめす。
姫君はあなたに渡したてまつりたまひつ。しひて気遠くもてなしたまひ、「御琴の音ばかりをも聞かせたてまつらじ」と、今はこよなく隔てきこえたまふを、
「いとほしきことありぬべき世なるこそ」
と、近う仕うまつる大宮の御方のねび人ども、ささめきけり。
大臣出でたまひぬるやうにて、忍びて人にもののたまふとて立ちたまへりけるを、
大臣出でたまひぬるやうにて、忍びて人にもののたまふとて立ちたまへりけるを、やをらかい細りて出でたまふ道に、かかるささめき言をするに、あやしうなりたまひて、御耳とどめたまへば、わが御うへをぞ言ふ。
「かしこがりたまへど、人の親よ。おのづから、おれたることこそ出で来べかめれ」
「子を知るといふは、虚言なめり」
などぞ、つきしろふ。
「あさましくもあるかな。さればよ。思ひ寄らぬことにはあらねど、いはけなきほどにうちたゆみて。世は憂きものにもありけるかな」
と、けしきをつぶつぶと心得たまへど、音もせで出でたまひぬ。
御前駆追ふ声のいかめしきにぞ、
「殿は、今こそ出でさせたまひけれ」
「いづれの隈におはしましつらむ」
「今さへかかる御あだけこそ」
と言ひあへり。ささめき言の人びとは、
「いとかうばしき香のうちそよめき出でつるは、冠者の君のおはしつるとこそ思ひつれ」
「あな、むくつけや。しりう言や、ほの聞こしめしつらむ。わづらはしき御心を」
と、わびあへり。
殿は、道すがら思すに、
殿は、道すがら思すに、
「いと口惜しく悪しきことにはあらねど、めづらしげなきあはひに、世人も思ひ言ふべきこと。大臣の、しひて女御をおし沈めたまふもつらきに、わくらばに、人にまさることもやとこそ思ひつれ、ねたくもあるかな」
と思す。殿の御仲の、おほかたには昔も今もいとよくおはしながら、かやうの方にては、挑みきこえたまひし名残も思し出でて、心憂ければ、寝覚がちにて明かしたまふ。
「大宮をも、さやうのけしきには御覧ずらむものを、世になくかなしくしたまふ御孫にて、まかせて見たまふならむ」
と、人びとの言ひしけしきを、ねたしと思すに、御心動きて、すこし男々しくあざやぎたる御心には、静めがたし。
二日ばかりありて、参りたまへり。
二日ばかりありて、参りたまへり。しきりに参りたまふ時は、大宮もいと御心ゆき、うれしきものに思いたり。御尼額ひきつくろひ、うるはしき御小袿などたてまつり添へて、子ながら恥づかしげにおはする御人ざまなれば、まほならずぞ見えたてまつりたまふ。
大臣御けしき悪しくて、
「ここにさぶらふもはしたなく、人びといかに見はべらむと、心置かれにたり。はかばかしき身にはべらねど、世にはべらむ限り、御目離れず御覧ぜられ、おぼつかなき隔てなくとこそ思ひたまふれ。
よからぬもののうへにて、恨めしと思ひきこえさせつべきことの出でまうで来たるを、かうも思うたまへじとかつは思ひたまふれど、なほ静めがたくおぼえはべりてなむ」
と、涙おし拭ひたまふに、宮、化粧じたまへる御顔の色違ひて、御目も大きになりぬ。
「いかやうなることにてか、今さらの齢の末に、心置きては思さるらむ」
「いかやうなることにてか、今さらの齢の末に、心置きては思さるらむ」
と聞こえたまふも、さすがにいとほしけれど、
「頼もしき御蔭に、幼き者をたてまつりおきて、みづからをばなかなか幼くより見たまへもつかず、まづ目に近きが、交じらひなどはかばかしからぬを、見たまへ嘆きいとなみつつ、さりとも人となさせたまひてむと頼みわたりはべりつるに、思はずなることのはべりければ、いと口惜しうなむ。
まことに天の下並ぶ人なき有職にはものせらるめれど、親しきほどにかかるは、人の聞き思ふところも、あはつけきやうになむ、何ばかりのほどにもあらぬ仲らひにだにしはべるを、かの人の御ためにも、いとかたはなることなり。さし離れ、きらきらしうめづらしげあるあたりに、今めかしうもてなさるるこそ、をかしけれ。ゆかりむつび、ねぢけがましきさまにて、大臣も聞き思すところはべりなむ。
さるにても、かかることなむと、知らせたまひて、ことさらにもてなし、
さるにても、かかることなむと、知らせたまひて、ことさらにもてなし、すこしゆかしげあることをまぜてこそはべらめ。幼き人びとの心にまかせて御覧じ放ちけるを、心憂く思うたまふ」
など聞こえたまふに、夢にも知りたまはぬことなれば、あさましう思して、
「げに、かうのたまふもことわりなれど、かけてもこの人びとの下の心なむ知りはべらざりける。げに、いと口惜しきことは、ここにこそまして嘆くべくはべれ。もろともに罪をおほせたまふは、恨めしきことになむ。
見たてまつりしより、心ことに思ひはべりて、そこに思しいたらぬことをも、すぐれたるさまにもてなさむとこそ、人知れず思ひはべれ。ものげなきほどを、心の闇に惑ひて、いそぎものせむとは思ひ寄らぬことになむ。
さても、誰かはかかることは聞こえけむ。よからぬ世の人の言につきて、きはだけく思しのたまふも、あぢきなく、むなしきことにて、人の御名や汚れむ」
とのたまへば、
「何の、浮きたることにかはべらむ。さぶらふめる人びとも、かつは皆もどき笑ふべかめるものを、いと口惜しく、やすからず思うたまへらるるや」
とて、立ちたまひぬ。
心知れるどちは、いみじういとほしく思ふ。一夜のしりう言の人びとは、まして心地も違ひて、「何にかかる睦物語をしけむ」と、思ひ嘆きあへり。
姫君は、何心もなくておはするに、さしのぞきたまへれば、
姫君は、何心もなくておはするに、さしのぞきたまへれば、いとらうたげなる御さまを、あはれに見たてまつりたまふ。
「若き人といひながら、心幼くものしたまひけるを知らで、いとかく人なみなみにと思ひける我こそ、まさりてはかなかりけれ」
とて、御乳母どもをさいなみのたまふに、聞こえむ方なし。
「かやうのことは、限りなき帝の御いつき女も、おのづから過つ例、昔物語にもあめれど、けしきを知り伝ふる人、さるべき隙にてこそあらめ」
「これは、明け暮れ立ちまじりたまひて年ごろおはしましつるを、何かは、いはけなき御ほどを、宮の御もてなしよりさし過ぐしても、隔てきこえさせむと、うちとけて過ぐしきこえつるを、一昨年ばかりよりは、けざやかなる御もてなしになりにてはべるめるに、若き人とても、うち紛ればみ、いかにぞや、世づきたる人もおはすべかめるを、夢に乱れたるところおはしまさざめれば、さらに思ひ寄らざりけること」
と、おのがどち嘆く。
「よし、しばし、かかること漏らさじ。
「よし、しばし、かかること漏らさじ。隠れあるまじきことなれど、心をやりて、あらぬこととだに言ひなされよ。今かしこに渡したてまつりてむ。宮の御心のいとつらきなり。そこたちは、さりとも、いとかかれとしも、思はれざりけむ」
とのたまへば、「いとほしきなかにも、うれしくのたまふ」と思ひて、
「あな、いみじや。大納言殿に聞きたまはむことをさへ思ひはべれば、めでたきにても、ただ人の筋は、何のめづらしさにか思ひたまへかけむ」
と聞こゆ。
姫君は、いと幼げなる御さまにて、よろづに申したまへども、かひあるべきにもあらねば、うち泣きたまひて、
「いかにしてか、いたづらになりたまふまじきわざはすべからむ」
と、忍びてさるべきどちのたまひて、大宮をのみぞ恨みきこえたまふ。
宮は、いといとほしと思すなかにも、男君の御かなしさはすぐれたまふにやあらむ、
宮は、いといとほしと思すなかにも、男君の御かなしさはすぐれたまふにやあらむ、かかる心のありけるも、うつくしう思さるるに、情けなく、こよなきことのやうに思しのたまへるを、
「などかさしもあるべき。もとよりいたう思ひつきたまふことなくて、かくまでかしづかむとも思し立たざりしを、わがかくもてなしそめたればこそ、春宮の御ことをも思しかけためれ。とりはづして、ただ人の宿世あらば、この君よりほかにまさるべき人やはある。容貌、ありさまよりはじめて、等しき人のあるべきかは。これより及びなからむ際にもとこそ思へ」
と、わが心ざしのまさればにや、大臣を恨めしう思ひきこえたまふ。御心のうちを見せたてまつりたらば、ましていかに恨みきこえたまはむ。
かく騒がるらむとも知らで、冠者の君参りたまへり。
かく騒がるらむとも知らで、冠者の君参りたまへり。一夜も人目しげうて、思ふことをもえ聞こえずなりにしかば、常よりもあはれにおぼえたまひければ、夕つ方おはしたるなるべし。
宮、例は是非知らず、うち笑みて待ちよろこびきこえたまふを、まめだちて物語など聞こえたまふついでに、
「御ことにより、内大臣の怨じてものしたまひにしかば、いとなむいとほしき。ゆかしげなきことをしも思ひそめたまひて、人にもの思はせたまひつべきが心苦しきこと。かうも聞こえじと思へど、さる心も知りたまはでやと思へばなむ」
と聞こえたまへば、心にかかれることの筋なれば、ふと思ひ寄りぬ。面赤みて、
「何ごとにかはべらむ。静かなる所に籠もりはべりにしのち、ともかくも人に交じる折なければ、恨みたまふべきことはべらじとなむ思ひたまふる」
とて、いと恥づかしと思へるけしきを、あはれに心苦しうて、
「よし。今よりだに用意したまへ」
とばかりにて、異事に言ひなしたまうつ。
「いとど文なども通はむことのかたきなめり」と思ふに、
「いとど文なども通はむことのかたきなめり」と思ふに、いと嘆かしう、物参りなどしたまへど、さらに参らで、寝たまひぬるやうなれど、心も空にて、人静まるほどに、中障子を引けど、例はことに鎖し固めなどもせぬを、つと鎖して、人の音もせず。いと心細くおぼえて、障子に寄りかかりてゐたまへるに、女君も目を覚まして、風の音の竹に待ちとられて、うちそよめくに、雁の鳴きわたる声の、ほのかに聞こゆるに、幼き心地にも、とかく思し乱るるにや、
「雲居の雁もわがごとや」
と、独りごちたまふけはひ、若うらうたげなり。
いみじう心もとなければ、
「これ、開けさせたまへ。小侍従やさぶらふ」
とのたまへど、音もせず。御乳母子なりけり。
独り言を聞きたまひけるも恥づかしうて、
独り言を聞きたまひけるも恥づかしうて、あいなく御顔も引き入れたまへど、あはれは知らぬにしもあらぬぞ憎きや。乳母たちなど近く臥して、うちみじろくも苦しければ、かたみに音もせず。
「さ夜中に友呼びわたる雁が音に
うたて吹き添ふ荻の上風」
「身にもしみけるかな」と思ひ続けて、宮の御前に帰りて嘆きがちなるも、「御目覚めてや聞かせたまふらむ」とつつましく、みじろき臥したまへり。
あいなくもの恥づかしうて、わが御方にとく出でて、御文書きたまへれど、
あいなくもの恥づかしうて、わが御方にとく出でて、御文書きたまへれど、小侍従もえ逢ひたまはず、かの御方ざまにもえ行かず、胸つぶれておぼえたまふ。
女はた、騒がれたまひしことのみ恥づかしうて、「わが身やいかがあらむ、人やいかが思はむ」とも深く思し入れず、をかしうらうげにて、うち語らふさまなどを、疎ましとも思ひ離れたまはざりけり。
また、かう騒がるべきこととも思さざりけるを、御後見どももいみじうあはめきこゆれば、え言も通はしたまはず。おとなびたる人や、さるべき隙をも作り出づらむ、男君も、今すこしものはかなき年のほどにて、ただいと口惜しとのみ思ふ。
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第95回 「乙女」より その3 |
|---|---|
| 収録日 | 2007年6月16日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
平成19年春期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。