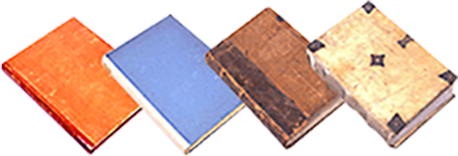第111回 「常夏」より その2
大臣(源氏)は姫君(玉葛)に内大臣家との関係を漏らす。源氏は和琴を弾き、和琴を礼賛する。源氏と玉葛は、世間に例のない難しい間柄である。内大臣は太政大臣(源氏)について、軽蔑の心で語る。内大臣は姫君(雲居雁)が昼寝しているのをいさめる。

講師:岡野弘彦
たそかれ時のおぼおぼしきに、同じ直衣どもなれば、
たそかれ時のおぼおぼしきに、同じ直衣どもなれば、何ともわきまへられぬに、大臣、姫君を、
「すこし外出でたまへ」
とて、忍びて、
「少将、侍従など率てまうで来たり。いと翔けり来まほしげに思へるを、中将の、いと実法の人にて率て来ぬ、無心なめりかし。
この人びとは、皆思ふ心なきならじ。なほなほしき際をだに、窓の内なるほどは、ほどに従ひて、ゆかしく思ふべかめるわざなれば、この家のおぼえ、うちうちのくだくだしきほどよりは、いと世に過ぎて、ことことしくなむ言ひ思ひなすべかめる。かたがたものすめれど、さすがに人の好きごと言ひ寄らむにつきなしかし。
かくてものしたまふは、いかでさやうならむ人のけしきの、深さ浅さをも見むなど、さうざうしきままに願ひ思ひしを、本意なむ叶ふ心地しける」
など、ささめきつつ聞こえたまふ。
御前に、乱れがはしき前栽なども植ゑさせたまはず、
御前に、乱れがはしき前栽なども植ゑさせたまはず、撫子の色をととのへたる、唐の、大和の、籬いとなつかしく結ひなして、咲き乱れたる夕ばえ、いみじく見ゆ。皆、立ち寄りて、心のままにも折り取らぬを、飽かず思ひつつやすらふ。
「有職どもなりな。心もちゐなども、とりどりにつけてこそめやすけれ。右の中将は、ましてすこし静まりて、心恥づかしき気まさりたり。いかにぞや、おとづれ聞こゆや。はしたなくも、なさし放ちたまひそ」
などのたまふ。
中将の君は、かくよきなかに、すぐれてをかしげになまめきたまへり。
「中将を厭ひたまふこそ、大臣は本意なけれ。交じりものなく、きらきらしかめるなかに、大君だつ筋にて、かたくななりとにや」
とのたまへば、
「来まさば、といふ人もはべりけるを」
と聞こえたまふ。
「いで、その御肴もてはやされむさまは願はしからず。ただ、幼きどちの結びおきけむ心も解けず、年月、隔てたまふ心むけのつらきなり。まだ下臈なり、世の聞き耳軽しと思はれば、知らず顔にて、ここに任せたまへらむに、うしろめたくはありなましや」
など、うめきたまふ。「さは、かかる御心の隔てある御仲なりけり」と聞きたまふにも、親に知られたてまつらむことのいつとなきは、あはれにいぶせく思す。
月もなきころなれば、燈籠に御殿油参れり。
月もなきころなれば、燈籠に御殿油参れり。
「なほ、気近くて暑かはしや。篝火こそよけれ」
とて、人召して、
「篝火の台一つ、こなたに」
と召す。をかしげなる和琴のある、引き寄せたまひて、掻き鳴らしたまへば、律にいとよく調べられたり。音もいとよく鳴れば、すこし弾きたまひて、
「かやうのことは御心に入らぬ筋にやと、月ごろ思ひおとしきこえけるかな。秋の夜の月影涼しきほど、いと奥深くはあらで、虫の声に掻き鳴らし合はせたるほど、気近く今めかしきものの音なり。ことことしき調べ、もてなししどけなしや。
このものよ、さながら多くの遊び物の音、拍子を調へとりたるなむいとかしこき。大和琴とはかなく見せて、際もなくしおきたることなり。広く異国のことを知らぬ女のためとなむおぼゆる。
同じくは、心とどめて物などに掻き合はせて習ひたまへ。深き心とて、何ばかりもあらずながら、またまことに弾き得ることはかたきにやあらむ、ただ今は、この内大臣になずらふ人なしかし。
ただはかなき同じ菅掻きの音に、よろづのものの音、籠もり通ひて、いふかたもなくこそ、響きのぼれ」
と語りたまへば、ほのぼの心得て、いかでと思すことなれば、いとどいぶかしくて、
「このわたりにて、さりぬべき御遊びの折など、聞きはべりなむや。あやしき山賤などのなかにも、まねぶものあまたはべるなることなれば、おしなべて心やすくやとこそ思ひたまへつれ。さは、すぐれたるは、さまことにやはべらむ」
と、ゆかしげに、切に心に入れて思ひたまへれば、
「さかし。あづまとぞ名も立ち下りたるやうなれど、御前の御遊びにも、まづ書司を召すは、人の国は知らず、ここにはこれをものの親としたるにこそあめれ。
そのなかにも、親としつべき御手より弾き取りたまへらむは、心ことなりなむかし。ここになども、さるべからむ折にはものしたまひなむを、この琴に、手惜しまずなど、あきらかに掻き鳴らしたまはむことやかたからむ。ものの上手は、いづれの道も心やすからずのみぞあめる。
さりとも、つひには聞きたまひてむかし」
とて、調べすこし弾きたまふ。ことつひいと二なく、今めかしくをかし。「これにもまされる音や出づらむ」と、親の御ゆかしさたち添ひて、このことにてさへ、「いかならむ世に、さてうちとけ弾きたまはむを聞かむ」など、思ひゐたまへり。
「貫河の瀬々のやはらた」と、いとなつかしく謡ひたまふ。
「貫河の瀬々のやはらた」と、いとなつかしく謡ひたまふ。「親避くるつま」は、すこしうち笑ひつつ、わざともなく掻きなしたまひたる菅掻きのほど、いひ知らずおもしろく聞こゆ。
「いで、弾きたまへ。才は人になむ恥ぢぬ。「想夫恋」ばかりこそ、心のうちに思ひて、紛らはす人もありけめ、おもなくて、かれこれに合はせつるなむよき」
と、切に聞こえたまへど、さる田舎の隈にて、ほのかに京人と名のりける、古王君女教へきこえければ、ひがことにもやとつつましくて、手触れたまはず。
「しばしも弾きたまはなむ。聞き取ることもや」と心もとなきに、この御琴によりぞ、近くゐざり寄りて、
「いかなる風の吹き添ひて、かくは響きはべるぞとよ」
とて、うち傾きたまへるさま、火影にいとうつくしげなり。笑ひたまひて、
「耳固からぬ人のためには、身にしむ風も吹き添ふかし」
とて、押しやりたまふ。いと心やまし。
人びと近くさぶらへば、例の戯れごともえ聞こえたまはで、
人びと近くさぶらへば、例の戯れごともえ聞こえたまはで、
「撫子を飽かでも、この人びとの立ち去りぬるかな。いかで、大臣にも、この花園見せたてまつらむ。世もいと常なきをと思ふに、いにしへも、もののついでに語り出でたまへりしも、ただ今のこととぞおぼゆる」
とて、すこしのたまひ出でたるにも、いとあはれなり。
「撫子のとこなつかしき色を見ば
もとの垣根を人や尋ねむ
このことのわづらはしさにこそ、繭ごもりも心苦しう思ひきこゆれ」
とのたまふ。君、うち泣きて、
「山賤の垣ほに生ひし撫子の
もとの根ざしを誰れか尋ねむ」
はかなげに聞こえないたまへるさま、げにいとなつかしく若やかなり。
「来ざらましかば」
とうち誦じたまひて、いとどしき御心は、苦しきまで、なほえ忍び果つまじく思さる。
渡りたまふことも、あまりうちしきり、人の見たてまつり咎むべきほどは、
渡りたまふことも、あまりうちしきり、人の見たてまつり咎むべきほどは、心の鬼に思しとどめて、さるべきことをし出でて、御文の通はぬ折なし。ただこの御ことのみ、明け暮れ御心にはかかりたり。
「なぞ、かくあいなきわざをして、やすからぬもの思ひをすらむ。さ思はじとて、心のままにもあらば、世の人のそしり言はむことの軽々しさ、わがためをばさるものにて、この人の御ためいとほしかるべし。限りなき心ざしといふとも、春の上の御おぼえに並ぶばかりは、わが心ながらえあるまじく」思し知りたり。「さて、その劣りの列にては、何ばかりかはあらむ。わが身ひとつこそ、人よりは異なれ、見む人のあまたが中に、かかづらはむ末にては、何のおぼえかはたけからむ。異なることなき納言の際の、二心なくて思はむには、劣りぬべきことぞ」
と、みづから思し知るに、いといとほしくて、「宮、大将などにや許してまし。さてもて離れ、いざなひ取りては、思ひも絶えなむや。いひかひなきにて、さもしてむ」と思す折もあり。
されど、渡りたまひて、御容貌を見たまひ、今は御琴教へたてまつりたまふにさへことづけて、近やかに馴れ寄りたまふ。
姫君も、初めこそむくつけく、うたてとも思ひたまひしか、「かくても、なだらかに、うしろめたき御心はあらざりけり」と、やうやう目馴れて、いとしも疎みきこえたまはず、さるべき御いらへも、馴れ馴れしからぬほどに聞こえかはしなどして、見るままにいと愛敬づき、薫りまさりたまへれば、なほさてもえ過ぐしやるまじく思し返す。
「さはまた、さて、ここながらかしづき据ゑて、さるべき折々に、はかなくうち忍び、ものをも聞こえて慰みなむや。かくまだ世馴れぬほどの、わづらはしさにこそ、心苦しくはありけれ、おのづから関守強くとも、ものの心知りそめ、いとほしき思ひなくて、わが心も思ひ入りなば、しげくとも障はらじかし」と思し寄る、いとけしからぬことなりや。
いよいよ心やすからず、思ひわたらむ苦しからむ。なのめに思ひ過ぐさむことの、とざまかくざまにもかたきぞ、世づかずむつかしき御語らひなりける。
内の大殿は、この今の御女のことを、「殿の人も許さず、軽み言ひ、
内の大殿は、この今の御女のことを、「殿の人も許さず、軽み言ひ、世にもほきたることと誹りきこゆ」と、聞きたまふに、少将の、ことのついでに、太政大臣の「さることや」ととぶらひたまひしこと、語りきこゆれば、
「さかし。そこにこそは、年ごろ、音にも聞こえぬ山賤の子迎へ取りて、ものめかしたつれ。をさをさ人の上もどきたまはぬ大臣の、このわたりのことは、耳とどめてぞおとしめたまふや。これぞ、おぼえある心地しける」
とのたまふ。少将の、
「かの西の対に据ゑたまへる人は、いとこともなきけはひ見ゆるわたりになむはべるなる。兵部卿宮など、いたう心とどめてのたまひわづらふとか。おぼろけにはあらじとなむ、人びと推し量りはべめる」
と申したまへば、
「いで、それは、かの大臣の御女と思ふばかりのおぼえのいといみじきぞ。人の心、皆さこそある世なめれ。かならずさしもすぐれじ。人びとしきほどならば、年ごろ聞こえなまし。
あたら、大臣の、塵もつかず、この世には過ぎたまへる御身のおぼえありさまに、おもだたしき腹に、女かしづきて、げに疵なからむと、思ひやりめでたきがものしたまはぬは。
おほかたの子の少なくて、心もとなきなめりかし。劣り腹なれど、明石の御許の産み出でたるはしも、さる世になき宿世にて、あるやうあらむとおぼゆかし。
その今姫君は、ようせずは、実の御子にもあらじかし。さすがにいとけしきあるところつきたまへる人にて、もてないたまふならむ」
と、言ひおとしたまふ。
「さて、いかが定めらるなる。親王こそまつはし得たまはむ。もとより取り分きて御仲よし、人柄も警策なる御あはひどもならむかし」
などのたまひては、なほ、姫君の御こと、飽かず口惜し。「かやうに、心にくくもてなして、いかにしなさむなど、やすからずいぶかしがらせましものを」とねたければ、位さばかりと見ざらむ限りは、許しがたく思すなりけり。
大臣なども、ねむごろに口入れかへさひたまはむにこそは、負くるやうにてもなびかめと思すに、男方は、さらに焦られきこえたまはず、心やましくなむ。
とかく思しめぐらすままに、ゆくりもなく軽らかにはひ渡りたまへり。
とかく思しめぐらすままに、ゆくりもなく軽らかにはひ渡りたまへり。少将も御供に参りたまふ。
姫君は、昼寝したまへるほどなり。羅の単衣を着たまひて臥したまへるさま、暑かはしくは見えず、いとらうたげにささやかなり。透きたまへる肌つきなど、いとうつくしげなる手つきして、扇を持たまへりけるながら、かひなを枕にて、うちやられたる御髪のほど、いと長くこちたくはあらねど、いとをかしき末つきなり。
人びとものの後に寄り臥しつつうち休みたれば、ふともおどろいたまはず。扇を鳴らしたまへるに、何心もなく見上げたまへるまみ、らうたげにて、つらつき赤めるも、親の御目にはうつくしくのみ見ゆ。
「うたた寝はいさめきこゆるものを。などか、いとものはかなきさまにては大殿籠もりける。人びとも近くさぶらはで、あやしや。
女は、身を常に心づかひして守りたらむなむよかるべき。心やすくうち捨てざまにもてなしたる、品なきことなり。
さりとて、いとさかしく身かためて、不動の陀羅尼誦みて、印つくりてゐたらむも憎し。うつつの人にもあまり気遠く、もの隔てがましきなど、気高きやうとても、人にくく、心うつくしくはあらぬわざなり。
太政大臣の、后がねの姫君ならはしたまふなる教へは、よろづのことに通はしなだらめて、かどかどしきゆゑもつけじ、たどたどしくおぼめくこともあらじと、ぬるらかにこそ掟てたまふなれ。
げに、さもあることなれど、人として、心にもするわざにも、立ててなびく方は方とあるものなれば、生ひ出でたまふさまあらむかし。この君の人となり、宮仕へに出だし立てたまはむ世のけしきこそ、いとゆかしけれ」
などのたまひて、
「思ふやうに見たてまつらむと思ひし筋は、難うなりにたる御身なれど、いかで人笑はれならずしなしたてまつらむとなむ、人の上のさまざまなるを聞くごとに、思ひ乱れはべる。
心みごとにねむごろがらむ人のねぎごとに、なしばしなびきたまひそ。思ふさまはべり」
など、いとらうたしと思ひつつ聞こえたまふ。
「昔は、何ごとも深くも思ひ知らで、なかなか、さしあたりていとほしかりしことの騒ぎにも、おもなくて見えたてまつりけるよ」と、今ぞ思ひ出づるに、胸ふたがりて、いみじく恥づかしき。
大宮よりも、常におぼつかなきことを恨みきこえたまへど、かくのたまふるがつつましくて、え渡り見たてまつりたまはず。
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第111回 「常夏」より その2 |
|---|---|
| 収録日 | 2008年6月28日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
平成20年春期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。