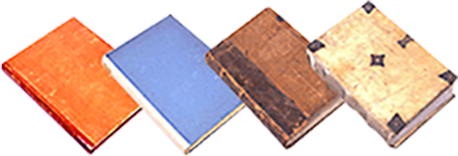乙女 (をとめ)
少女子も神さびぬらし天つ袖古き世の友よはひ経ぬれば 光源氏
かけて言へば今日のこととぞ思ほゆる日蔭の霜の袖にとけしも 五節
日影にもしるかりけめや少女子が天の羽袖にかけし心は 夕霧
- ・歌の背景
- 光源氏三十三歳。五節の日、参上した源氏は舞姫を見て、若い時に目にとめた舞姫の乙女の姿をお思い出し、文をお遣わしになる。
一方、夕霧は惟光の娘の五節に歌を贈る。
- ・講義より
-
少女子も神さびぬらし天つ袖古き世の友よはひ経ぬれば
五節の舞姫というのは、天武天皇が吉野で体験した天つ乙女の舞というものが起源になっているという伝えがあるわけですが、「少女子も神さびぬらし」、その天つ乙女の舞を舞った乙女も今は神さびただろうな。「神さぶ」というのは、神らしくなった、年取っただろうなということです。「天つ袖古き世の友」、天つ袖を振って舞った、そして自分と縁を触れ合った古き世の友。石上(いそのかみ)布留(ふる)を縁語としてこんなところで働かせているわけです。古き世の友である自分も、「よはひ経ぬれば」――あれからこうして年を重ねてしまった。そのことを考えると「少女子も神さびぬらし」ということですね。
かけて言へば今日のこととぞ思ほゆる日蔭の霜の袖にとけしも
「かけて言へば」というのは、心にかけてということですが、同時に、舞姫が日蔭の葛(かずら)をたすきのようにかけて舞う。それもまさしく掛け詞で言っているわけです。あの五節の舞姫にちなんだ言葉にかけて申し上げますならば、神に申し上げるときの「かけまくも賢き」という決まり文句は、心にかけて申し上げるのも、さらに言葉にかけて申し上げるのもという意味ですけれども、そういう決まり文句を幾様にも働かせて、五節のことにかけて、あなた様からこんなふうに歌をいただきまして、お心をおっしゃってくださいますと、まるであの過ぎ去ったことが今日のことのように思われてまいります。「日蔭の霜の袖にとけしも」、あの身にかけました日蔭の葛、身に日蔭の葛をかけて舞いましたことが、袖に溶ける霜のように心溶けて思われることでございます。
日影にもしるかりけめや少女子が天の羽袖にかけし心は
前の「かけて言へば今日のこととぞ思ほゆる日蔭の霜の袖にとけしも」(五節)。舞姫の身につけている日蔭の葛と、それと、こっちの日影は日の光という意味に使っているわけですけれども、舞姫にゆかりの日蔭の葛、ゆかりのある言葉を使ってきて、「日影にもしるかりけめや」、日の光にもはっきりとあらわれていたことでしょうよ。くっきりとあらわれていたことでしょうよ。その日蔭の葛をかけて舞う少女子が、「天の羽袖」、天の羽衣の舞を舞う袖に私がかけた思いのほどは。だれの目にも見えたはずですよ、少女子が舞う天の羽袖に私がかけた思いのほどは。
- 講義ページ
-
第97回 「乙女」より その5
- 6.浅葱の心やましければ、内裏へ参ることもせず、
 15:22~24:01
15:22~24:01 - 8.せうとの童殿上する、常にこの君に参り仕うまつるを、
 10:42~13:23
10:42~13:23
- 6.浅葱の心やましければ、内裏へ参ることもせず、
玉鬘 (たまかづら)
恋ひわたる身はそれなれど玉かづらいかなる筋を尋ね来つらむ 光源氏
- ・歌の背景
- 光源氏三十五歳。夕顔の遺児玉鬘は乳母と筑紫へ下っていたが、後に玉鬘と乳母達は上洛し、初瀬に参詣していたところ、右近に再会。それがきっかけで源氏に引き取られる。
- ・講義より
-
恋ひわたる身はそれなれど玉かづらいかなる筋を尋ね来つらむ あはれ
あの亡き夕顔を焦がれ続けるその我が身はそのままだけれども、今、玉かづらは一体どんな筋を、つまり「玉かづら」というのは蔓草ですが、「玉かづら」と「筋」、縁語で言っているわけですね。玉かづら、それじゃないけれども、一体どういう筋を尋ねて我がもとに来たのだろう。自分が恋しいと思う亡き夕顔の魂は、亡き身そのままだけれども、この玉かづらの魂は一体いかなる筋を尋ねてやってきたのだろう。
- 講義ページ
-
第102回 「玉葛」より その4
- 16.めやすくものしたまふを、うれしく思して、上にも語りきこえたまふ。
 13:39~18:23
13:39~18:23
- 16.めやすくものしたまふを、うれしく思して、上にも語りきこえたまふ。
初音 (はつね)
年月を松にひかれて経る人に今日鴬の初音聞かせよ 明石の御方
ひき別れ年は経れども鶯の巣立ちし松の根を忘れめや 明石の姫君
- ・歌の背景
- 光源氏三十六歳。明石の御方は、なかなか対面もできないわが子である姫君へ歌を贈る。
- ・講義より
-
年月を松にひかれて経る人に今日鴬の初音聞かせよ 音せぬ里の
年月を待つ、その松に引かれて年を過ごす人も、今日という日は鶯の初音を聞かせてくださいな。本歌があって、「松の上に鳴く鶯の声をこそ初音の日とはいふべかりけれ」。『拾遺集』の宮内卿の歌です。正月に年の改まるときでも親子の体面もできない母親の思いが、「年月を松にひかれて経る人」、娘にも会えないで年月を過ごしている自分という風な思いがあるわけでしょうね。今日ばかりは鶯もその初音を聞かせてほしい。「音せぬ里の」これが効いているわけですね。これも引歌があって、「今日だにも初音聞かせよ鶯の音せぬ里はあるかひもなし」。これは源氏釈の中に、ここのところの引歌として引かれているわけで、ほかの歌集のどこに出ているかということはわからないのですけれども、なるほど、そう言われれば、歌に添えた「音せぬ里の」という思いのこもった言葉がこの歌を本歌としているとすれば、よく働いていますね。「今日だにも初音聞かせよ」、せめてこの年の初めの今日だけでも、その初音を聞かせておくれよ。鶯の初音を聞かない里は、春が来たと言っても、春だと思うかいもないことだ。春になったという気もしないことだ、という風な、そういう思いを「音せぬ里の」という言葉に込めて言っているわけでしょう。
ひき別れ年は経れども鶯の巣立ちし松の根を忘れめや
間を引き別れて年の数は過ぎたけれども、幾年が過ぎたけれども、鶯が巣立ちをした松のもとを忘れることがありましょうか。反語にとっておいた方がはっきりしますね。忘れはいたしません。
- 講義ページ
-
第103回 「玉葛」 その5~「初音」 その1
- 11.姫君の御方に渡りたまへれば、童女、下仕へなど、
 9:22~12:15
9:22~12:15 - 11.姫君の御方に渡りたまへれば、童女、下仕へなど、
 16:37~17:50
16:37~17:50
- 11.姫君の御方に渡りたまへれば、童女、下仕へなど、
胡蝶 (こてふ)
花園の胡蝶をさへや下草に秋待つ虫はうとく見るらむ 紫の上
胡蝶にも誘はれなまし心ありて八重山吹を隔てざりせば 秋好中宮
- ・歌の背景
- 光源氏三十六歳。光源氏の一番大事にしている紫の上と、光源氏の力添えによって、帝の信頼厚い女性となった秋好中宮が住まう六条院で、それぞれの好みを背景に春と秋の優劣を競い合う。
- ・講義より
-
花園の胡蝶をさへや下草に秋待つ虫はうとく見るらむ
春の花園の胡蝶をすら、下草の陰で秋を待っている虫どもは、気疎いもの、憂鬱なもの、ちょっと気に添わないものとして見ることでしょうよ。一本取ったつもりなんですね。
昨日は音に泣きぬべくこそは 胡蝶にも誘はれなまし心ありて八重山吹を隔てざりせば
身を蝶々にもなして、身を胡蝶になして、胡蝶と「来てふ」を掛けて言っているわけですが、本当に身を胡蝶にもなして、誘われていけばよろしゅうございました。「誘われなまし」で反実仮想ですから、誘われていけばよろしゅうございました。「八重山吹を隔てざりせば」、あの八重山吹の隔てをおつくりになりませんでしたら。山吹の垣根がございませんでしたら。時と場に応じて、引歌を引いた挨拶の返しの歌ですね。
- 講義ページ
-
第105回 「胡蝶」より その1
- 12.春の上の御心ざしに、仏に花たてまつらせたまふ。
 12:36~14:40
12:36~14:40 - 13.宮の亮をはじめて、さるべき上人ども、禄取り続きて、童べに賜ぶ。
 7:36~10:49
7:36~10:49
- 12.春の上の御心ざしに、仏に花たてまつらせたまふ。
蛍 (ほたる)
鳴く声も聞こえぬ虫の思ひだに人の消つには消ゆるものかは 兵部卿宮
声はせで身をのみ焦がす蛍こそ言ふよりまさる思ひなるらめ 玉鬘
- ・歌の背景
- 光源氏三十六歳。光源氏の態度に思い乱れている玉鬘には、前から文を通わせてきている方が何人かいる。その一人の兵部卿宮が尋ねてきた時に、源氏は部屋に蛍を放ち、そのわずかな光のもと、玉鬘の気配を感じる兵部卿宮は思いを詠む。
- ・講義より
-
鳴く声も聞こえぬ虫の思ひだに人の消つには消ゆるものかは 思ひ知りたまひぬや
鳴く声も聞こえぬ虫、その虫の灯す火、そのわずかなはかない思いすら、人が消すのに任せてはかなく消えるものだろうか、そんなはずはない。そういう思いをこの歌に託して、「思ひ知りたまひぬや」、あなたのことをこんなに思っております私の心をお察しなすってくださいますか、と申し上げなされた。
声はせで身をのみ焦がす蛍こそ言ふよりまさる思ひなるらめ
声を立てることもない、そのかわり身ばかりを炎として燃え立たせて焦がす虫こそ、言葉で言うよりはまさっている思いのほどでございましょうよ。
- 講義ページ
-
第108回 「蛍」より その1
- 10.宮は、人のおはするほど、さばかりと推し量りたまふが、
 9:13~14:23
9:13~14:23
- 10.宮は、人のおはするほど、さばかりと推し量りたまふが、
常夏 (とこなつ)
撫子のとこなつかしき色を見ばもとの垣根を人や尋ねむ 光源氏
山賤の垣ほに生ひし撫子のもとの根ざしを誰れか尋ねむ 玉鬘
- ・歌の背景
- 光源氏三十六歳。夕顔の面影がある玉鬘への思いがつのる源氏は、玉鬘の父である内大臣に、夕顔の遺児である玉鬘を対面させることを検討する。
- ・講義より
-
撫子のとこなつかしき色を見ばもとの垣根を人や尋ねむ
「とこなつかしき色を見ば」、永遠にいつまでも懐かしい、忘れることのできない色を見るというと、「もとの垣根を人や尋ねむ」。「撫子」は娘の方の玉鬘、「とこなつ」は永遠に懐かしいということと常夏の掛け詞になっているわけです。だから「もとの垣根」は夕顔への連想ですね。この撫子の、時が長くたってもいつまでも懐かしい花の色を見るというと、遠い以前のもとのゆかりを秘めている、あの垣根が懐かしいことよ。「もとの垣根」は夕顔の連想をかき立てるわけですね。
山賤の垣ほに生ひし撫子のもとの根ざしを誰れか尋ねむ
あの山賤の垣根に咲いた撫子の花のような、この私の本来の根ざしを、一体だれが尋ねてくれることでしょうか。自分を生んだ母親はとっくに亡くなっている。そして父親は今を時めく大臣であるわけですけれども、そのことにまだ全く気がついていない。山賤の垣ほに生ひし撫子である自分の、この心もとない境遇は、だれが尋ね出してくれるのでしょうかというふうな歌ですね。
- 講義ページ
-
第111回 「常夏」より その2
- 5.人びと近くさぶらへば、例の戯れごともえ聞こえたまはで、
 5:34~13:20
5:34~13:20
- 5.人びと近くさぶらへば、例の戯れごともえ聞こえたまはで、
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。