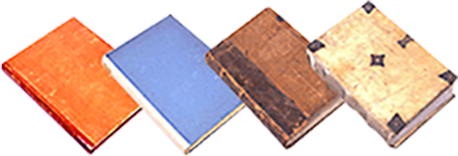第52回 「紅葉賀」その4~「花宴」その1
藤壺の宮は立后し源氏の君は宰相になる。花宴に巻は変わり、南殿の桜の宴で春鶯囀を舞う。弘徽殿の細殿で出会った女性に名を尋ねると「草の原をば訪はじとや思ふ」と詠む。

講師:岡野弘彦
- 目次
-
- はじめに ―圭室氏、海老沢氏との座談会―
- さて、そののち、ともすればことのついでごとに、
- 七月にぞ后ゐたまふめりし。源氏の君、宰相になりたまひぬ。
- 参りたまふ夜の御供に、宰相君も仕うまつりたまふ。
- 皇子は、およすけたまふ月日に従ひて、いと見たてまつり分きがたげなるを、
- 如月の二十日あまり、南殿の桜の宴せさせたまふ。
- さての人びとは、皆臆しがちに鼻白める多かり。
- 楽どもなどは、さらにもいはずととのへさせたまへり。
- 夜いたう更けてなむ、事果てける。
- あさましきにあきれたるさま、いとなつかしうをかしげなり。
- (補足) ―草の原―
- 桐壷には、人びと多くさぶらひて、おどろきたるもあれば、
- その日は後宴のことありて、まぎれ暮らしたまひつ。
- 「姫君、いかにつれづれならむ。日ごろになれば、
はじめに ―圭室氏、海老沢氏との座談会―
「江戸時代というものはなかなか穏やかに過ぎた時代のようですけれども、実際に生きていた人たちにとっては、人によって信教の自由、自分の墓のあり方そのものにすら志を得ない重い時代でもあった。いつの時代でもそうですけれども、そういうことが、(本居宣長の)あの遺言書がああいう形で書かれなければならない理由なんだなということがわかりました。わかってみて、どうということもないんですけれども、『古事記』を通して日本人の長い長い心の流れというものをあんなに緻密にはっきりととらえていた宣長さんが、その命の最後の、我が死後の魂の鎮めようを考えるためにも、貫こうとするためにも、あれだけの苦心をしたんだなということが身にしみてわかった気がしました。」
・圭室(やまむろ)文雄さん、海老沢泰久さんとの座談会の後で考えたこと
・長谷川伸 『相楽総三とその同志たち』
・本居宣長の遺言書について
さて、そののち、ともすればことのついでごとに、
さて、そののち、ともすればことのついでごとに、言ひ迎ふるくさはひなるを、いとどものむつかしき人ゆゑと、思し知るべし。女は、なほいと艶に怨みかくるを、わびしと思ひありきたまふ。
中将は、妹の君にも聞こえ出でず、ただ、「さるべき折の脅しぐさにせむ」とぞ思ひける。やむごとなき御腹々の親王たちだに、主上の御もてなしのこよなきにわづらはしがりて、いとことにさりきこえたまへるを、この中将は、「さらにおし消たれきこえじ」と、はかなきことにつけても、思ひいどみきこえたまふ。
この君一人ぞ、姫君の御一つ腹なりける。帝の御子といふばかりにこそあれ、我も、同じ大臣と聞こゆれど、御おぼえことなるが、皇女腹にてまたなくかしづかれたるは、何ばかり劣るべき際と、おぼえたまはぬなるべし。人がらも、あるべき限りととのひて、何ごともあらまほしく、たらひてぞものしたまひける。この御中どもの挑みこそ、あやしかりしか。されど、うるさくてなむ 。
七月にぞ后ゐたまふめりし。源氏の君、宰相になりたまひぬ。
七月にぞ后ゐたまふめりし。源氏の君、宰相になりたまひぬ。帝、下りゐさせたまはむの御心づかひ近うなりて、この若宮を坊に、と思ひきこえさせたまふに、御後見したまふべき人おはせず。御母方の、みな親王たちにて、源氏の公事しりたまふ筋ならねば、母宮をだに動きなきさまにしおきたてまつりて、強りにと思すになむありける。
弘徽殿、いとど御心動きたまふ、ことわりなり。されど、
「春宮の御世、いと近うなりぬれば、疑ひなき御位なり。思ほしのどめよ」
とぞ聞こえさせたまひける。「げに、春宮の御母にて二十余年になりたまへる女御をおきたてまつりては、引き越したてまつりたまひがたきことなりかし」と、例の、やすからず世人も聞こえけり 。
参りたまふ夜の御供に、宰相君も仕うまつりたまふ。
参りたまふ夜の御供に、宰相君も仕うまつりたまふ。同じ宮と聞こゆるなかにも、后腹の皇女、玉光りかかやきて、たぐひなき御おぼえにさへものしたまへば、人もいとことに思ひかしづききこえたり。まして、わりなき御心には、御輿のうちも思ひやられて、いとど及びなき心地したまふに、すずろはしきまでなむ。
「尽きもせぬ心の闇に暮るるかな
雲居に人を見るにつけても」
とのみ、独りごたれつつ、ものいとあはれなり。
皇子は、およすけたまふ月日に従ひて、いと見たてまつり分きがたげなるを、
皇子は、およすけたまふ月日に従ひて、いと見たてまつり分きがたげなるを、宮、いと苦し、と思せど、思ひ寄る人なきなめりかし。げに、いかさまに作り変へてかは、劣らぬ御ありさまは、世に出でものしたまはまし。月日の光の空に通ひたるやうに、ぞ世人も思へる。
如月の二十日あまり、南殿の桜の宴せさせたまふ。
花宴
如月の二十日あまり、南殿の桜の宴せさせたまふ。后、春宮の御局、左右にして、参う上りたまふ。弘徽殿の女御、中宮のかくておはするを、をりふしごとにやすからず思せど、物見にはえ過ぐしたまはで、参りたまふ。
日いとよく晴れて、空のけしき、鳥の声も、心地よげなるに、親王たち、上達部よりはじめて、その道のは皆、探韻賜はりて文つくりたまふ。宰相中将、「春といふ文字賜はれり」と、のたまふ声さへ、例の、人に異なり。次に頭中将、人の目移しも、ただならずおぼゆべかめれど、いとめやすくもてしづめて、声づかひなど、ものものしくすぐれたり。
さての人びとは、皆臆しがちに鼻白める多かり。
さての人びとは、皆臆しがちに鼻白める多かり。地下の人は、まして、帝、春宮の御才かしこくすぐれておはします、かかる方にやむごとなき人多くものしたまふころなるに、恥づかしく、はるばると曇りなき庭に立ち出づるほど、はしたなくて、やすきことなれど、苦しげなり。年老いたる博士どもの、なりあやしくやつれて、例馴れたるも、あはれに、さまざま御覧ずるなむ、をかしかりける。
楽どもなどは、さらにもいはずととのへさせたまへり。
楽どもなどは、さらにもいはずととのへさせたまへり。やうやう入り日になるほど、春の鴬囀るといふ舞、いとおもしろく見ゆるに、源氏の御紅葉の賀の折、思し出でられて、春宮、かざしたまはせて、せちに責めのたまはするに、逃がれがたくて、立ちてのどかに袖返すところを一折れ、けしきばかり舞ひたまへるに、似るべきものなく見ゆ。左大臣、恨めしさも忘れて、涙落したまふ。
「頭中将、いづら。遅し」
とあれば、柳花苑といふ舞を、これは今すこし過ぐして、かかることもやと、心づかひやしけむ、いとおもしろければ、御衣賜はりて、いとめづらしきことに人思へり。上達部皆乱れて舞ひたまへど、夜に入りては、ことにけぢめも見えず。文など講ずるにも、源氏の君の御をば、講師もえ読みやらず、句ごとに誦じののしる。博士どもの心にも、いみじう思へり。
かうやうの折にも、まづこの君を光にしたまへれば、帝もいかでかおろかに思されむ。中宮、御目のとまるにつけて、「春宮の女御のあながちに憎みたまふらむもあやしう、わがかう思ふも心憂し」とぞ、みづから思し返されける。
「おほかたに花の姿を見ましかば
つゆも心のおかれましやは」
御心のうちなりけむこと、いかで漏りにけむ 。
夜いたう更けてなむ、事果てける。
夜いたう更けてなむ、事果てける。
上達部おのおのあかれ、后、春宮帰らせたまひぬれば、のどやかになりぬるに、月いと明うさし出でてをかしきを、源氏の君、酔ひ心地に、見過ぐしがたくおぼえたまひければ、「上の人びともうち休みて、かやうに思ひかけぬほどに、もしさりぬべき隙もやある」と、藤壷わたりを、わりなう忍びてうかがひありけど、語らふべき戸口も鎖してければ、うち嘆きて、なほあらじに、弘徽殿の細殿に立ち寄りたまへれば、三の口開きたり。
女御は、上の御局にやがて参う上りたまひにければ、人少ななるけはひなり。奥の枢戸も開きて、人音もせず。
「かやうにて、世の中のあやまちはするぞかし」と思ひて、やをら上りて覗きたまふ。人は皆寝たるべし。いと若うをかしげなる声の、なべての人とは聞こえぬ、
「朧月夜に似るものぞなき」
とうち誦じて、こなたざまには来るものか。いとうれしくて、ふと袖をとらへたまふ。女、恐ろしと思へるけしきにて、
「あな、むくつけ。こは、誰そ」とのたまへど、
「何か、疎ましき」とて、
「深き夜のあはれを知るも入る月の
おぼろけならぬ契りとぞ思ふ」
とて、やをら抱き下ろして、戸は押し立てつ。
あさましきにあきれたるさま、いとなつかしうをかしげなり。
あさましきにあきれたるさま、いとなつかしうをかしげなり。わななくわななく、
「ここに、人」
と、のたまへど、
「まろは、皆人に許されたれば、召し寄せたりとも、なんでふことかあらむ。ただ、忍びてこそ」
とのたまふ声に、この君なりけりと聞き定めて、いささか慰めけり。わびしと思へるものから、情けなくこはごはしうは見えじ、と思へり。酔ひ心地や例ならざりけむ、許さむことは口惜しきに、女も若うたをやぎて、強き心も知らぬなるべし。
らうたしと見たまふに、ほどなく明けゆけば、心あわたたし。女は、まして、さまざまに思ひ乱れたるけしきなり。
「なほ、名のりしたまへ。いかでか、聞こゆべき。かうてやみなむとは、さりとも思されじ」
とのたまへば、
「憂き身世にやがて消えなば尋ねても
草の原をば問はじとや思ふ」
と言ふさま、艶になまめきたり。
「ことわりや。聞こえ違へたる文字かな」とて、
「いづれぞと露のやどりを分かむまに
小笹が原に風もこそ吹け
わづらはしく思すことならずは、何かつつまむ。もし、すかいたまふか」
とも言ひあへず、人々起き騒ぎ、上の御局に参りちがふけしきども、しげくまよへば、いとわりなくて、扇ばかりをしるしに取り換へて、出でたまひぬ。
(補足) ―草の原―
行くすゑは空もひとつのむさし野に草の原より出づる月かげ 藤原良経
霜がれはそことも見えぬ草の原たれに問はまし秋のなごりを 俊成の娘
見し秋を何に残さん草の原ひとつに変る野辺のけしきに 藤原良経
霜枯の野辺のあはれを見ぬ人や秋の色には心とめけむ 藤原隆信朝臣
桐壷には、人びと多くさぶらひて、おどろきたるもあれば、
桐壷には、人びと多くさぶらひて、おどろきたるもあれば、かかるを、
「さも、たゆみなき御忍びありきかな」
とつきじろひつつ、そら寝をぞしあへる。入りたまひて臥したまへれど、寝入られず。
「をかしかりつる人のさまかな。女御の御おとうとたちにこそはあらめ。まだ世に馴れぬは、五、六の君ならむかし。帥宮の北の方、頭中将のすさめぬ四の君などこそ、よしと聞きしか。なかなかそれならましかば、今すこしをかしからまし。六は春宮にたてまつらむとこころざしたまへるを、いとほしうもあるべいかな。わづらはしう、尋ねむほどもまぎらはし、さて絶えなむとは思はぬけしきなりつるを、いかなれば、言通はすべきさまを教へずなりぬらむ」
など、よろづに思ふも、心のとまるなるべし。かうやうなるにつけても、まづ、「かのわたりのありさまの、こよなう奥まりたるはや」と、ありがたう思ひ比べられたまふ。
その日は後宴のことありて、まぎれ暮らしたまひつ。
その日は後宴のことありて、まぎれ暮らしたまひつ。箏の琴仕うまつりたまふ。昨日のことよりも、なまめかしうおもしろし。藤壺は、暁に参う上りたまひにけり。「かの有明、出でやしぬらむ」と、心もそらにて、思ひ至らぬ隈なき良清、惟光をつけて、うかがはせたまひければ、御前よりまかでたまひけるほどに、
「ただ今、北の陣より、かねてより隠れ立ちてはべりつる車どもまかり出づる。御方々の里人はべりつるなかに、四位の少将、右中弁など急ぎ出でて、送りしはべりつるや、弘徽殿の御あかれならむと見たまへつる。けしうはあらぬけはひどもしるくて、車三つばかりはべりつ」
と聞こゆるにも、胸うちつぶれたまふ。
「いかにして、いづれと知らむ。父大臣など聞きて、ことことしうもてなさむも、いかにぞや。まだ、人のありさまよく見さだめぬほどは、わづらはしかるべし。さりとて、知らであらむ、はた、いと口惜しかるべければ、いかにせまし」と、思しわづらひて、つくづくとながめ臥したまへり。
「姫君、いかにつれづれならむ。日ごろになれば、
「姫君、いかにつれづれならむ。日ごろになれば、屈してやあらむ」と、らうたく思しやる。かのしるしの扇は、桜襲ねにて、濃きかたにかすめる月を描きて、水にうつしたる心ばへ、目馴れたれど、ゆゑなつかしうもてならしたり。「草の原をば」と言ひしさまのみ、心にかかりたまへば、
「世に知らぬ心地こそすれ有明の
月のゆくへを空にまがへて」
と書きつけたまひて、置きたまへり。
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第52回 「紅葉賀」その4~「花宴」その1 |
|---|---|
| 収録日 | 2004年7月10日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
平成16年春期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。