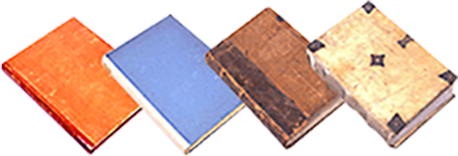第61回 「賢木」より その4
藤壺は思い悩み出家を考えるが春宮の為に押し殺す。源氏は雲林院へ籠る。紫の上と文を交わすが、理想的な女性になっている。朝顔ともやりとりをする。二条へ戻り藤壺へ紅葉に添え文を送る。

講師:岡野弘彦
- 目次
「いづこを面にてかは、またも見えたてまつらむ。
「いづこを面にてかは、またも見えたてまつらむ。いとほしと思し知るばかり」と思して、御文も聞こえたまはず。うち絶えて、内裏、春宮にも参りたまはず、籠もりおはして、起き臥し、「いみじかりける人の御心かな」と、人悪ろく恋しう悲しきに、心魂も失せにけるにや、悩ましうさへ思さる。もの心細く、「なぞや、世に経れば憂さこそまされ」と、思し立つには、この女君のいとらうたげにて、あはれにうち頼みきこえたまへるを、振り捨てむこと、いとかたし。
宮も、その名残、例にもおはしまさず。
宮も、その名残、例にもおはしまさず。かうことさらめきて籠もりゐ、おとづれたまはぬを、命婦などはいとほしがりきこゆ。宮も、春宮の御ためを思すには、「御心置きたまはむこと、いとほしく、世をあぢきなきものに思ひなりたまはば、ひたみちに思し立つこともや」と、さすがに苦しう思さるべし。
「かかること絶えずは、いとどしき世に、憂き名さへ漏り出でなむ。大后の、あるまじきことにのたまふなる位をも去りなむ」と、やうやう思しなる。院の思しのたまはせしさまの、なのめならざりしを思し出づるにも、「よろづのこと、ありしにもあらず、変はりゆく世にこそあめれ。戚夫人の見けむ目のやうにあらずとも、かならず、人笑へなることは、ありぬべき身にこそあめれ」など、世の疎ましく、過ぐしがたう思さるれば、背きなむことを思し取るに、春宮、見たてまつらで面変はりせむこと、あはれに思さるれば、忍びやかにて参りたまへり。
大将の君は、さらぬことだに、思し寄らぬことなく仕うまつりたまふを、
大将の君は、さらぬことだに、思し寄らぬことなく仕うまつりたまふを、御心地悩ましきにことつけて、御送りにも参りたまはず。おほかたの御とぶらひは、同じやうなれど、「むげに、思し屈しにける」と、心知るどちは、いとほしがりきこゆ。
宮は、いみじううつくしうおとなびたまひて、めづらしううれしと思して、むつれきこえたまふを、かなしと見たてまつりたまふにも、思し立つ筋はいとかたけれど、内裏わたりを見たまふにつけても、世のありさま、あはれにはかなく、移り変はることのみ多かり。
大后の御心もいとわづらはしくて、かく出で入りたまふにも、はしたなく、事に触れて苦しければ、宮の御ためにも危ふくゆゆしう、よろづにつけて思ほし乱れて、
「御覧ぜで、久しからむほどに、容貌の異ざまにてうたてげに変はりてはべらば、いかが思さるべき」
と聞こえたまへば、御顔うちまもりたまひて、
「式部がやうにや。いかでか、さはなりたまはむ」
と、笑みてのたまふ。いふかひなくあはれにて、
「それは、老いてはべれば醜きぞ。さはあらで、髪はそれよりも短くて、黒き衣などを着て、夜居の僧のやうになりはべらむとすれば、見たてまつらむことも、いとど久しかるべきぞ」
とて泣きたまへば、まめだちて、
「久しうおはせぬは、恋しきものを」
とて、涙の落つれば、恥づかしと思して、さすがに背きたまへる、御髪はゆらゆらときよらにて、まみのなつかしげに匂ひたまへるさま、おとなびたまふままに、ただかの御顔を脱ぎすべたまへり。御歯のすこし朽ちて、口の内黒みて、笑みたまへる薫りうつくしきは、女にて見たてまつらまほしうきよらなり。「いと、かうしもおぼえたまへるこそ、心憂けれ」と、玉の瑕に思さるるも、世のわづらはしさの、空恐ろしうおぼえたまふなりけり。
大将の君は、宮をいと恋しう思ひきこえたまへど、
大将の君は、宮をいと恋しう思ひきこえたまへど、「あさましき御心のほどを、時々は、思ひ知るさまにも見せたてまつらむ」と、念じつつ過ぐしたまふに、人悪ろく、つれづれに思さるれば、秋の野も見たまひがてら、雲林院に詣でたまへり。
「故母御息所の御兄の律師の籠もりたまへる坊にて、法文など読み、行なひせむ」と思して、二、三日おはするに、あはれなること多かり。
紅葉やうやう色づきわたりて、秋の野のいとなまめきたるなど見たまひて、
紅葉やうやう色づきわたりて、秋の野のいとなまめきたるなど見たまひて、故里も忘れぬべく思さる。法師ばらの、才ある限り召し出でて、論議せさせて聞こしめさせたまふ。所からに、いとど世の中の常なさを思し明かしても、なほ、「憂き人しもぞ」と、思し出でらるるおし明け方の月影に、法師ばらの閼伽たてまつるとて、からからと鳴らしつつ、菊の花、濃き薄き紅葉など、折り散らしたるも、はかなげなれど、
「このかたのいとなみは、この世もつれづれならず、後の世はた、頼もしげなり。さも、あぢきなき身をもて悩むかな」
など、思し続けたまふ。律師の、いと尊き声にて、
「念仏衆生摂取不捨」
と、うちのべて行なひたまへるは、いとうらやましければ、「なぞや」と思しなるに、まづ、姫君の心にかかりて思ひ出でられたまふぞ、いと悪ろき心なるや。
例ならぬ日数も、おぼつかなくのみ思さるれば、
例ならぬ日数も、おぼつかなくのみ思さるれば、御文ばかりぞ、しげう聞こえたまふめる。
「行き離れぬべしやと、試みはべる道なれど、つれづれも慰めがたう、心細さまさりてなむ。聞きさしたることありて、やすらひはべるほど、いかに」
など、陸奥紙にうちとけ書きたまへるさへぞ、めでたき。
「浅茅生の露のやどりに君をおきて
四方の嵐ぞ静心なき」
など、こまやかなるに、女君もうち泣きたまひぬ。御返し、白き色紙に、
「風吹けばまづぞ乱るる色変はる
浅茅が露にかかるささがに」
とのみありて、「御手はいとをかしうのみなりまさるものかな」と、独りごちて、うつくしとほほ笑みたまふ。
常に書き交はしたまへば、わが御手にいとよく似て、今すこしなまめかしう、女しきところ書き添へたまへり。「何ごとにつけても、けしうはあらず生ほし立てたりかし」と思ほす。
[休憩後の話題] 高松宮妃殿下の和歌
「お亡くなりになった高松宮妃殿下は、私が和歌の御用係を言いつけられて、皇族方の歌を拝見するようになった初めのころですが、高松宮妃殿下は皇族方の中でも大変熱心でいらして、月並の歌会なんかにも必ず何首か歌を詠んで、半紙を横長の形に二つ折にして、大体三首ぐらい書かれる。一枚で済まなくて、さらに二枚目を使って書かれて、そして漆塗りの通い箱がありまして、それに収められて、結んで、こよりで封をして毎回宮家の人が持ってこられるんです。拝見すると、お若いころから詠んでおられたから、当然旧派の和歌がしみついていられるわけです。旧派の歌で徹底して詠んでいられるわけです。」
・『菊と葵のものがたり』(中央文庫)
吹き交ふ風も近きほどにて、斎院にも聞こえたまひけり。
吹き交ふ風も近きほどにて、斎院にも聞こえたまひけり。中将の君に、
「かく、旅の空になむ、もの思ひにあくがれにけるを、思し知るにもあらじかし」
など、怨みたまひて、御前には、
「かけまくはかしこけれどもそのかみの
秋思ほゆる木綿欅かな
昔を今に、と思ひたまふるもかひなく、とり返されむもののやうに」
と、なれなれしげに、唐の浅緑の紙に、榊に木綿つけなど、神々しうしなして参らせたまふ。
御返り、中将、
「紛るることなくて、来し方のことを思ひたまへ出づるつれづれのままには、思ひやりきこえさすること多くはべれど、かひなくのみなむ」
と、すこし心とどめて多かり。御前のは、木綿の片端に、
「そのかみやいかがはありし木綿欅
心にかけてしのぶらむゆゑ
近き世に」
とぞある。
「御手、こまやかにはあらねど、らうらうじう、草などをかしうなりにけり。まして、朝顔もねびまさりたまふらむかし」と思ほゆるも、ただならず、恐ろしや。
「あはれ、このころぞかし。野の宮のあはれなりしこと」と思し出でて、
「あはれ、このころぞかし。野の宮のあはれなりしこと」と思し出でて、「あやしう、やうのもの」と、神恨めしう思さるる御癖の、見苦しきぞかし。わりなう思さば、さもありぬべかりし年ごろは、のどかに過ぐいたまひて、今は悔しう思さるべかめるも、あやしき御心なりや。
院も、かくなべてならぬ御心ばへを見知りきこえたまへれば、たまさかなる御返りなどは、えしももて離れきこえたまふまじかめり。すこしあいなきことなりかし。
六十巻といふ書、読みたまひ、
六十巻といふ書、読みたまひ、おぼつかなきところどころ解かせなどしておはしますを、「山寺には、いみじき光行なひ出だしたてまつれり」と、「仏の御面目あり」と、あやしの法師ばらまでよろこびあへり。しめやかにて、世の中を思ほしつづくるに、帰らむことももの憂かりぬべけれど、人一人の御こと思しやるがほだしなれば、久しうもえおはしまさで、寺にも御誦経いかめしうせさせたまふ。あるべき限り、上下の僧ども、そのわたりの山賤まで物賜び、尊きことの限りを尽くして出でたまふ。見たてまつり送るとて、このもかのもに、あやしきしはふるひどもも集りてゐて、涙を落としつつ見たてまつる。黒き御車のうちにて、藤の御袂にやつれたまへれば、ことに見えたまはねど、ほのかなる御ありさまを、世になく思ひきこゆべかめり。
女君は、日ごろのほどに、ねびまさりたまへる心地して、
女君は、日ごろのほどに、ねびまさりたまへる心地して、いといたうしづまりたまひて、世の中いかがあらむと思へるけしきの、心苦しうあはれにおぼえたまへば、あいなき心のさまざま乱るるやしるからむ、「色変はる」とありしもらうたうおぼえて、常よりことに語らひきこえたまふ。
山づとに持たせたまへりし紅葉、御前のに御覧じ比ぶれば、
山づとに持たせたまへりし紅葉、御前のに御覧じ比ぶれば、ことに染めましける露の心も見過ぐしがたう、おぼつかなさも、人悪るきまでおぼえたまへば、ただおほかたにて宮に参らせたまふ。命婦のもとに、
「入らせたまひにけるを、めづらしきこととうけたまはるに、宮の間の事、おぼつかなくなりはべりにければ、静心なく思ひたまへながら、行ひもつとめむなど、思ひ立ちはべりし日数を、心ならずやとてなむ、日ごろになりはべりにける。紅葉は、一人見はべるに、錦暗う思ひたまふればなむ。折よくて御覧ぜさせたまへ」
などあり。
げに、いみじき枝どもなれば、御目とまるに、例の、いささかなるものありけり。人びと見たてまつるに、御顔の色も移ろひて、
「なほ、かかる心の絶えたまはぬこそ、いと疎ましけれ。あたら思ひやり深うものしたまふ人の、ゆくりなく、かうやうなること、折々混ぜたまふを、人もあやしと見るらむかし」
と、心づきなく思されて、瓶に挿させて、廂の柱のもとにおしやらせたまひつ。
おほかたのことども、宮の御事に触れたることなどをば、うち頼めるさまに、すくよかなる御返りばかり聞こえたまへるを、「さも心かしこく、尽きせずも」と、恨めしうは見たまへど、何ごとも後見きこえならひたまひにたれば、「人あやしと、見とがめもこそすれ」と思して、まかでたまふべき日、参りたまへり。
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第61回 「賢木」より その4 |
|---|---|
| 収録日 | 2005年4月2日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
平成17年春期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。