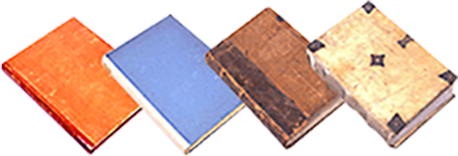第65回 「須磨」より その2
寝ずに自分を待っていた紫の上を、心からなぐさめる。源氏は花散里にも別れを言い、文の箱と琴一つを持ち、一切のことを紫の上に託し、朧月夜にも文を遣り、亡き桐壺の北山へ参詣し入道の宮(藤壺)にも別れを告げる。

講師:岡野弘彦
- 目次
-
- はじめに
- 殿におはしたれば、わが御方の人びとも、
- 西の対に渡りたまへれば、御格子も参らで、
- 「なほ世に許されがたうて、年月を経ば、巌の中にも迎へたてまつらむ。
- 帥宮、三位中将などおはしたり。
- 花散里の心細げに思して、常に聞こえたまふもことわりにて、
- 西面は、「かうしも渡りたまはずや」と、うち屈して思しけるに、
- よろづのことどもしたためさせたまふ。親しう仕まつり、世になびかぬ限りの人びと、
- わが御方の中務、中将などやうの人びと、
- 尚侍の御もとに、わりなくして聞こえたまふ。
- 明日とて、暮には、院の御墓拝みたてまつりたまふとて、
- 「見しはなくあるは悲しき世の果てを
- 御山に詣うでたまひて、おはしましし御ありさま、
- 明け果つるほどに帰りたまひて、春宮にも御消息聞こえたまふ。
はじめに
・梅雨の季節を迎えて
殿におはしたれば、わが御方の人びとも、
殿におはしたれば、わが御方の人びとも、まどろまざりけるけしきにて、所々に群れゐて、あさましとのみ世を思へるけしきなり。侍には、親しう仕まつる限りは、御供に参るべき心まうけして、私の別れ惜しむほどにや、人もなし。さらぬ人は、とぶらひ参るも重き咎めあり、わづらはしきことまされば、所狭く集ひし馬、車の方もなく、寂しきに、「世は憂きものなりけり」と、思し知らる。
台盤なども、かたへは塵ばみて、畳、所々引き返したり。「見るほどだにかかり。ましていかに荒れゆかむ」と思す。
西の対に渡りたまへれば、御格子も参らで、
西の対に渡りたまへれば、御格子も参らで、眺め明かしたまひければ、簀子などに、若き童女、所々に臥して、今ぞ起き騒ぐ。宿直姿どもをかしうてゐるを見たまふにも、心細う、「年月経ば、かかる人びとも、えしもあり果てでや、行き散らむ」など、さしもあるまじきことさへ、御目のみとまりけり。
「昨夜は、しかしかして夜更けにしかばなむ。例の思はずなるさまにや思しなしつる。かくてはべるほどだに御目離れずと思ふを、かく世を離るる際には、心苦しきことのおのづから多かりける、ひたやごもりにてやは。常なき世に、人にも情けなきものと心おかれ果てむと、いとほしうてなむ」
と聞こえたまへば、
「かかる世を見るよりほかに、思はずなることは、何ごとにか」
とばかりのたまひて、いみじと思し入れたるさま、人よりことなるを、ことわりぞかし、父親王、いとおろかにもとより思しつきにけるに、まして、世の聞こえをわづらはしがりて、訪れきこえたまはず、御とぶらひにだに渡りたまはぬを、人の見るらむことも恥づかしく、なかなか知られたてまつらでやみなましを、継母の北の方などの、
「にはかなりし幸ひのあわたたしさ。あな、ゆゆしや。思ふ人、方々につけて別れたまふ人かな」
とのたまひけるを、さる便りありて漏り聞きたまふにも、いみじう心憂ければ、これよりも絶えて訪れきこえたまはず。また頼もしき人もなく、げにぞ、あはれなる御ありさまなる。
「なほ世に許されがたうて、年月を経ば、巌の中にも迎へたてまつらむ。
「なほ世に許されがたうて、年月を経ば、巌の中にも迎へたてまつらむ。ただ今は、人聞きのいとつきなかるべきなり。朝廷にかしこまりきこゆる人は、明らかなる月日の影をだに見ず、安らかに身を振る舞ふことも、いと罪重かなり。過ちなけれど、さるべきにこそかかることもあらめと思ふに、まして思ふ人具するは、例なきことなるを、ひたおもむきにものぐるほしき世にて、立ちまさることもありなむ」
など聞こえ知らせたまふ。
日たくるまで大殿籠もれり。
帥宮、三位中将などおはしたり。
帥宮、三位中将などおはしたり。対面したまはむとて、御直衣などたてまつる。
「位なき人は」
とて、無紋の直衣、なかなか、いとなつかしきを着たまひて、うちやつれたまへる、いとめでたし。御鬢かきたまふとて、鏡台に寄りたまへるに、面痩せたまへる影の、我ながらいとあてにきよらなれば、
「こよなうこそ、衰へにけれ。この影のやうにや痩せてはべる。あはれなるわざかな」
とのたまへば、女君、涙一目うけて、見おこせたまへる、いと忍びがたし。
「身はかくてさすらへぬとも君があたり
去らぬ鏡の影は離れじ」
と、聞こえたまへば、
「別れても影だにとまるものならば
鏡を見ても慰めてまし」
柱隠れにゐ隠れて、涙を紛らはしたまへるさま、「なほ、ここら見るなかにたぐひなかりけり」と、思し知らるる人の御ありさまなり。
親王は、あはれなる御物語聞こえたまひて、暮るるほどに帰りたまひぬ。
花散里の心細げに思して、常に聞こえたまふもことわりにて、
花散里の心細げに思して、常に聞こえたまふもことわりにて、「かの人も、今ひとたび見ずは、つらしとや思はむ」と思せば、その夜は、また出でたまふものから、いともの憂くて、いたう更かしておはしたれば、女御、
「かく数まへたまひて、立ち寄らせたまへること」
と、よろこびきこえたまふさま、書き続けむもうるさし。
いといみじう心細き御ありさま、ただ御蔭に隠れて過ぐいたまへる年月、いとど荒れまさらむほど思しやられて、殿の内、いとかすかなり。
月おぼろにさし出でて、池広く、山木深きわたり、心細げに見ゆるにも、住み離れたらむ巌のなか、思しやらる。
西面は、「かうしも渡りたまはずや」と、うち屈して思しけるに、
西面は、「かうしも渡りたまはずや」と、うち屈して思しけるに、あはれ添へたる月影の、なまめかしうしめやかなるに、うち振る舞ひたまへるにほひ、似るものなくて、いと忍びやかに入りたまへば、すこしゐざり出でて、やがて月を見ておはす。またここに御物語のほどに、明け方近うなりにけり。
「短か夜のほどや。かばかりの対面も、またはえしもやと思ふこそ、ことなしにて過ぐしつる年ごろも悔しう、来し方行く先のためしになるべき身にて、何となく心のどまる世なくこそありけれ」
と、過ぎにし方のことどものたまひて、鶏もしばしば鳴けば、世につつみて急ぎ出でたまふ。例の、月の入り果つるほど、よそへられて、あはれなり。女君の濃き御衣に映りて、げに、漏るる顔なれば、
「月影の宿れる袖はせばくとも
とめても見ばやあかぬ光を」
いみじと思いたるが、心苦しければ、かつは慰めきこえたまふ。
「行きめぐりつひにすむべき月影の
しばし雲らむ空な眺めそ
思へば、はかなしや。ただ、知らぬ涙のみこそ、心を昏らすものなれ」
などのたまひて、明けぐれのほどに出でたまひぬ。
よろづのことどもしたためさせたまふ。親しう仕まつり、世になびかぬ限りの人びと、
よろづのことどもしたためさせたまふ。親しう仕まつり、世になびかぬ限りの人びと、殿の事とり行なふべき上下、定め置かせたまふ。御供に慕ひきこゆる限りは、また選り出でたまへり。
かの山里の御住みかの具は、えさらずとり使ひたまふべきものども、ことさらよそひもなくことそぎて、さるべき書ども文集など入りたる箱、さては琴一つぞ持たせたまふ。所狭き御調度、はなやかなる御よそひなど、さらに具したまはず、あやしの山賤めきてもてなしたまふ。
さぶらふ人びとよりはじめ、よろづのこと、みな西の対に聞こえわたしたまふ。領じたまふ御荘、御牧よりはじめて、さるべき所々、券など、みなたてまつり置きたまふ。それよりほかの御倉町、納殿などいふことまで、少納言をはかばかしきものに見置きたまへれば、親しき家司ども具して、しろしめすべきさまどものたまひ預く。
わが御方の中務、中将などやうの人びと、
わが御方の中務、中将などやうの人びと、つれなき御もてなしながら、見たてまつるほどこそ慰めつれ、「何ごとにつけてか」と思へども、
「命ありてこの世にまた帰るやうもあらむを、待ちつけむと思はむ人は、こなたにさぶらへ」
とのたまひて、上下、皆参う上らせたまふ。
若君の御乳母たち、花散里なども、をかしきさまのはさるものにて、まめまめしき筋に思し寄らぬことなし。
尚侍の御もとに、わりなくして聞こえたまふ。
尚侍の御もとに、わりなくして聞こえたまふ。
「問はせたまはぬも、ことわりに思ひたまへながら、今はと、世を思ひ果つるほどの憂さもつらさも、たぐひなきことにこそはべりけれ。
逢ふ瀬なき涙の河に沈みしや
流るる澪の初めなりけむ
と思ひたまへ出づるのみなむ、罪逃れがたうはべりける」
道のほども危ふければ、こまかには聞こえたまはず。
女、いといみじうおぼえたまひて、忍びたまへど、御袖よりあまるも所狭うなむ。
「涙河浮かぶ水泡も消えぬべし
流れて後の瀬をも待たずて」
泣く泣く乱れ書きたまへる御手、いとをかしげなり。今ひとたび対面なくやと思すは、なほ口惜しけれど、思し返して、憂しと思しなすゆかり多うて、おぼろけならず忍びたまへば、いとあながちにも聞こえたまはずなりぬ。
明日とて、暮には、院の御墓拝みたてまつりたまふとて、
明日とて、暮には、院の御墓拝みたてまつりたまふとて、北山へ詣でたまふ。暁かけて月出づるころなれば、まづ、入道の宮に参うでたまふ。近き御簾の前に御座参りて、御みづから聞こえさせたまふ。春宮の御事をいみじううしろめたきものに思ひきこえたまふ。
かたみに心深きどちの御物語は、よろづあはれまさりけむかし。なつかしうめでたき御けはひの昔に変はらぬに、つらかりし御心ばへも、かすめきこえさせまほしけれど、今さらにうたてと思さるべし、わが御心にも、なかなか今ひときは乱れまさりぬべければ、念じ返して、ただ、
「かく思ひかけぬ罪に当たりはべるも、思うたまへあはすることの一節になむ、空も恐ろしうはべる。惜しげなき身はなきになしても、宮の御世にだに、ことなくおはしまさば」
とのみ聞こえたまふぞ、ことわりなるや。
宮も、みな思し知らるることにしあれぼ、御心のみ動きて、聞こえやりたまはず。大将、よろづのことかき集め思し続けて、泣きたまへるけしき、いと尽きせずなまめきたり。
「御山に参りはべるを、御ことつてや」
と聞こえたまふに、とみにものも聞こえたまはず、わりなくためらひたまふ御けしきなり。
「見しはなくあるは悲しき世の果てを
「見しはなくあるは悲しき世の果てを
背きしかひもなくなくぞ経る」
いみじき御心惑ひどもに、思し集むることどもも、えぞ続けさせたまはぬ。
「別れしに悲しきことは尽きにしを
またぞこの世の憂さはまされる」
月待ち出でて出でたまふ。御供にただ五、六人ばかり、下人もむつましき限りして、御馬にてぞおはする。さらなることなれど、ありし世の御ありきに異なり、皆いと悲しう思ふなり。なかに、かの御禊の日、仮の御随身にて仕うまつりし右近の将監の蔵人、得べきかうぶりもほど過ぎつるを、つひに御簡削られ、官も取られて、はしたなければ、御供に参るうちなり。
賀茂の下の御社を、かれと見渡すほど、ふと思ひ出でられて、下りて、御馬の口を取る。
「ひき連れて葵かざししそのかみを
思へばつらし賀茂の瑞垣」
と言ふを、「げに、いかに思ふらむ。人よりけにはなやかなりしものを」と思すも、心苦し。
君も、御馬より下りたまひて、御社のかた拝みたまふ。神にまかり申したまふ。
「憂き世をば今ぞ別るるとどまらむ
名をば糺の神にまかせて」
とのたまふさま、ものめでする若き人にて、身にしみてあはれにめでたしと見たてまつる。
御山に詣うでたまひて、おはしましし御ありさま、
御山に詣うでたまひて、おはしましし御ありさま、ただ目の前のやうに思し出でらる。限りなきにても、世に亡くなりぬる人ぞ、言はむかたなく口惜しきわざなりける。よろづのことを泣く泣く申したまひても、そのことわりをあらはに承りたまはねば、「さばかり思しのたまはせしさまざまの御遺言は、いづちか消え失せにけむ」と、いふかひなし。
御墓は、道の草茂くなりて、分け入りたまふほど、いとど露けきに、月も隠れて、森の木立、木深く心すごし。帰り出でむ方もなき心地して、拝みたまふに、ありし御面影、さやかに見えたまへる、そぞろ寒きほどなり。
「亡き影やいかが見るらむよそへつつ
眺むる月も雲隠れぬる」
明け果つるほどに帰りたまひて、春宮にも御消息聞こえたまふ。
明け果つるほどに帰りたまひて、春宮にも御消息聞こえたまふ。王命婦を御代はりにてさぶらはせたまへば、「その局に」とて、
「今日なむ、都離れはべる。また参りはべらずなりぬるなむ、あまたの憂へにまさりて思うたまへられはべる。よろづ推し量りて啓したまへ。
いつかまた春の都の花を見む
時失へる山賤にして」
桜の散りすきたる枝につけたまへり。「かくなむ」と御覧ぜさすれば、幼き御心地にもまめだちておはします。
「御返りいかがものしはべらむ」
と啓すれば、
「しばし見ぬだに恋しきものを、遠くはましていかに、と言へかし」
とのたまはす。「ものはかなの御返りや」と、あはれに見たてまつる。あぢきなきことに御心をくだきたまひし昔のこと、折々の御ありさま、思ひ続けらるるにも、もの思ひなくて我も人も過ぐいたまひつべかりける世を、心と思し嘆きけるを悔しう、わが心ひとつにかからむことのやうにぞおぼゆる。御返りは、
「さらに聞こえさせやりはべらず。御前には啓しはべりぬ。心細げに思し召したる御けしきもいみじくなむ」
と、そこはかとなく、心の乱れけるなるべし。
「咲きてとく散るは憂けれどゆく春は
花の都を立ち帰り見よ
時しあらば」
と聞こえて、名残もあはれなる物語をしつつ、一宮のうち、忍びて泣きあへり。
一目も見たてまつれる人は、かく思しくづほれぬる御ありさまを、嘆き惜しみきこえぬ人なし。まして、常に参り馴れたりしは、知り及びたまふまじき長女、御厠人まで、ありがたき御顧みの下なりつるを、「しばしにても、見たてまつらぬほどや経む」と、思ひ嘆きけり。
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第65回 「須磨」より その2 |
|---|---|
| 収録日 | 2005年6月4日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
平成17年春期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。