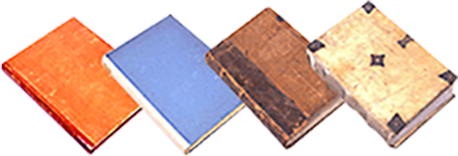第73回 「明石」より その4
源氏は春宮の後見役でもあり赦される。当初は多くはなかった源氏の、明石の君との逢瀬が重なる。懐妊した明石の君と後朝を交わし、「ねびととの」った紫の上の迎える都へ戻る。

講師:岡野弘彦
- 目次
-
- はじめに
- 年変はりぬ。内裏に御薬のことありて、
- つひのことと思ひしかど、世の常なきにつけても、
- そのころは、夜離れなく語らひたまふ。
- さぶらふ人びと、ほどほどにつけてはよろこび思ふ。
- 明後日ばかりになりて、例のやうにいたくも更かさで渡りたまへり。
- このたびは立ち別るとも藻塩焼く煙は同じ方になびかむ
- 「琴は、また掻き合はするまでの形見に」
- 立ちたまふ暁は、夜深く出でたまひて、
- うれしきにも、「げに、今日を限りに、
- 世をうみにここらしほじむ身となりてなほこの岸をえこそ離れね
- 正身の心地、たとふべき方なくて、かうしも人に見えじと思ひ沈むれど
- 君は、難波の方に渡りて御祓へしたまひて、
- 二条院におはしまし着きて、都の人も、御供の人も、
- 召しありて、内裏に参りたまふ。
- 院の御ために、八講行はるべきこと、
- まことや、かの明石には、返る波につけて御文つかはす。
はじめに
・一日だけのお正月気分
「今はあわただしい時代ですから、お正月もなるべく早く済ませてしまいますけれども、昔流に言えば、十五日くらいまでは正月でございまして、私の家なんかも神主の家ですから、なるべくお正月が長い方がいいわけです。つまり参拝者がたくさん来ますから。子供のころから、十五日まで正月だというふうな気分でおりましたけれども、最近では、宮中の歌会始が十日前後でありまして、その歌会始が終わらないと私は肩の荷が下りたような気がしませんで、お正月というよりは、歌会始が終わると、あの日一日だけが正月で、そこまで何となく緊張しているんです。」
年変はりぬ。内裏に御薬のことありて、
年変はりぬ。内裏(うち)に御薬のことありて、世の中さまざまにののしる。当代の御子は、右大臣の女(むすめ)、承香殿(そきやうでん)の女御の御腹に男御子生まれたまへる、二つになりたまへば、いといはけなし。春宮(とうぐう)にこそは譲りきこえたまはめ。朝廷(おほやけ)の御後見をし、世をまつりごつべき人を思しめぐらすに、この源氏のかく沈みたまふこと、いとあたらしうあるまじきことなれば、つひに后(きさい)の御諌めをも背きて、赦されたまふべき定め出で来ぬ。
去年(こぞ)より、后も御もののけ悩みたまひ、さまざまのもののさとししきりに、騒がしきを、いみじき御つつしみどもをしたまふしるしにや、よろしうおはしましける御目の悩みさへ、このころ重くならせたまひて、もの心細く思されければ、七月二十余日のほどに、また重ねて、京へ帰りたまふべき宣旨下る。
つひのことと思ひしかど、世の常なきにつけても、
つひのことと思ひしかど、世の常なきにつけても、「いかになり果つべきにか」と嘆きたまふを、かうにはかなれば、うれしきに添へても、また、この浦を今はと思ひ離れむことを思し嘆くに、入道、さるべきことと思ひながら、うち聞くより胸ふたがりておぼゆれど、「思ひのごと栄えたまはばこそは、我が思ひの叶ふにはあらめ」など、思ひ直す。
そのころは、夜離れなく語らひたまふ。
そのころは、夜(よ)離(か)れなく語らひたまふ。六月ばかりより心苦しきけしきありて悩みけり。かく別れたまふべきほどなれば、あやにくなるにやありけむ、ありしよりもあはれに思して、「あやしうもの思ふべき身にもありけるかな」と思し乱る。
女は、さらにも言はず思ひ沈みたり。いとことわりなりや。思ひの外(ほか)に悲しき道に出で立ちたまひしかど、「つひには行きめぐり来なむ」と、かつは思し慰めき。
このたびはうれしき方の御出で立ちの、「またやは帰り見るべき」と思すに、あはれなり 。
さぶらふ人びと、ほどほどにつけてはよろこび思ふ。
さぶらふ人びと、ほどほどにつけてはよろこび思ふ。京よりも御迎へに人びと参り、心地よげなるを、主人(あるじ)の入道、涙にくれて、月も立ちぬ。
ほどさへあはれなる空のけしきに、「なぞや、心づから今も昔も、すずろなることにて身をはふらかすらむ」と、さまざまに思し乱れたるを、心知れる人びとは、
「あな憎、例の御癖ぞ」
と、見たてまつりむつかるめり。
「月ごろは、つゆ人にけしき見せず、時々はひ紛れなどしたまへるつれなさを」
「このころ、あやにくに、なかなかの、人の心づくしに」
と、つきじろふ。少納言、しるべして聞こえ出でし初めのことなど、ささめきあへるを、ただならず思へり 。
明後日ばかりになりて、例のやうにいたくも更かさで渡りたまへり。
明後日(あさて)ばかりになりて、例のやうにいたくも更かさで渡りたまへり。さやかにもまだ見たまはぬ容貌(かたち)など、「いとよしよししう、気高きさまして、めざましうもありけるかな」と、見捨てがたく口惜しう思さる。「さるべきさまにして迎へむ」と思しなりぬ。さやうにぞ語らひ慰めたまふ。
男の御容貌(かたち)、ありさまはた、さらにも言はず。年ごろの御行なひにいたく面(おも)痩せたまへるしも、言ふ方なくめでたき御ありさまにて、心苦しげなるけしきにうち涙ぐみつつ、あはれ深く契りたまへるは、「ただかばかりを、幸ひにても、などか止(や)まざらむ」とまでぞ見ゆめれど、めでたきにしも、我が身のほどを思ふも、尽きせず。波の声、秋の風には、なほ響きことなり。塩焼く煙かすかにたなびきて、とりあつめたる所のさまなり。
このたびは立ち別るとも藻塩焼く煙は同じ方になびかむ
「このたびは立ち別るとも藻塩焼く
煙は同じ方(かた)になびかむ」
とのたまへば、
「かきつめて海人のたく藻の思ひにも
今はかひなき恨みだにせじ」
あはれにうち泣きて、言(こと)少ななるものから、さるべき節の御応(いら)へなど浅からず聞こゆ。この、常にゆかしがりたまふ物の音(ね)など、さらに聞かせた てまつらざりつるを、いみじう恨みたまふ。
「さらば、形見にも偲(しの)ぶばかりの一琴(こと)をだに」
とのたまひて、京より持ておはしたりし琴(きん)の御琴取りに遣はして、心ことなる調べをほのかにかき鳴らしたまへる、深き夜の澄めるは、たとへむ方なし。
入道、え堪へで箏(さう)の琴取りてさし入れたり。みづからも、いとど涙さへそそのかされて、とどむべき方なきに、誘はるるなるべし、忍びやかに調べたるほど、いと上衆(じゃうず)めきたり。入道の宮の御琴の音(ね)を、ただ今のまたな きものに思ひきこえたるは、「今めかしう、あなめでた」と、聞く人の心ゆきて、容貌(かたち)さへ思ひやらるることは、げに、いと限りなき御琴の音(ね)なり。
これはあくまで弾き澄まし、心にくくねたき音(ね)ぞまされる。この御心にだに、初めてあはれになつかしう、まだ耳なれたまはぬ手など、心やましきほどに弾きさしつつ、飽かず思さるるにも、「月ごろ、など強ひても、聞きならさざりつらむ」と、悔しう思さる。心の限り行く先の契りをのみしたまふ 。
「琴は、また掻き合はするまでの形見に」
「琴(きん)は、また掻き合はするまでの形見に」
とのたまふ。
女、
「なほざりに頼め置くめる一ことを
尽きせぬ音(ね)にやかけて偲ばむ」
言ふともなき口すさびを、恨みたまひて、
「逢ふまでのかたみに契る中の緒の
調べはことに変はらざらなむ
この音(ね)違(たが)はぬさきにかならずあひ見む」
と頼めたまふめり。されど、ただ別れむほどのわりなさを思ひ咽(む)せたるも、いとことわりなり 。
立ちたまふ暁は、夜深く出でたまひて、
立ちたまふ暁は、夜深く出でたまひて、御迎への人びとも騒がしければ、心も空なれど、人まをはからひて、
「うち捨てて立つも悲しき浦波の
名残いかにと思ひやるかな」
御返り、
「年経(へ)つる苫屋も荒れて憂き波の
返る方にや身をたぐへまし」
と、うち思ひけるままなるを見たまふに、忍びたまへど、ほろほろとこぼれぬ。心知らぬ人びとは、
「なほかかる御住まひなれど、年ごろといふばかり馴れたまへるを、今はと思すは、さもあることぞかし」
など見たてまつる。
良清などは、「おろかならず思すなめりかし」と、憎くぞ思ふ。
うれしきにも、「げに、今日を限りに、
うれしきにも、「げに、今日を限りに、この渚を別るること」などあはれがりて、口々しほたれ言ひあへることどもあめり。されど、何かはとてなむ。
入道、今日の御まうけ、いといかめしう仕うまつれり。人びと、下(しも)の品(しな)まで、旅の装束(さうぞく)めづらしきさまなり。いつの間にかしあへけむと見えたり。御よそひは言ふべくもあらず。御衣櫃(みぞびつ)あまたかけさぶらはす。まことの都の苞(つと)にしつべき御贈り物ども、ゆゑづきて、思ひ寄らぬ隈(くま)なし。今日たてまつるべき狩の御装束に、
「寄る波に立ちかさねたる旅衣(ごろも)
しほどけしとや人の厭(いと)はむ」
とあるを御覧じつけて、騒がしけれど、
「かたみにぞ換(か)ふべかりける逢ふことの
日数隔てむ中の衣を」
とて、「心ざしあるを」とて、たてまつり替(か)ふ。御身になれたるどもを遣はす。げに、今一重(ひとへ)偲ばれたまふべきことを添ふる形見なめり。えならぬ御衣(ぞ)に匂ひの移りたるを、いかが人の心にも染(し)めざらむ。
入道、
「今はと世を離れはべりにし身なれども、今日の御送りに仕うまつらぬこと」
など申して、かひをつくるもいとほしながら、若き人は笑ひぬべし。
◆(評釈)・「きぬぎぬの別れ」の心の伝統(10分20秒~)
世をうみにここらしほじむ身となりてなほこの岸をえこそ離れね
「世をうみにここらしほじむ身となりて
なほこの岸をえこそ離れね
心の闇は、いとど惑ひぬべくはべれば、境までだに」と聞こえて、
「好き好きしきさまなれど、思し出でさせたまふ折はべらば」
など、御けしき賜はる。
いみじうものをあはれと思して、所々うち赤みたまへる御まみのわたりなど、言はむかたなく見えたまふ。
「思ひ捨てがたき筋もあめれば、今いととく見直したまひてむ。ただこの住みかこそ見捨てがたけれ。いかがすべき」とて、
「都出でし春の嘆きに劣らめや
年経(ふ)る浦を別れぬる秋」
とて、おし拭(のご)ひたまへるに、いとどものおぼえず、しほたれまさる。立ちゐもあさましうよろぼふ。
正身の心地、たとふべき方なくて、かうしも人に見えじと思ひ沈むれど
正身(さうじみ)の心地、たとふべき方なくて、かうしも人に見えじと思ひ沈むれど、身の憂きをもとにて、わりなきことなれど、うち捨てたまへる恨みのやる方なきに、おもかげそひて忘れがたきに、たけきこととは、ただ涙に沈めり。母君も慰めわびて、
「何に、かく心尽くしなることを思ひそめけむ。すべて、ひがひがしき人に従ひける心のおこたりぞ」
と言ふ。入道、
「あなかまや。思し捨つまじきこともものしたまふめれば、さりとも、思すところあらむ。思ひ慰めて、御湯などをだに参れ。あな、ゆゆしや」とて、片隅に寄りゐたり。乳母(めのと)、母君など、ひがめる心を言ひ合はせつつ、
「いつしか、いかで思ふさまにて見たてまつらむと、年月を頼み過ぐし、今や、思ひ叶ふとこそ頼みきこえつれ、心苦しきことをも、もののはじめに見るかな」
と嘆くを見るにも、いとほしければ、いとどほけられて、昼は日一日(ひとひ)、寝(い)をのみ寝(ね)暮らし、夜はすくよかに起きゐて、「数珠の行方も知らずなりにけり」とて、手をおしすりて仰ぎゐたり。
弟子どもにあはめられて、月夜に出でて行道(ぎやうだう)するものは、遣水(やりみず)に倒れ入りにけり。よしある岩の片側(かたそば)に腰もつきそこなひて、病(や)み臥したるほどになむ、すこしもの紛れける 。
君は、難波の方に渡りて御祓へしたまひて、
君は、難波の方に渡りて御祓へしたまひて、住吉にも、平らかにて、いろいろの願果たし申すべきよし、御使して申させたまふ。にはかに所狭(せ)うて、みづからはこのたびえ詣(まう)でたまはず、ことなる御逍遥(せうえう)などなくて、急ぎ入りたまひぬ。
二条院におはしまし着きて、都の人も、御供の人も、
二条院におはしまし着きて、都の人も、御供の人も、夢の心地して行き合ひ、喜び泣きもゆゆしきまで立ち騷ぎたり。
女君も、かひなきものに思し捨てつる命、うれしう思さるらむかし。いとうつくしげにねびととのほりて、御もの思ひのほどに、所狭かりし御髪(ぐし)のすこしへがれたるしも、いみじうめでたきを、「今はかくて見るべきぞかし」と、御心落ちゐるにつけては、また、かの飽かず別れし人の思へりしさま、心苦しう思しやらる。なほ世とともに、かかる方にて御心の暇(いとま)ぞなきや。
その人のことどもなど聞こえ出でたまへり。思し出でたる御けしき浅からず見ゆるを、ただならずや見たてまつりたまふらむ、わざとならず、「身をば思はず」など、ほのめかしたまふぞ、をかしうらうたく思ひきこえたまふ。かつ、「見るにだに飽かぬ御さまを、いかで隔てつる年月ぞ」と、あさましきまで思ほすに、取り返し、世の中もいと恨めしうなむ。
ほどもなく、元の御位あらたまりて、員(かず)より外(ほか)の権大納言になりたまふ。次々の人も、さるべき限りは元の官(つかさ)返し賜はり、世に許さるるほど、枯れたりし木の春にあへる心地して、いとめでたげなり 。
召しありて、内裏に参りたまふ。
召しありて、内裏(うち)に参りたまふ。御前(まへ)にさぶらひたまふに、ねびまさりて、「いかで、さるものむつかしき住まひに年経(へ)たまひつらむ」と見たてまつる。女房などの、院の御時よりさぶらひて、老いしらへるどもは、悲しくて、今さらに泣き騒ぎめできこゆ。
主上(うへ)も、恥づかしうさへ思し召されて、御よそひなどことに引きつくろひて出でおはします。御心地、例ならで、日ごろ経(へ)させたまひければ、いたう衰へさせたまへるを、昨日今日ぞ、すこしよろしう思されける。御物語しめやかにありて、夜に入りぬ。
十五夜の月おもしろう静かなるに、昔のこと、かき尽くし思し出でられて、しほたれさせたまふ。もの心細く思さるるなるべし。
「遊びなどもせず、昔聞きし物の音(ね)なども聞かで、久しうなりにけるかな」
とのたまはするに、
「わたつ海にしなえうらぶれ蛭の児の
脚立たざりし年は経にけり」
と聞こえたまへば、いとあはれに心恥づかしう思されて、
「宮柱めぐりあひける時しあれば
別れし春の恨み残すな」
いとなまめかしき御ありさまなり。
◆(評釈)・「蛭の子」/「宮柱」(7分45秒~)
院の御ために、八講行はるべきこと、
院の御ために、八講(はこう)行はるべきこと、まづ急がせたまふ。春宮(とうぐう)を見たてまつりたまふに、こよなくおよすけさせたまひて、めづらしう思しよろこびたるを、限りなくあはれと見たてまつりたまふ。御才(ざえ)もこよなくまさらせたまひて、世をたもたせたまはむに、憚りあるまじく、かしこく見えさせたまふ。
入道の宮にも、御心すこし静めて、御対面のほどにも、あはれなることどもあらむかし。
まことや、かの明石には、返る波につけて御文つかはす。
まことや、かの明石には、返る波につけて御文つかはす。ひき隠してこまやかに書きたまふめり。
「波のよるよるいかに、
嘆きつつ明石の浦に朝霧の
立つやと人を思ひやるかな」
かの帥(そち)の娘の五節、あいなく、人知れぬもの思ひさめぬる心地して、まくなぎつくらせてさし置かせけり。
「須磨の浦に心を寄せし舟人(ふなびと)の
やがて朽(く)たせる袖を見せばや」
「手などこよなくまさりにけり」と、見おほせたまひて、遣はす。
「帰りてはかことやせまし寄せたりし
名残に袖の干がたかりしを」
「飽かずをかし」と思しし名残なれば、おどろかされたまひて、いとど思し出づれど、このころは、さやうの御振る舞ひ、さらにつつみたまふめり。
花散里などにも、ただ御消息(せうそこ)などばかりにて、おぼつかなく、なかなか恨めしげなり。
◆(評釈)・「朝霧の立つ」(3分~7分30秒)
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第73回 「明石」より その4 |
|---|---|
| 収録日 | 2006年1月14日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
平成17年秋期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。