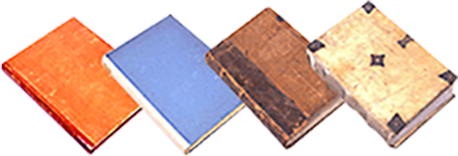第88回 「薄雲」より その4
冒頭正月に「若水をくむ」話。帝は、法師の話に臥せり大臣(源氏)の位が臣下であることを悩む。桃園式部卿も亡くなり「秋の司召」に帝は退位の気持ちを大臣(源氏)に話す。大臣(源氏)は「いとまばゆく、恐ろしう思」す。

講師:岡野弘彦
- 目次
-
- 若水をくむ
- 今様 昔話 ― この世にはあらぬむごき話して、人の世のあはれを知るが、まことの昔話なりしものを
- 主上は、夢のやうにいみじきことを聞かせたまひて、いろいろに思し乱れさせたまふ。
- その日、式部卿の親王亡せたまひぬるよし奏するに、
- 主上は、王命婦に詳しきことは、問はまほしう思し召せど、
- 秋の司召に、太政大臣になりたまふべきこと、うちうちに定め申したまふついでになむ、
- なほ思しめぐらすに、 「故宮の御ためにもいとほしう、
- 斎宮の女御は、思ししもしるき御後見にて、やむごとなき御おぼえなり。
- 「前栽どもこそ残りなく紐解きはべりにけれ。
- 「過ぎにし方、ことに思ひ悩むべきこともなくてはべりぬべかりし世の中にも、
- 「中ごろ、身のなきに沈みはべりしほど、方々に思ひたまへしことは、
若水をくむ
・年の初めの予祝の行事
「昔の農村なんかの生活感覚ですと、十五日正月と言って、十五日まではまだ正月のうち、あるいは七日松の内は正月の気持ちで過ごしたわけです。さらに農村なんかでは、月半ば、十五日正月まで、『鳥追い』とか、『もぐら打ち』とか、『庭田植え』とか、年の初めのいろんな予祝の行事があって、これがなかなか忙しかったんです。一年の初めのときに、凝縮した形でその一年の通しの収穫の予祝をしておかないと、その年がいい年にならないという農耕生活の上の長い信仰があって、それを非常に大事にして生きていたわけです。戦後、一番変わったのは、まずそういう部分ですね。」
<若水をくむ>
初めて若水をくんだのは、五歳になった正月のことである。
大歳(おおとし)の夜を眠らないで過した母親は、父が森の中の神社へ歳旦(さいたん)祭に上ったのち、私を起こして、家の下を流れる川へ若水をくみにゆくための羽織・袴(はかま)をつけさせ、川の神にとなえる呪文(じゅもん)をおしえる。
今朝 くむ水は
福くむ 水くむ 宝くむ
命ながくの 水をくむかな
くり返し暗誦(あんしょう)したのち、男衆の万さんの提灯(ちょうちん)に照らされた暁闇(ぎょうあん)の道を、雪を踏み分けて川辺へ下る。
そのころ父は神社の本殿にこもって、いつものように「神風の伊勢の雲出(くもづ)の川上、朝川夕川の瀬の音(と)きよきこれの河内(かふち)を、鎮宮(しづみや)どころと定めまつりて…」と、祝詞をとなえているにちがいないと思いながら、私も川の上流に向かって、声を張って呪文をとなえ、新しい白木の手桶(ておけ)に入れてきた洗米と切弊(きりぬさ)を水の神に祈って散米して、澄み透った水を流れに逆らう形で桶にくみ取る。
万さんは帰りの坂道で、重い手桶を持った私をささえながら、「坊さんもやがて立派な神主さんになって、お父さんのあとを継ぎなさるんやなぁ。三十五代目の大きなふし目の神主さんですぞ」と感慨ふかい様子でいう。祖父のころから三十年も家に居て、家族のようになっている人だ。
私は万さんの話よりも、この細々とした雲出川の流れが、幾つもの村々を流れ下って、やがて伊勢湾にそそぎ入る、まだ実際には見たことのない、青々とした海と空の涯(はて)しない広がりを空想して、ひそかに胸をときめかしている。やがて海抜千メートルの山々にかこまれた山あいの小さな盆地にも、東の空の暁の色がほのかにとどき始めた。
家に帰ると母はねぎらいの言葉をかけながら若水を受け取り、茶釜で福茶のお湯をわかしにかかる。初めて大人にまじって年初の行事の一役をつとめたという興奮の中で、祭りを終って帰ってきた父に、さっき川辺で思った海への連想を話してみたくなった。「お父さん、ぼくはまだ海を見たことがない。早く海を見たい」。自分の言葉が思いがけず唐突になったのにとまどっていると、父の答えはさらに思いがけなかった。
「谷川で若水をくみながら海を思ったのか。それは面白い。山の村へ来られる正月さまは、空から山を伝って谷川や尾根道を村里へ降りて来られる。ところが海岸の村では、正月さまは遠い海の彼方(かなた)から、青波の上を渡って新しい年の幸福を運んで来て下さる。それがこの日本列島に住む者の信じている神さまの姿なのだ」と語ってくれた。
思えば父も母も若かった。八十を過ぎた今も、匂(にお)うような正月の母の姿を忘れない。
餅花のすがしき土間におりたてる
睦月の母の声徹るなり
(東京新聞 2007年1月4日夕刊に掲載)
今様 昔話 ― この世にはあらぬむごき話して、人の世のあはれを知るが、まことの昔話なりしものを
・昔話は心の伝統。安易に内容を作り変えてはいけない
「昔話というのは、本来、大変厳しい、荒々しい、むごい要素を持っているわけです。それが、戦後、限りなく優しいものだけをよしとする時代になって、敗戦後の日本人たちの中で、そういう話を子供たちに与えることをやめましょうという運動が起こった。あるいは語り変えてしまう、話の内容まで変えてしまう、よその国のグリムの話まで全部変えてしまう、そんな本が出たわけです。僕は、我々の祖先たちの心の伝統というものを無視した何と知識の貧しい人たちだろうと思っていました。」
・言葉狩りについて
「我々日本人の長い英知、人間としてのよりよい生き方というのはこういうものだったんだよ、ということを教えてくれるのは、やはり古典なんです。そして、歴史よりもより細やかにその心を伝えてくれるのは、我々の祖先たちが残していった文学遺産ですけれども、そういうものが、一部のプランナーの思いつきみたいな形で、ひょいひょいと変えられていく軽薄な世の中というものをつくづく思わないではいられないわけです。」
<今様 昔話>
鳥けもの 飢ゑてさすらひ殺さるる 哀れをすらや。人は楽しむ
鋏もて舌を切らるる子雀の かなしき声を 親は語らず
血まみれの子を抱(いだ)く母。今の世の酒呑(しゅてん)童子は 車馳せくる
森ふかく木の実拾ふと入りゆきて 子らは帰らず。夕焼くる空
呼び交し ちるちる みちる啼く声は 鬼の竈(かまど)に煮られゆく子ら
親が子を 子が親を殺す世なりけり。継子話もかたる甲斐なき
赤頭巾が 白き頭巾を看とりゆく 森の奥処(おくか)の闇 おそろしき
母の乳房くちに含みて とろとろと 老いの心は 呆けゆくなり
主上は、夢のやうにいみじきことを聞かせたまひて、いろいろに思し乱れさせたまふ。
主上は、夢のやうにいみじきことを聞かせたまひて、いろいろに思し乱れさせたまふ。
「故院の御ためもうしろめたく、大臣のかくただ人にて世に仕へたまふも、あはれにかたじけなかりける事」
かたがた思し悩みて、日たくるまで出でさせたまはねば、「かくなむ」と聞きたまひて、大臣も驚きて参りたまへるを、御覧ずるにつけても、いとど忍びがたく思し召されて、御涙のこぼれさせたまひぬるを、
「おほかた故宮の御事を、干る世なく思し召したるころなればなめり」
と見たてまつりたまふ。
その日、式部卿の親王亡せたまひぬるよし奏するに、
その日、式部卿の親王亡せたまひぬるよし奏するに、いよいよ世の中の騒がしきことを嘆き思したり。かかるころなれば、大臣は里にもえまかでたまはで、つとさぶらひたまふ。
しめやかなる御物語のついでに、
「世は尽きぬるにやあらむ、もの心細く例ならぬ心地なむするを、天の下もかくのどかならぬに、よろづあわたたしくなむ。故宮の思さむところによりてこそ、世間のことも思ひ憚りつれ、今は心やすきさまにても過ぐさまほしくなむ」
と語らひきこえたまふ。
「いとあるまじき御ことなり。世の静かならぬことは、かならず政事の直く、ゆがめるにもよりはべらず。さかしき世にしもなむ、よからぬことどももはべりける。聖の帝の世にも、横様の乱れ出で来ること、唐土にもはべりける。わが国にもさなむはべる。まして、ことわりの齢どもの、時至りぬるを、思し嘆くべきことにもはべらず」
など、すべて多くのことどもを聞こえたまふ。片端まねぶも、いとかたはらいたしや。
常よりも黒き御装ひに、やつしたまへる御容貌、違ふところなし。主上も、年ごろ御鏡にも、思しよることなれど、聞こし召ししことの後は、またこまかに見たてまつりたまひつつ、ことにいとあはれに思し召さるれば、「いかで、このことをかすめ聞こえばや」と思せど、さすがに、はしたなくも思しぬべきことなれば、若き御心地につつましくて、ふともえうち出できこえたまはぬほどは、ただおほかたのことどもを、常よりことになつかしう聞こえさせたまふ。
うちかしこまりたまへるさまにて、いと御けしきことなるを、かしこき人の御目には、あやしと見たてまつりたまへど、いとかく、さださだと聞こし召したらむとは思さざりけり。
主上は、王命婦に詳しきことは、問はまほしう思し召せど、
主上は、王命婦に詳しきことは、問はまほしう思し召せど、
「今さらに、しか忍びたまひけむこと知りにけりと、かの人にも思はれじ。ただ、大臣にいかでほのめかし問ひきこえて、先々のかかる事の例はありけりやと問ひ聞かむ」
とぞ思せど、さらについでもなければ、いよいよ御学問をせさせたまひつつ、さまざまの書どもを御覧ずるに、
「唐土には、現はれても忍びても、乱りがはしき事いと多かりけり。日本には、さらに御覧じ得るところなし。たとひあらむにても、かやうに忍びたらむことをば、いかでか伝へ知るやうのあらむとする。一世の源氏、また納言、大臣になりて後に、さらに親王にもなり、位にも即きたまへるも、あまたの例ありけり。人柄のかしこきにことよせて、さもや譲りきこえまし」
など、よろづにぞ思しける。
秋の司召に、太政大臣になりたまふべきこと、うちうちに定め申したまふついでになむ、
秋の司召に、太政大臣になりたまふべきこと、うちうちに定め申したまふついでになむ、帝、思し寄する筋のこと、漏らしきこえたまひけるを、大臣、いとまばゆく、恐ろしう思して、さらにあるまじきよしを申し返したまふ。
「故院の御心ざし、あまたの皇子たちの御中に、とりわきて思し召しながら、位を譲らせたまはむことを思し召し寄らずなりにけり。何か、その御心改めて、及ばぬ際には昇りはべらむ。ただ、もとの御おきてのままに、朝廷に仕うまつりて、今すこしの齢かさなりはべりなば、のどかなる行なひに籠もりはべりなむと思ひたまふる」
と、常の御言の葉に変はらず奏したまへば、いと口惜しうなむ思しける。
太政大臣になりたまふべき定めあれど、しばし、と思すところありて、ただ御位添ひて、牛車聴されて参りまかでしたまふを、帝、飽かず、かたじけなきものに思ひきこえたまひて、なほ親王になりたまふべきよしを思しのたまはすれど、
「世の中の御後見したまふべき人なし。権中納言、大納言になりて、右大将かけたまへるを、今一際あがりなむに、何ごとも譲りてむ。さて後に、ともかくも、静かなるさまに」
とぞ思しける。
なほ思しめぐらすに、 「故宮の御ためにもいとほしう、
なほ思しめぐらすに、
「故宮の御ためにもいとほしう、また主上のかく思し召し悩めるを見たてまつりたまふもかたじけなきに、誰れかかることを漏らし奏しけむ」
と、あやしう思さる。
命婦は、御匣殿の替はりたる所に移りて、曹司たまはりて参りたり。大臣、対面したまひて、
「このことを、もし、もののついでに、露ばかりにても漏らし奏したまふことやありし」
と案内したまへど、
「さらに。かけても聞こし召さむことを、いみじきことに思し召して、かつは、罪得ることにやと、主上の御ためを、なほ思し召し嘆きたりし」
と聞こゆるにも、ひとかたならず心深くおはせし御ありさまなど、尽きせず恋ひきこえたまふ。
斎宮の女御は、思ししもしるき御後見にて、やむごとなき御おぼえなり。
斎宮の女御は、思ししもしるき御後見にて、やむごとなき御おぼえなり。御用意、ありさまなども、思ふさまにあらまほしう見えたまへれば、かたじけなきものにもてかしづききこえたまへり。
秋のころ、二条院にまかでたまへり。寝殿の御しつらひ、いとど輝くばかりしたまひて、今はむげの親ざまにもてなして、扱ひきこえたまふ。
秋の雨いと静かに降りて、御前の前栽の色々乱れたる露のしげさに、いにしへのことどもかき続け思し出でられて、御袖も濡れつつ、女御の御方に渡りたまへり。こまやかなる鈍色の御直衣姿にて、世の中の騒がしきなどことつけたまひて、やがて御精進なれば、数珠ひき隠して、さまよくもてなしたまへる、尽きせずなまめかしき御ありさまにて、御簾の内に入りたまひぬ。御几帳ばかりを隔てて、みづから聞こえたまふ。
「前栽どもこそ残りなく紐解きはべりにけれ。
「前栽どもこそ残りなく紐解きはべりにけれ。いとものすさまじき年なるを、心やりて時知り顔なるも、あはれにこそ」
とて、柱に寄りゐたまへる夕ばえ、いとめでたし。昔の御ことども、かの野の宮に立ちわづらひし曙などを、聞こえ出でたまふ。いとものあはれと思したり。
宮も、「かくれば」とにや、すこし泣きたまふけはひ、いとらうたげにて、うち身じろきたまふほども、あさましくやはらかになまめきておはすべかめる。「見たてまつらぬこそ、口惜しけれ」と、胸のうちつぶるるぞ、うたてあるや。
「過ぎにし方、ことに思ひ悩むべきこともなくてはべりぬべかりし世の中にも、
「過ぎにし方、ことに思ひ悩むべきこともなくてはべりぬべかりし世の中にも、なほ心から、好き好きしきことにつけて、もの思ひの絶えずもはべりけるかな。さるまじきことどもの、心苦しきが、あまたはべりし中に、つひに心も解けず、むすぼほれて止みぬること、二つなむはべる。
一つは、この過ぎたまひにし御ことよ。あさましうのみ思ひつめて止みたまひにしが、長き世の愁はしきふしと思ひたまへられしを、かうまでも仕うまつり、御覧ぜらるるをなむ、慰めに思うたまへなせど、燃えし煙の、むすぼほれたまひけむは、なほいぶせうこそ思ひたまへらるれ」
とて、今一つはのたまひさしつ。
「中ごろ、身のなきに沈みはべりしほど、方々に思ひたまへしことは、
「中ごろ、身のなきに沈みはべりしほど、方々に思ひたまへしことは、片端づつかなひにたり。東の院にものする人の、そこはかとなくて、心苦しうおぼえわたりはべりしも、おだしう思ひなりにてはべり。心ばへの憎からぬなど、我も人も見たまへあきらめて、いとこそさはやかなれ。
かく立ち返り、朝廷の御後見仕うまつるよろこびなどは、さしも心に深く染まず、かやうなる好きがましき方は、静めがたうのみはべるを、おぼろけに思ひ忍びたる御後見とは、思し知らせたまふらむや。あはれとだにのたまはせずは、いかにかひなくはべらむ」
とのたまへば、むつかしうて、御応へもなければ、
「さりや。あな心憂」
とて、異事に言ひ紛らはしたまひつ。
「今は、いかでのどやかに、生ける世の限り、思ふこと残さず、後の世の勤めも心にまかせて、籠もりゐなむと思ひはべるを、この世の思ひ出にしつべきふしのはべらぬこそ、さすがに口惜しうはべりぬべけれ。かならず、幼き人のはべる、生ひ先いと待ち遠なりや、かたじけなくとも、なほ、この門広げさせたまひて、はべらずなりなむ後にも、数まへさせたまへ」
など聞こえたまふ。
御応へは、いとおほどかなるさまに、からうして一言ばかりかすめたまへるけはひ、いとなつかしげなるに聞きつきて、しめじめと暮るるまでおはす。
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第88回 「薄雲」より その4 |
|---|---|
| 収録日 | 2007年1月20日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
平成18年秋期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。