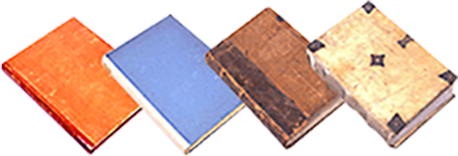第128回 「藤裏葉」より その1
冒頭、ベッドの上に短冊が置いてあるホテルの話をし、本文に。宰相の中将(夕霧)と女君(雲居雁)はちぐはぐな状態で、(内)大臣は、譲って折れておくべきだろう、と考えるようになった。館の藤の花が盛りのときに、内大臣は夕霧に文を出し、大臣(源氏)は直衣の色にも気を使って夕霧を送り出す。宴が催され、酔った夕霧は中将(柏木)に泊まらせて欲しいと頼み、柏木は雲居雁のところへ夕霧を案内した。

講師:岡野弘彦
- 目次
-
- ベッドの上の短冊
- 藤裏葉の巻について
- 御いそぎのほどにも、宰相中将は眺めがちにて、
- 大臣も、さこそ心強がりたまひしかど、
- 上はつれなくて、恨み解けぬ御仲なれば、
- 夕かけて、皆帰りたまふほど、花は皆散り乱れ、
- 心あわたたしき雨風に、皆ちりぢりに競ひ帰りたまひぬ。
- ここらの年ごろの思ひのしるしにや、かの大臣も、名残なく思し弱りて、
- 大臣の御前に、かくなむ、とて、御覧ぜさせたまふ。
- わが御方にて、心づかひいみじう化粧じて、たそかれも過ぎ、
- 月はさし出でぬれど、花の色さだかにも見えぬほどなるを、
- 「君は、末の世にはあまるまで、天の下の有職にものしたまふめるを、
- 「いかでか。昔を思うたまへ出づる御変はりどもには、
- 七日の夕月夜、影ほのかなるに、池の鏡のどかに澄みわたれり。
- やうやう夜更け行くほどに、いたうそら悩みして、
ベッドの上の短冊
・ベッドの上に短冊を置くホテル
日本のホテルは不思議なところ
バイブルと仏典は置いてあるが、日本の神話である古事記が置いてない。
月は船 星は白波 雲は海
如何に漕ぐらん
桂男は唯一人して
(梁塵秘抄)
天の海に 雲の波立ち 月の船
星の林に 榜ぎ隠る見ゆ
(柿本人麻呂)
反応のない日本人、面白がる外国人
・日本の伝統文学の不思議な力
調べと語彙が違う天皇の歌
至尊風の調べ、至尊風の格調(折口信夫)
わが国のたちなほり来し年どしに
あけぼのすぎの木はのびにけり
(昭和天皇)
日本の文学史のバックボーンは二十一代の勅撰和歌集 (丸谷才一)
勅撰和歌集が選ばれなくなってから五百年、それでもなおその力は、いろんな形でにじみ出ている。
藤裏葉の巻について
・藤原氏がモデルの左大臣家が催す藤の花の宴が中心となっている巻
・藤原氏に縁のある藤の花の花の宴、そしてそれは紫のゆかりを踏んでいる
御いそぎのほどにも、宰相中将は眺めがちにて、
藤裏葉
御いそぎのほどにも、宰相中将は眺めがちにて、ほれぼれしき心地するを、「かつはあやしく、わが心ながら執念きぞかし。あながちにかう思ふことならば、関守の、うちも寝ぬべきけしきに思ひ弱りたまふなるを聞きながら、同じくは、人悪からぬさまに見果てむ」と念ずるも、苦しう思ひ乱れたまふ。
女君も、大臣のかすめたまひしことの筋を、「もし、さもあらば、何の名残かは」と嘆かしうて、あやしく背き背きに、さすがなる御もろ恋なり。
大臣も、さこそ心強がりたまひしかど、
大臣も、さこそ心強がりたまひしかど、たけからぬに思しわづらひて、「かの宮にも、さやうに思ひ立ち果てたまひなば、またとかく改め思ひかかづらはむほど、人のためも苦しう、わが御方ざまにも人笑はれに、おのづから軽々しきことやまじらむ。忍ぶとすれど、うちうちのことあやまりも、世に漏りにたるべし。とかく紛らはして、なほ負けぬべきなめり」と、思しなりぬ。
上はつれなくて、恨み解けぬ御仲なれば、
上はつれなくて、恨み解けぬ御仲なれば、「ゆくりなく言ひ寄らむもいかが」と、思し憚りて、「ことことしくもてなさむも、人の思はむところをこなり。いかなるついでしてかはほのめかすべき」など思すに、三月二十日、大殿の大宮の御忌日にて、極楽寺に詣でたまへり。
君達皆ひき連れ、勢ひあらまほしく、上達部などもあまた参り集ひたまへるに、宰相中将、をさをさけはひ劣らず、よそほしくて、容貌など、ただ今のいみじき盛りにねびゆきて、取り集めめでたき人の御ありさまなり。
この大臣をば、つらしと思ひきこえたまひしより、見えたてまつるも、心づかひせられて、いといたう用意し、もてしづめてものしたまふを、大臣も、常よりは目とどめたまふ。御誦経など、六条院よりもせさせたまへり。宰相君は、まして、よろづをとりもちて、あはれにいとなみ仕うまつりたまふ。
夕かけて、皆帰りたまふほど、花は皆散り乱れ、
夕かけて、皆帰りたまふほど、花は皆散り乱れ、霞たどたどしきに、大臣、昔を思し出でて、なまめかしううそぶき眺めたまふ。宰相も、あはれなる夕べのけしきに、いとどうちしめりて、「雨気あり」と、人びとの騒ぐに、なほ眺め入りてゐたまへり。心ときめきに見たまふことやありけむ、袖を引き寄せて、
「などか、いとこよなくは勘じたまへる。今日の御法の縁をも尋ね思さば、罪許したまひてよや。残り少なくなりゆく末の世に、思ひ捨てたまへるも、恨みきこゆべくなむ」
とのたまへば、うちかしこまりて、
「過ぎにし御おもむけも、頼みきこえさすべきさまに、うけたまはりおくことはべりしかど、許しなき御けしきに、憚りつつなむ」
と聞こえたまふ。
心あわたたしき雨風に、皆ちりぢりに競ひ帰りたまひぬ。
心あわたたしき雨風に、皆ちりぢりに競ひ帰りたまひぬ。君、「いかに思ひて、例ならずけしきばみたまひつらむ」など、世とともに心をかけたる御あたりなれば、はかなきことなれど、耳とまりて、とやかうやと思ひ明かしたまふ。
ここらの年ごろの思ひのしるしにや、かの大臣も、名残なく思し弱りて、
ここらの年ごろの思ひのしるしにや、かの大臣も、名残なく思し弱りて、はかなきついでの、わざとはなく、さすがにつきづきしからむを思すに、四月の朔日ごろ、御前の藤の花、いとおもしろう咲き乱れて、世の常の色ならず、ただに見過ぐさむこと惜しき盛りなるに、遊びなどしたまひて、暮れ行くほどの、いとど色まされるに、頭中将して、御消息あり。
「一日の花の蔭の対面の、飽かずおぼえはべりしを、御暇あらば、立ち寄りたまひなむや」
とあり。御文には、
「わが宿の藤の色濃きたそかれに
尋ねやは来ぬ春の名残を」
げに、いとおもしろき枝につけたまへり。待ちつけたまへるも、心ときめきせられて、かしこまりきこえたまふ。
「なかなかに折りやまどはむ藤の花
たそかれ時のたどたどしくは」
と聞こえて、
「口惜しくこそ臆しにけれ。取り直したまへよ」
と聞こえたまふ。
「御供にこそ」
とのたまへば、
「わづらはしき随身は、否」
とて、返しつ。
大臣の御前に、かくなむ、とて、御覧ぜさせたまふ。
大臣の御前に、かくなむ、とて、御覧ぜさせたまふ。
「思ふやうありてものしたまへるにやあらむ。さも進みものしたまはばこそは、過ぎにし方の孝なかりし恨みも解けめ」
とのたまふ。御心おごり、こよなうねたげなり。
「さしもはべらじ。対の前の藤、常よりもおもしろう咲きてはべるなるを、静かなるころほひなれば、遊びせむなどにやはべらむ」
と申したまふ。
「わざと使ひさされたりけるを、早うものしたまへ」
と許したまふ。いかならむと、下には苦しう、ただならず。
「直衣こそあまり濃くて、軽びためれ。非参議のほど、何となき若人こそ、二藍はよけれ、ひき繕はむや」
とて、わが御料の心ことなるに、えならぬ御衣ども具して、御供に持たせてたてまつれたまふ。
わが御方にて、心づかひいみじう化粧じて、たそかれも過ぎ、
わが御方にて、心づかひいみじう化粧じて、たそかれも過ぎ、心やましきほどに参うでたまへり。主人の君達、中将をはじめて、七、八人うち連れて迎ヘ入れたてまつる。いづれとなくをかしき容貌どもなれど、なほ、人にすぐれて、あざやかにきよらなるもなから、なつかしう、よしづき、恥づかしげなり。
大臣、御座ひきつくろはせなどしたまふ御用意、おろかならず。御冠などしたまひて、出でたまふとて、北の方、若き女房などに、
「覗きて見たまへ。いと警策にねびまさる人なり。用意などいと静かに、ものものしや。あざやかに、抜け出でおよすけたる方は、父大臣にもまさりざまにこそあめれ。
かれは、ただいと切になまめかしう愛敬づきて、見るに笑ましく、世の中忘るる心地ぞしたまふ。公ざまは、すこしたはれて、あざれたる方なりし、ことわりぞかし。
これは、才の際もまさり、心もちゐ男々しく、すくよかに足らひたりと、世におぼえためり」
などのたまひてぞ、対面したまふ。ものまめやかに、むべむべしき御物語は、すこしばかりにて、花の興に移りたまひぬ。
「春の花、いづれとなく、皆開け出づる色ごとに、目おどろかぬはなきを、心短くうち捨てて散りぬるが、恨めしうおぼゆるころほひ、この花のひとり立ち後れて、夏に咲きかかるほどなむ、あやしう心にくくあはれにおぼえはべる。色もはた、なつかしきゆかりにしつべし」
とて、うちほほ笑みたまへる、けしきありて、匂ひきよげなり。
月はさし出でぬれど、花の色さだかにも見えぬほどなるを、
月はさし出でぬれど、花の色さだかにも見えぬほどなるを、もてあそぶに心を寄せて、大酒参り、御遊びなどしたまふ。大臣、ほどなく空酔ひをしたまひて、乱りがはしく強ひ酔はしたまふを、さる心して、いたうすまひ悩めり。
「君は、末の世にはあまるまで、天の下の有職にものしたまふめるを、
「君は、末の世にはあまるまで、天の下の有職にものしたまふめるを、齢古りぬる人、思ひ捨てたまふなむつらかりける。文籍にも、家礼といふことあるべくや。なにがしの教へも、よく思し知るらむと思ひたまふるを、いたう心悩ましたまふと、恨みきこゆべくなむ」
などのたまひて、酔ひ泣きにや、をかしきほどにけしきばみたまふ。
「いかでか。昔を思うたまへ出づる御変はりどもには、
「いかでか。昔を思うたまへ出づる御変はりどもには、身を捨つるさまにもとこそ、思うたまへ知りはべるを、いかに御覧じなすことにかはべらむ。もとより、おろかなる心のおこたりにこそ」
と、かしこまりきこえたまふ。御時よく、さうどきて、
「藤の裏葉の」
とうち誦じたまへる、御けしきを賜はりて、頭中将、花の色濃く、ことに房長きを折りて、客人の御盃に加ふ。取りて、もて悩むに、大臣、
「紫にかことはかけむ藤の花
まつより過ぎてうれたけれども」
宰相、盃を持ちながら、けしきばかり拝したてまつりたまへるさま、いとよしあり。
「いく返り露けき春を過ぐし来て
花の紐解く折にあふらむ」
頭中将に賜へば、
「たをやめの袖にまがへる藤の花
見る人からや色もまさらむ」
次々順流るめれど、酔ひの紛れにはかばかしからで、これよりまさらず。
七日の夕月夜、影ほのかなるに、池の鏡のどかに澄みわたれり。
七日の夕月夜、影ほのかなるに、池の鏡のどかに澄みわたれり。げに、まだほのかなる梢どもの、さうざうしきころなるに、いたうけしきばみ横たはれる松の、木高きほどにはあらぬに、かかれる花のさま、世の常ならずおもしろし。
例の、弁少将、声いとなつかしくて、「葦垣」を謡ふ。大臣、
「いとけやけうも仕うまつるかな」
と、うち乱れたまひて、
「年経にけるこの家の」
と、うち加へたまへる御声、いとおもしろし。をかしきほどに乱りがはしき御遊びにて、もの思ひ残らずなりぬめり。
催馬楽 葦垣
葦垣真垣 真垣かきわけ てふ越すと 負ひ越すと 誰
てふ越すと 誰か誰か このことを 親に 申よこし申しし
とどろける この家 この家の 弟嫁 親に 申よこしけらしも
あめつちの 神も神も 証したべ 我は 申よこし申さず
菅の根の すがな すがなきことを 我は聞く 我は聞くかな
やうやう夜更け行くほどに、いたうそら悩みして、
やうやう夜更け行くほどに、いたうそら悩みして、
「乱り心地いと堪へがたうて、まかでむ空もほとほとしうこそはべりぬべけれ。宿直所譲りたまひてむや」
と、中将に愁へたまふ。大臣、
「朝臣や、御休み所求めよ。翁いたう酔ひ進みて無礼なれば、まかり入りぬ」
と言ひ捨てて、入りたまひぬ。
中将、
「花の蔭の旅寝よ。いかにぞや、苦しきしるべにぞはべるや」
と言へば、
「松に契れるは、あだなる花かは。ゆゆしや」
と責めたまふ。中将は、心のうちに、「ねたのわざや」と思ふところあれど、人ざまの思ふさまにめでたきに、「かうもあり果てなむ」と、心寄せわたることなれば、うしろやすく導きつ。
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第128回 「藤裏葉」より その1 |
|---|---|
| 収録日 | 2009年7月25日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
平成21年春期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。