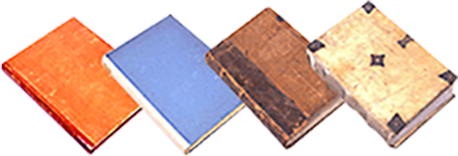第144回 「若菜下」より その2
(蛍)兵部卿宮は真木柱(大宮(式部卿宮)の孫)と結婚するが、幸せとはいえない。内裏の帝(冷泉院)は病気になり、譲位され、人事の異動がある。対の上(紫の上)は出家を希望するが源氏は許さない。源氏は住吉を参詣する。

講師:岡野弘彦
兵部卿宮、なほ一所のみおはして、
兵部卿宮、なほ一所のみおはして、御心につきて思しけることどもは、皆違ひて、世の中もすさまじく、人笑へに思さるるに、「さてのみやはあまえて過ぐすべき」と思して、このわたりにけしきばみ寄りたまへれば、大宮、
「何かは。かしづかむと思はむ女子をば、宮仕へに次ぎては、親王たちにこそは見せたてまつらめ。ただ人の、すくよかに、なほなほしきをのみ、今の世の人のかしこくする、品なきわざなり」
とのたまひて、いたくも悩ましたてまつりたまはず、受け引き申したまひつ。
親王、あまり怨みどころなきを、さうざうしと思せど、おほかたのあなづりにくきあたりなれば、えしも言ひすべしたまはで、おはしましそめぬ。いと二なくかしづききこえたまふ。
大宮は、女子あまたものしたまひて、
大宮は、女子あまたものしたまひて、
「さまざまもの嘆かしき折々多かるに、物懲りしぬべけれど、なほこの君のことの思ひ放ちがたくおぼえてなむ。母君は、あやしきひがものに、年ごろに添へてなりまさりたまふ。大将はた、わがことに従はずとて、おろかに見捨てられためれば、いとなむ心苦しき」
とて、御しつらひをも、立ちゐ、御手づから御覧じ入れ、よろづにかたじけなく御心に入れたまへり。
宮は、亡せたまひにける北の方を、
宮は、亡せたまひにける北の方を、世とともに恋ひきこえたまひて、「ただ、昔の御ありさまに似たてまつりたらむ人を見む」と思しけるに、「悪しくはあらねど、さま変はりてぞものしたまひける」と思すに、口惜しくやありけむ、通ひたまふさま、いともの憂げなり。
大宮、「いと心づきなきわざかな」と思し嘆きたり。母君も、さこそひがみたまへれど、うつし心出で来る時は、「口惜しく憂き世」と、思ひ果てたまふ。
大将の君も、「さればよ。いたく色めきたまへる親王を」と、はじめよりわが御心に許したまはざりしことなればにや、ものしと思ひたまへり。
尚侍の君も、かく頼もしげなき御さまを、
尚侍の君も、かく頼もしげなき御さまを、近く聞きたまふには、「さやうなる世の中を見ましかば、こなたかなた、いかに思し見たまはまし」など、なまをかしくも、あはれにも思し出でけり。
「そのかみも、気近く見聞こえむとは、思ひ寄らざりきかし。ただ、情け情けしう、心深きさまにのたまひわたりしを、あへなくあはつけきやうにや、聞き落としたまひけむ」と、いと恥づかしく、年ごろも思しわたることなれば、「かかるあたりにて、聞きたまはむことも、心づかひせらるべく」など思す。
これよりも、さるべきことは扱ひきこえたまふ。
これよりも、さるべきことは扱ひきこえたまふ。せうとの君たちなどして、かかる御けしきも知らず顔に、憎からず聞こえまつはしなどするに、心苦しくて、もて離れたる御心はなきに、大北の方といふさがな者ぞ、常に許しなく怨じきこえたまふ。
「親王たちは、のどかに二心なくて、見たまはむをだにこそ、はなやかならぬ慰めには思ふべけれ」
とむつかりたまふを、宮も漏り聞きたまひては、「いと聞きならはぬことかな。昔、いとあはれと思ひし人をおきても、なほ、はかなき心のすさびは絶えざりしかど、かう厳しきもの怨じは、ことになかりしものを」、心づきなく、いとど昔を恋ひきこえたまひつつ、故里にうち眺めがちにのみおはします。さ言ひつつも、二年ばかりになりぬれば、かかる方に目馴れて、ただ、さる方の御仲にて過ぐしたまふ。
はかなくて、年月もかさなりて、
はかなくて、年月もかさなりて、内裏の帝、御位に即かせたまひて、十八年にならせたまひぬ。
「嗣の君とならせたまふべき御子おはしまさず、ものの栄なきに、世の中はかなくおぼゆるを、心やすく、思ふ人びとにも対面し、私ざまに心をやりて、のどかに過ぎまほしくなむ」
と、年ごろ思しのたまはせつるを、日ごろいと重く悩ませたまふことありて、にはかに下りゐさせたまひぬ。世の人、「飽かず盛りの御世を、かく逃れたまふこと」と惜しみ嘆けど、春宮もおとなびさせたまひにたれば、うち嗣ぎて、世の中の政事など、ことに変はるけぢめもなかりけり。
玉上琢弥氏の解釈との違い
・玉上琢弥さんの角川書店から出ている大部にわたる本(『源氏物語評釈』)は、源氏物語の構成、背後の人物関係、有職故実が細かく考証せられて、便利な本である。
・『源氏物語』に関して、玉上さんは「おとぎ話」という比喩を使っているが、僕は「日本人の心の中にある神話体系」といった方がよく分かると思う。
太政大臣、致仕の表たてまつりて、
太政大臣、致仕の表たてまつりて、籠もりゐたまひぬ。
世の中の常なきにより、かしこき帝の君も、位を去りたまひぬるに、年深き身の冠を挂けむ、何か惜しからむ」と思しのたまひて、左大将、右大臣になりたまひてぞ、世の中の政事仕うまつりたまひける。女御の君は、かかる御世をも待ちつけたまはで、亡せたまひにければ、限りある御位を得たまへれど、ものの後ろの心地して、かひなかりけり。
六条の女御の御腹の一の宮、坊にゐたまひぬ。さるべきこととかねて思ひしかど、さしあたりてはなほめでたく、目おどろかるるわざなりけり。右大将の君、大納言になりたまひぬ。いよいよあらまほしき御仲らひなり。
六条院は、下りゐたまひぬる冷泉院の、
六条院は、下りゐたまひぬる冷泉院の、御嗣おはしまさぬを、飽かず御心のうちに思す。同じ筋なれど、思ひ悩ましき御ことならで、過ぐしたまへるばかりに、罪は隠れて、末の世まではえ伝ふまじかりける御宿世、口惜しくさうざうしく思せど、人にのたまひあはせぬことなれば、いぶせくなむ。
春宮の女御は、
春宮の女御は、御子たちあまた数添ひたまひて、いとど御おぼえ並びなし。源氏の、うち続き后にゐたまふべきことを、世人飽かず思へるにつけても、冷泉院の后は、ゆゑなくて、あながちにかくしおきたまへる御心を思すに、いよいよ六条院の御ことを、年月に添へて、限りなく思ひきこえたまへり。
院の帝、思し召ししやうに、御幸も、所狭からで渡りたまひなどしつつ、かくてしも、げにめでたくあらまほしき御ありさまなり。
姫宮の御ことは、帝、
姫宮の御ことは、帝、御心とどめて思ひきこえたまふ。おほかたの世にも、あまねくもてかしづかれたまふを、対の上の御勢ひには、えまさりたまはず。年月経るままに、御仲いとうるはしく睦びきこえ交はしたまひて、いささか飽かぬことなく、隔ても見えたまはぬものから、
「今は、かうおほぞうの住まひならで、のどやかに行なひをも、となむ思ふ。この世はかばかりと、見果てつる心地する齢にもなりにけり。さりぬべきさまに思し許してよ」
と、まめやかに聞こえたまふ折々あるを、
「あるまじく、つらき御ことなり。みづから、深き本意あることなれど、とまりてさうざうしくおぼえたまひ、ある世に変はらむ御ありさまの、うしろめたさによりこそ、ながらふれ。つひにそのこと遂げなむ後に、ともかくも思しなれ」
などのみ、妨げきこえたまふ。
女御の君、ただこなたを、
女御の君、ただこなたを、まことの御親にもてなしきこえたまひて、御方は隠れがの御後見にて、卑下しものしたまへるしもぞ、なかなか、行く先頼もしげにめでたかりける。
尼君も、ややもすれば、堪へぬよろこびの涙、ともすれば落ちつつ、目をさへ拭ひただして、命長き、うれしげなる例になりてものしたまふ。
住吉の御願、かつがつ果たしたまはむとて、
住吉の御願、かつがつ果たしたまはむとて、春宮女御の御祈りに詣でたまはむとて、かの箱開けて御覧ずれば、さまざまのいかめしきことども多かり。
年ごとの春秋の神楽に、かならず長き世の祈りを加へたる願ども、げに、かかる御勢ひならでは、果たしたまふべきこととも思ひおきてざりけり。ただ走り書きたる趣きの、才々しくはかばかしく、仏神も聞き入れたまふべき言の葉明らかなり。
「いかでさる山伏の聖心に、かかることどもを思ひよりけむ」と、あはれにおほけなくも御覧ず。「さるべきにて、しばしかりそめに身をやつしける、昔の世の行なひ人にやありけむ」など思しめぐらすに、いとど軽々しくも思されざりけり。
このたびは、この心をば表はしたまはず、
このたびは、この心をば表はしたまはず、ただ、院の御物詣でにて出で立ちたまふ。浦伝ひのもの騒がしかりしほど、そこらの御願ども、皆果たし尽くしたまへれども、なほ世の中にかくおはしまして、かかるいろいろの栄えを見たまふにつけても、神の御助けは忘れがたくて、対の上も具しきこえさせたまひて、詣でさせたまふ、響き世の常ならず。いみじくことども削ぎ捨てて、世の煩ひあるまじく、と省かせたまへど、限りありければ、めづらかによそほしくなむ。
上達部も、大臣二所をおきたてまつりては、
上達部も、大臣二所をおきたてまつりては、皆仕うまつりたまふ。舞人は、衛府の次将どもの、容貌きよげに、丈だち等しき限りを選らせたまふ。この選びに入らぬをば恥に、愁へ嘆きたる好き者どもありけり。
陪従も、石清水、賀茂の臨時の祭などに召す人びとの、道々のことにすぐれたる限りを整へさせたまへり。加はりたる二人なむ、近衛府の名高き限りを召したりける。
御神楽の方には、いと多く仕うまつれり。内裏、春宮、院の殿上人、方々に分かれて、心寄せ仕うまつる。数も知らず、いろいろに尽くしたる上達部の御馬、鞍、馬副、随身、小舎人童、次々の舎人などまで、整へ飾りたる見物、またなきさまなり。
御殿、対の上は、
女御殿、対の上は、一つに奉りたり。次の御車には、明石の御方、尼君忍びて乗りたまへり。女御の御乳母、心知りにて乗りたり。方々のひとだまひ、上の御方の五つ、女御殿の五つ、明石の御あかれの三つ、目もあやに飾りたる装束、ありさま、言へばさらなり。さるは、
「尼君をば、同じくは、老の波の皺延ぶばかりに、人めかしくて詣でさせむ」
と、院はのたまひけれど、
「このたびは、かくおほかたの響きに立ち交じらむもかたはらいたし。もし思ふやうならむ世の中を待ち出でたらば」
と、御方はしづめたまひけるを、残りの命うしろめたくて、かつがつものゆかしがりて、慕ひ参りたまふなりけり。さるべきにて、もとよりかく匂ひたまふ御身どもよりも、いみじかりける契り、あらはに思ひ知らるる人の御ありさまなり。
| コンテンツ名 | 源氏物語全講会 第144回 「若菜下」より その2 |
|---|---|
| 収録日 | 2010年10月9日 |
| 講師 | 岡野弘彦(國學院大學名誉教授) |
平成22年秋期講座 |
|
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。