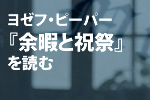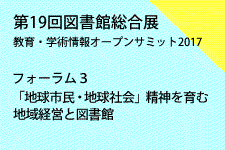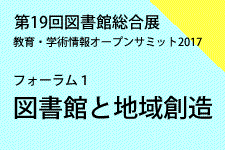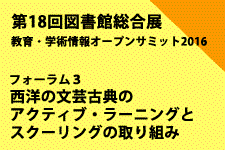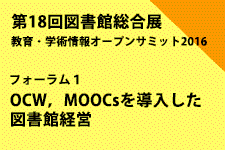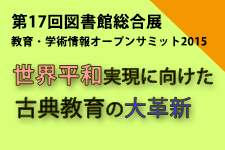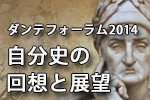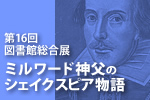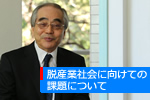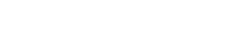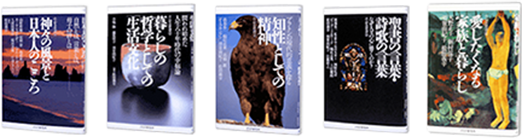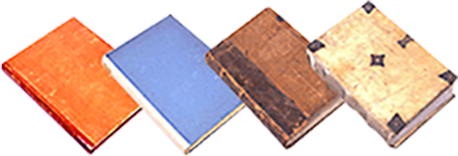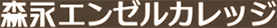講師プロフィール
松田 義幸まつだ よしゆき
尚美学園大学学長

尚美学園大学学長・森永エンゼル財団理事。専門分野は生活文化史。日経広告研究所、余暇開発センター研究主幹、筑波大学大学院客員教授等を経て現職。日本のレジャー・文化政策策定に関する仕事に携わり、「国際価値会議」「筑波会議」など国際学術文化会議のプロデュースを数多く手がける。エンゼル叢書シリーズとして『芸術都市の誕生』(PHP研究所)などを刊行。
※肩書などはコンテンツ収録時のものです
「地球市民・地球社会」精神を育む地域経営と図書館|第19回図書館総合展フォーラム3
地域人材と図書館の役割及び新しい技術の活用や組織連携、地域間ネットワークのありかたについて、トークインを行いました。
コミュニティ・カレッジ型の図書館経営:西洋の文芸古典のアクティブ・ラーニングとスクーリングの取り組み
アクティブ・ラーニングとスクーリング事例:「ミルワード先生のシェイクスピア講義」を活用したセミナー
世界平和実現に向けた古典教育の大革新
世界平和を実現するにあたり、古典教育がどのように影響を与えられるか、どのように変化していくべきかを論じたフォーラムが。2015年11月に開催されました。
図書館総合展グレートブックス・ライブラリ・カフェ|ミルワード神父のシェイクスピア物語
これまで謎とされてきたシェイクスピアの宗教的背景と実像に迫る、ミルワード神父のシェイクスピア物語。
脱産業化に向けての課題 「余暇行政」研究の自分史
バブル経済崩壊後、余暇行政は話題にすらならなくなった。政府のどの官庁も、また都道府県も、市町村も、余暇行政を表舞台からすっかり降ろしてしまった。しかし、あの石油危機以降の大量失業問題に直面した欧米諸国はその逆であった。
脱産業化に向けての課題 「日本人の生きがい構造」研究の自分史
神谷美恵子、島崎敏樹、両教授の「生きがい」構造論を紹介し、労働生活と生きがい充実度の関係、および国際会議のレジャー憲章提案を報告する
脱産業化に向けての課題 「レジャー概念」検討の自分史
余暇開発センターの私たちの研究グループは、1975 年4月から5年にわたる基礎研究プロジェクト「新しい人間、新しい社会」をスタートさせることになった。
脱産業化に向けての課題 レジャー研究の自分史 (3)
余暇開発センターの1973年の研究プロジェクトを振り返り、現在、日本社会が取り組んでいる構造改革に、時間配分の政策視点をつけ加えることを考察する。
脱産業化に向けての課題 レジャー研究の自分史 (1)
「レジャーとはなにか」「レジャーはいかにあるべきか」。私自身のレジャー研究の自分史を振り返り、レジャー問題の重要性を再度提起したいと思う。
脱産業化に向けての課題 論文「脱産業社会に向けての課題」について(松田義幸)
モノの豊かさから、心の豊かさへ。成熟社会を迎えて、日本人のこころも移り変わってきた。しかし、われわれは今もなお、余暇の重要性を本当に受けとめているとはいえない。40年以上にわたりレジャー哲学を研究してきた著者が語る、日本社会の真の課題。
グレート・ブックス・セミナーと生涯学習、多様なかたち
これまでの人生を、本との出会いを通じて振りかえる。若者と、そして子どもたちと本を読む歓びを分かちあう。グレート・ブックス・セミナーの多様なかたちについてお話しします。
グレート・ブックス・ライブラリ・カフェ:『神学大全』と人生哲学
毎年、図書館総合展にあわせて開催する特別フォーラム。今回(2013年)のテーマは、中世の大著、トマス・アクィナスの『神学大全』と人生哲学です。
子ども大学かわごえの革新
小中高校や大学の機能不全、学校と教育の危機が広く問題にされてきたなかで、従来の教育の枠組み・制度を越えた、新しい試みが生まれています。ドイツにはじまった「子ども大学」です。
フィレンツェに学ぶ芸術都市の経営 第4部 パネル討論
都市の経営という視点から、ルネサンスの芸術都市・フィレンツェの魅力をとらえなおす。2010年11月イタリア文化会館で開催されたフォーラムの模様。
フィレンツェに学ぶ芸術都市の経営 第3部 世界遺産からの視点(松田義幸)
都市の経営という視点から、ルネサンスの芸術都市・フィレンツェの魅力をとらえなおす。2010年11月イタリア文化会館で開催されたフォーラムの模様。
フィレンツェに学ぶ芸術都市の経営 第2部 美術史からの視点(田中英道)
都市の経営という視点から、ルネサンスの芸術都市・フィレンツェの魅力をとらえなおす。2010年11月イタリア文化会館で開催されたフォーラムの模様。
フィレンツェに学ぶ芸術都市の経営 開会にあたって
都市の経営という視点から、ルネサンスの芸術都市・フィレンツェの魅力をとらえなおす。2010年11月イタリア文化会館で開催されたフォーラムの模様。
フィレンツェに学ぶ芸術都市の経営 はじめに
都市の経営という視点から、ルネサンスの芸術都市・フィレンツェの魅力をとらえなおす。2010年11月イタリア文化会館で開催されたフォーラムの模様。
世界遺産モデル・フィレンツェに学ぶ 第3部 フィレンツェに学ぶ日本の世界遺産
2005年に開催し、 「『芸術の都・京都』から『芸術の国・日本』へ」を提言した「ダンテフォーラム 芸術都市の創造」の続編にあたります。
世界遺産モデル・フィレンツェに学ぶ 第2部 芸術からの視点
2005年に開催し、 「『芸術の都・京都』から『芸術の国・日本』へ」を提言した「ダンテフォーラム 芸術都市の創造」の続編にあたります。
世界遺産モデル・フィレンツェに学ぶ 第1部 歴史からの視点
2005年に開催し、 「『芸術の都・京都』から『芸術の国・日本』へ」を提言した「ダンテフォーラム 芸術都市の創造」の続編にあたります。
世界遺産モデル・フィレンツェに学ぶ 今日のテーマについて
2005年に開催し、 「『芸術の都・京都』から『芸術の国・日本』へ」を提言した「ダンテフォーラム 芸術都市の創造」の続編にあたります。
世界遺産モデル・フィレンツェに学ぶ はじめに
2005年に開催し、 「『芸術の都・京都』から『芸術の国・日本』へ」を提言した「ダンテフォーラム 芸術都市の創造」の続編にあたります。
フィレンツェに学ぶ芸術ルネサンス パネル討論 世界遺産・フィレンツェの魅力―芸術ルネサンスの故郷に学ぶ歴史の視点から―
あえて母語のトスカーナ語を用いたダンテは、その後のルネサンスにどんな影響を与えたか。母語と詩歌・人間精神の関係について考え、ルネサンスの偉業に学ぶ。
フィレンツェに学ぶ芸術ルネサンス 対話 母語・詩歌を心の糧に
あえて母語のトスカーナ語を用いたダンテは、その後のルネサンスにどんな影響を与えたか。母語と詩歌・人間精神の関係について考え、ルネサンスの偉業に学ぶ。
フィレンツェに学ぶ芸術ルネサンス はじめに
あえて母語のトスカーナ語を用いたダンテは、その後のルネサンスにどんな影響を与えたか。母語と詩歌・人間精神の関係について考え、ルネサンスの偉業に学ぶ。
『神学大全』と『神曲』の対話 シンポジウム ダンテとトマスをめぐって
中世最大の神学者トマス・アクィナスの思想を中心におき、トマスとダンテの思想上の関係と、その歴史的な背景について理解を深める。
源氏物語を世界中の人々に伝えたい シンポジウム 源氏英訳の新たな試みに向けて
カトリックの目から見た『源氏物語』とは? 『源氏物語』の英訳はどのように変化してきたか?『源氏物語』を世界文学としての視点から考えるシンポジウム。
源氏物語を世界中の人々に伝えたい はじめに
カトリックの目から見た『源氏物語』とは? 『源氏物語』の英訳はどのように変化してきたか?『源氏物語』を世界文学としての視点から考えるシンポジウム。
源氏物語全講会への期待 2003年 シンポジウム 源氏全講会への期待
国学最後の二人と呼ばれた三矢重松先生と折口信夫先生。源氏物語全講会にこめたそれぞれの思いとは何か。折口信夫没後50周年を記念して開催されたシンポジウムの模様。
源氏物語全講会への期待 2003年 はじめに
国学最後の二人と呼ばれた三矢重松先生と折口信夫先生。源氏物語全講会にこめたそれぞれの思いとは何か。折口信夫没後50周年を記念して開催されたシンポジウムの模様。
本居宣長・折口信夫・小林秀雄を辿って シンポジウム 折口信夫・小林秀雄をめぐっての対話
自分にとっての『古事記』との出会い。本居宣長、折口信夫、小林秀雄などの先人から学んだこと。 「『古事記』と日本人」をテーマに、対話したシンポジウムの模様を配信。
本居宣長・折口信夫・小林秀雄を辿って シンポジウム 本居宣長をめぐっての対話
自分にとっての『古事記』との出会い。本居宣長、折口信夫、小林秀雄などの先人から学んだこと。 「『古事記』と日本人」をテーマに、対話したシンポジウムの模様を配信。
本居宣長・折口信夫・小林秀雄を辿って シンポジウム 私にとっての『古事記』
自分にとっての『古事記』との出会い。本居宣長、折口信夫、小林秀雄などの先人から学んだこと。 「『古事記』と日本人」をテーマに、対話したシンポジウムの模様を配信。
本居宣長・折口信夫・小林秀雄を辿って はじめに
自分にとっての『古事記』との出会い。本居宣長、折口信夫、小林秀雄などの先人から学んだこと。 「『古事記』と日本人」をテーマに、対話したシンポジウムの模様を配信。
源氏物語全講会への期待 2002年
三矢重松、折口信夫の流れを継承して、平成13(2001)年に岡野弘彦「源氏物語 全講会」は始まりました。「全講会」に込めた思いが、熱く語ら れています。
新しい家族の絆をつくる 対談 家族をつなぎとめるもの
「サラサラ・フカフカ型の開かれた家族へ」「子供の自立には親子間の葛藤や対立が必要 」「ひらかれた家族へ」エンゼル・フォーラム「母親自身の生活設計4」の模様を配信
新しい家族の絆をつくる はじめに
「サラサラ・フカフカ型の開かれた家族へ」「子供の自立には親子間の葛藤や対立が必要 」「ひらかれた家族へ」エンゼル・フォーラム「母親自身の生活設計4」の模様を配信
人はなぜ「家族を生きる」のか 対談 家族の再生にむけて
「『理想の家族像』に縛られていないか?」「息苦しい家族から、道連れとしての家族へ 」エンゼル・フォーラム「母親自身の生活設計3」の模様を配信
母親自身の生活設計 対談 「生活文化」としてのライフスタイルを築くには
「今日という日は一回限りのもの」「守るに足る暮らしを持っていますか?」エンゼル・フォーラム「母親自身の生活設計」の模様を配信
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。